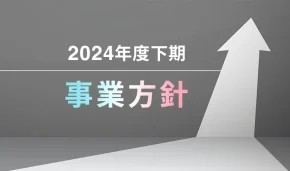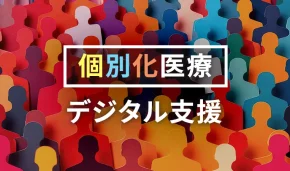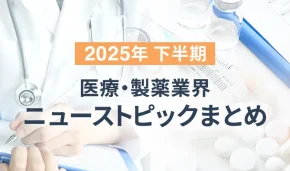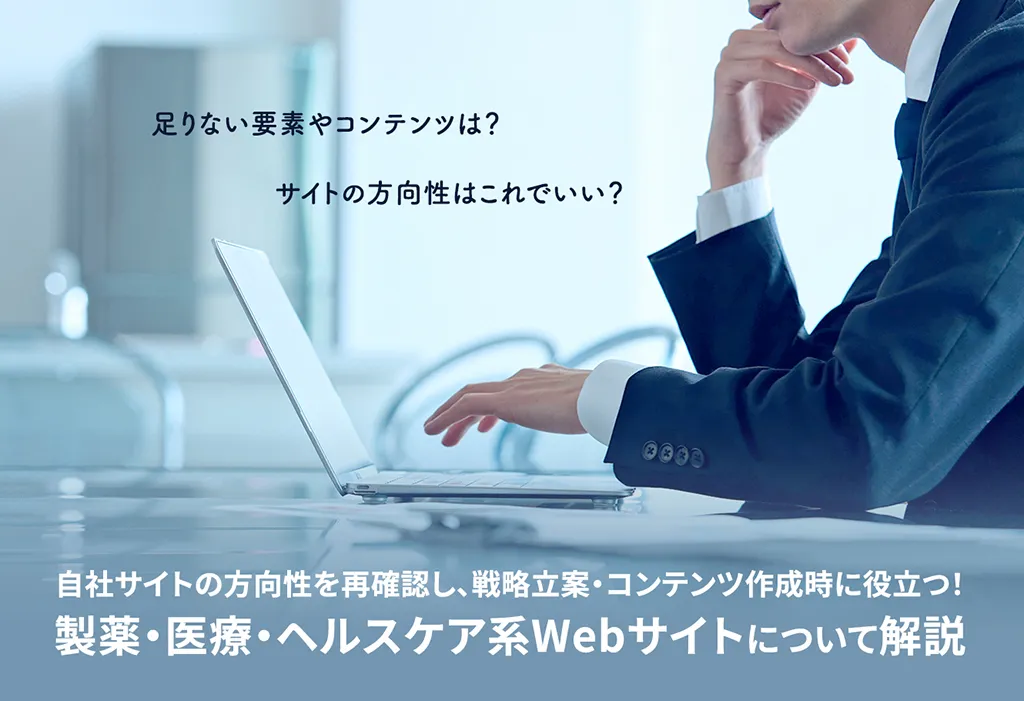
製薬・医療・ヘルスケア系Webサイトについて各サイトの目的や役割を解説していきます。これらを改めて確認することで自社サイトに足りない要素や追加コンテンツが見つけられるかもしれません。ぜひ、自社サイトの方向性を再確認し、戦略立案、コンテンツ作成時などにお役立てください。
業界別「戦略マップ」でWebサイトの立ち位置を明確化!
製薬・医療・ヘルスケア業界のWebサイトは医療従事者、研究者、投資家、一般人も含めたステークホルダーとの重要な接点となっています。Webサイトの運営を担当している方は、自社サイトの立ち位置や役割を踏まえたうえで運営できているか不安を感じていないでしょうか。各業界のWebサイトはカテゴリーごとに多種多様に存在しており、それぞれが異なる役割と目的を持っています。これらを正確に把握し、自社サイトがどこに位置付けられているかを改めて理解することで、各ステークホルダーの関心や期待に沿ったデジタル施策が実施できます。
今回は、HCPサイトから疾患啓発、患者支援、そしてコーポレートサイトに至るまで、業界特有のWebサイトの種類とその目的やターゲット、位置付けなどを徹底解説します。自社のデジタルマーケティングを次のステージへ進めるための『戦略マップ』として、ぜひご活用ください。
各Webサイトの目的や戦略的役割をチェック!
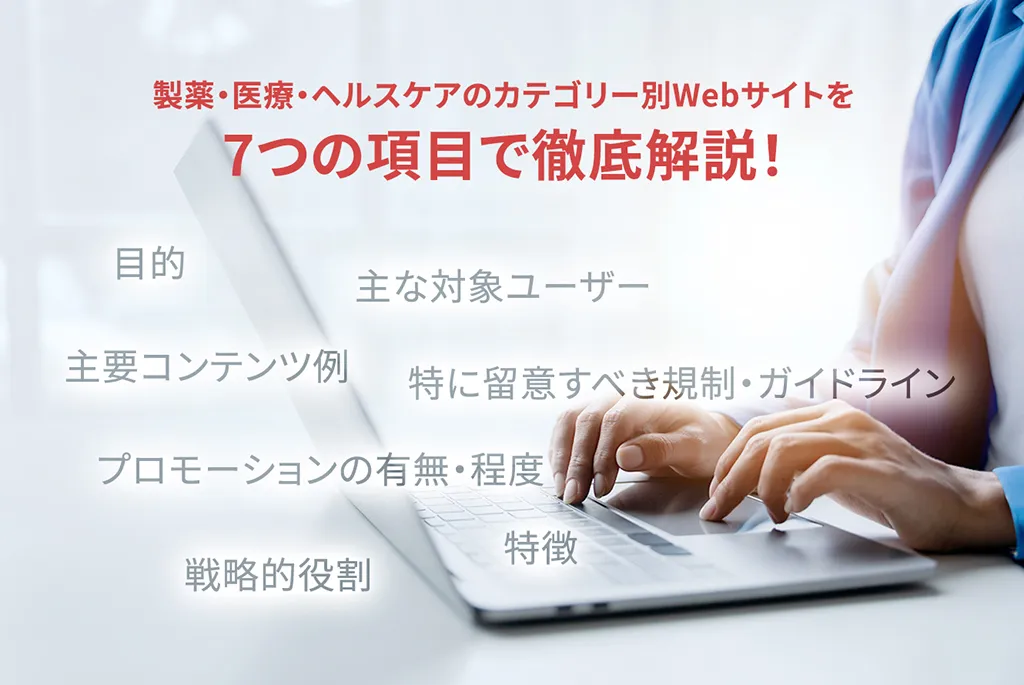
ここから製薬・医療・ヘルスケアのカテゴリー別(製薬業界、医療機関、医療機器メーカー、公的機関・研究機関、健康保険組合)にWebサイトの目的やターゲット、コンテンツ例などを紹介します。
【製薬業界】
■コーポレートサイト
〈目的〉企業情報の包括的発信、信頼構築、ESG開示
〈主な対象ユーザー〉投資家、求職者、取引先、一般人
〈主要コンテンツ例〉企業理念、沿革、IR、CSR、採用情報、研究開発方針
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉医薬品広告なし、社会的責任の透明性が求められる
〈プロモーションの有無・程度〉基本的になし(企業価値訴求に留まる)
〈特徴〉
コーポレートサイトは、企業全体の姿勢と信頼性を発信するデジタル基盤です。企業理念、沿革、事業内容、IR、採用、CSRなどを包括的に掲載し、多様なステークホルダーと信頼関係を長期的に築く“公式の顔”ともいえる存在です。製品そのもののプロモーションは行わず、企業としての信頼性や有用性、透明性を伝えます。
〈戦略的役割〉
社会性・倫理性・持続可能性など、製薬企業が求められる信頼の土台を可視化することで、ESG・サステナビリティ投資や人材採用にも影響するものとして発信します。良い薬を製造していること以外にも、「良き企業市民」であることを示す戦略的メディアとしても機能します。
■医療従事者向けサイト(HCPサイト)
〈目的〉医療用医薬品・疾患の情報提供
〈主な対象ユーザー〉医師、薬剤師、看護師など(認証制)
〈主要コンテンツ例〉添付文書、作用機序、臨床データ、講演会、業務支援ツール
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉薬機法、医療広告ガイドライン(医療従事者向けに限定)
〈プロモーションの有無・程度〉あり(専門家向けプロモーション)
〈特徴〉
医師や薬剤師などに限定した認証制サイトで、製品情報、添付文書、疾患資料、学会・研究情報、医療支援ツールなどを網羅しています。最新のエビデンスをもとに臨床現場で活用可能なリソースが揃っており、医療従事者の情報源として信頼されています。
〈戦略的役割〉
MRだけでは補えない情報ニーズを24時間カバーし、専門的・中立的な立場で医師との関係構築を担います。近年は生成AIなどデジタルツールの導入が進み、単なる情報発信から“業務支援型メディア”へと進化しつつあります。
■疾患啓発サイト(DAS)
〈目的〉一般向けに疾患の認知向上と適切な受診促進
〈主な対象ユーザー〉未診断の一般人、その家族
〈主要コンテンツ例〉症状・予防・受診情報、ライフスタイルアドバイス
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉薬機法で医薬品名・成績記載不可、不安や誤認誘導もNG
〈プロモーションの有無・程度〉限定的(一般の人への医療用医薬品の広告は明確に制限されている)
〈特徴〉
特定の疾患に関する正確で中立的な情報を一般生活者へ届けるメディアです。診断前の潜在患者やその家族が対象で、症状、予防法、生活習慣改善などをわかりやすく紹介します。疾患啓発を目的とするため、医薬品の情報には慎重な制限があります。
〈戦略的役割〉
治療の前段階にいる層と接点を持ち、正しい知識を提供することで早期受診や医療へのアクセス向上を促します。製品訴求については「情報提供」と「プロモーション」の間の微妙な境界線上で薬機法や医療広告ガイドラインの解釈において常に注意が必要ではあるものの、疾患領域への認知向上と自社ソリューションへの間接的誘導を担う“プレブランディング”の役割を果たします。
■患者向けサイト
〈目的〉医薬品の適正使用と継続治療支援
〈主な対象ユーザー〉医薬品を使用中または使用予定の患者と家族
〈主要コンテンツ例〉効能・用量・副作用、服用時の注意、相談窓口
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉薬機法、医療広告ガイドラインに準拠、過大表現や過度な期待を避ける
〈プロモーションの有無・程度〉原則なし(適正使用支援が主目的)
〈特徴〉
医薬品を使用中または使用開始予定の患者と家族に対し、服薬方法、副作用対応、注意点などの情報を提供します。閲覧対象を明確にし、効果の記載は必要最小限とし、過大な期待を抱かせないよう配慮し、正確で現実的な情報を通じて安心して治療を継続できるよう支援することに特化した構成です。
〈戦略的役割〉
正しい服薬をサポートし、アドヒアランス(服薬遵守)や治療成果の最大化をすることです。治療の途中離脱や不満の予防にも寄与し、主体的に治療に参加できるような情報を提供する役割があります。広告規制を遵守しながら、“安心して使える薬”という体験価値を高める情報設計が求められます。
■患者支援プログラムサイト(PSP)
〈目的〉服薬遵守とQOL向上支援、個別最適化
〈主な対象ユーザー〉治療中の患者、その家族
〈主要コンテンツ例〉リマインダー、記録ツール、生活支援、コミュニティ
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉訴求過多に注意、薬剤への誘導と見なされない配慮が必要
〈プロモーションの有無・程度〉間接的にブランド強化、使用継続促進目的あり
〈特徴〉
QOL向上を目的とした継続支援型プラットフォーム。疾患管理、服薬リマインダー、栄養・運動サポート、相談窓口など多様な支援コンテンツがあり、患者の生活全体に寄り添う体験設計がされています。
〈戦略的役割〉
単なる情報提供から一歩踏み込み、患者のリアルタイムデータを収集・分析して治療の継続率向上と個別最適化支援を目指します。製品中心ではなく“患者中心”の設計思想が核となり、ロイヤルティ形成や差別化戦略にも貢献する重要チャネルになります。
■医薬品ブランドサイト
〈目的〉特定製品の理解促進と適正使用支援
〈主な対象ユーザー〉医療従事者および一部患者(区別運用)
〈主要コンテンツ例〉製品特性、安全性、疾患情報、体験談(慎重に)
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉HCP向け:製品訴求OK、一般向け:個人情報保護法への配慮(体験談・属性情報など)
〈プロモーションの有無・程度〉有(対象・表現により濃淡あり、慎重な設計が前提)
〈特徴〉
特定製品に特化した情報提供サイトです。医療従事者・患者向けに分けて情報構成され、製品特性、作用機序、安全性、疾患情報などを戦略的に整理。厳格な規制があるため、慎重なコンテンツ設計が不可欠です。
〈戦略的役割〉
ブランドの信頼と認知を醸成し、処方・服薬の意思決定を支援する“情報ハブ”として運用します。直接的な訴求が難しい中で、ターゲット層が求める疾患課題に寄り添ったストーリーテリングを通じて処方行動や治療継続へ影響を与えることを目指し、製品のポジショニングの明確化をしていきます。
【医療機関(病院・クリニック)】
■公式ウェブサイト
〈目的〉受診促進、患者支援、採用、信頼形成
〈主な対象ユーザー〉地域住民、通院患者、求職者
〈主要コンテンツ例〉診療科案内、医師紹介、予約・アクセス、院内情報
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉医療広告ガイドラインに準拠、診療内容は客観的に
〈プロモーションの有無・程度〉訴求可能(過剰表現や虚偽はNG)
〈特徴〉
診療案内、医師紹介、院内施設、アクセスなどを網羅し、受診を検討する患者や地域住民に向けて正確かつ安心感のある情報を提供します。そのほか採用情報や医療機関の理念も発信し、求職者向けの採用情報も提供しています。
〈戦略的役割〉
公式ウェブサイトは患者にとって信頼獲得と受診誘導の接点となり、医療機関にとってはブランディングと集患・人材確保の起点となります。信頼性と使いやすさが“Web上の病院体験”を左右するため、各診療科や部門の詳細な説明、医師・スタッフの紹介、医療や診療内容に関するブログ記事なども効果的なコンテンツです。
■ポータルサイト
〈目的〉医療機関選定支援、集患促進
〈主な対象ユーザー〉一般生活者(患者予備軍)
〈主要コンテンツ例〉病院検索、口コミ、専門医情報、予約連携
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉口コミ内容に対するモニタリング・法的責任の配慮が必要
〈プロモーションの有無・程度〉医療機関による掲載は事実情報に基づけば可
〈特徴〉
診療科目・地域・評判など多様な軸で医療機関を効率的に比較・検索できる集合型プラットフォームです。口コミや予約連携機能も備え、ユーザー利便性にも優れています。
〈戦略的役割〉
患者の病院選びを支援し、医療機関にとっては検索流入による集患チャネルとしての役割があります。デジタル上での評判管理がブランド形成に直結する場として無料から有料プランまで選択肢があり、段階的にプロモーションを強化しながら活用することができます。
【医療機器メーカー】
■公式ウェブサイト
〈目的〉製品情報提供、安全性説明、信頼獲得
〈主な対象ユーザー〉医療従事者、販売関係者、一般人
〈主要コンテンツ例〉製品カタログ、添付文書、安全情報、CSR、採用情報
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉医療機器の広告制限、正確性・客観性が求められる
〈プロモーションの有無・程度〉医療関係者向けには可、一般向けには制限あり
〈特徴〉
製品情報、安全性、添付文書などを医療従事者向けに詳細に掲載しています。同時に企業理念、技術力、CSR活動などを公開し、企業としての信頼性、技術力、社会貢献への姿勢をアピールします。
〈戦略的役割〉
製品の専門性・安全性・技術力を正確かつ網羅的に発信する医療者との情報接点です。また、SDGsや社会貢献の取り組みを明示することで企業の信頼性・透明性を高め、投資家や人材への訴求も可能にします。サイト全体が、技術・倫理・社会価値を統合的に体現する戦略メディアといえます。
【公的機関・研究機関】
■厚生労働省関連サイト
〈目的〉政策情報と制度の正確な提供
〈主な対象ユーザー〉国民、医療従事者、自治体
〈主要コンテンツ例〉医療制度、医療機関検索、感染症情報、統計
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉行政文書としての中立性・正確性・アクセシビリティ
〈プロモーションの有無・程度〉なし(広報的表現は限定的)
〈特徴〉
政策情報、制度案内、統計データ、医療機関検索、公衆衛生情報などを網羅する信頼性の高い国の医療情報ポータルサイトです。全国の医療機関や薬局を検索でき、多言語対応やユニバーサルデザインも充実しています。
〈戦略的役割〉
国民のヘルスリテラシーと医療アクセスを支える公的インフラです。迅速・中立な情報提供が、医療行政への信頼形成と行動変容の鍵を握ります。将来的な医療費抑制や社会全体の活力維持に繋がる、長期的な視点に立ったデジタルヘルス戦略となります。
■医薬品医療機器総合機構(PMDA)
〈目的〉薬機法関連業務情報、承認・安全性情報
〈主な対象ユーザー〉国民、医療従事者、企業、研究者
〈主要コンテンツ例〉添付文書、救済制度、審査情報、安全情報
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉規制機関としての中立性・信頼性維持が必須
〈プロモーションの有無・程度〉なし(公的機関)
〈特徴〉
承認審査、安全対策、被害救済など、薬機法に関わる情報を多層的に提供。閲覧者の属性(国民・医療者・企業など)ごとに明確な構造設計を持っています。
〈戦略的役割〉
規制とイノベーションの両立を担い、日本の薬事行政の信頼性・透明性を支える情報ハブの役割。データ駆動型医療へのシフトするためのRWD活用やリスク管理を通じた医療の質向上にも貢献しています。
■国立医薬品食品衛生研究所サイト(NIHS)
〈目的〉医薬品、食品、化学物質などの安全評価と規制科学の情報提供
〈主な対象ユーザー〉規制当局、研究者、企業
〈主要コンテンツ例〉医薬品情報ガイド、国内外の承認薬情報、副作用情報データベース
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉科学的中立性、営利禁止
〈プロモーションの有無・程度〉なし(公的機関)
〈特徴〉
医薬品・食品・化学物質に関するリスク評価・規制科学研究を支える情報サイトです。副作用DBや国際ガイドラインへのリンクも網羅しています。
〈戦略的役割〉
科学的根拠にもとづく政策判断と企業活動を支える知識基盤です。最前線の研究成果を反映し、安全性確保と国際協調におけるアカデミックな支柱としての役割を果たします。
■国立高度専門医療研究センター(NCs)
〈目的〉疾患別の医療研究・支援発信
〈主な対象ユーザー〉患者、医療者、研究者
〈主要コンテンツ例〉疾患解説、研究成果、支援窓口
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉中立性、支援情報の配慮
〈プロモーションの有無・程度〉なし(公的機関)
〈特徴〉
特定の専門疾患領域(がん、循環器病、精神・神経、国際医療、成育医療、長寿医療、感染症)における最先端の医療研究、高度医療提供、人材育成、情報提供を行い、疾患別の専門医療・研究・人材育成を統合する情報拠点です。各センターが特定領域に特化し、研究成果や患者支援情報を発信しています。
〈戦略的役割〉
先端医療の社会実装を支える政策連携と情報普及のハブとしての役割があります。疾患別課題の解決を通じて医療イノベーションの加速と患者がどこにいても適切な支援を受けられるようにするための地域連携に寄与しています。
【健康保険組合】
■公式ウェブサイト
〈目的〉加入者支援と健康増進の情報提供
〈主な対象ユーザー〉組合加入者、その家族、人事・労務担当者
〈主要コンテンツ例〉給付・手続き案内、健診予約、KENPOS連携、健康情報、LINE通知
〈特に留意すべき規制・ガイドライン〉個人情報保護、制度表記の正確性、非営利性の保持
〈プロモーションの有無・程度〉あり(非営利型の健康促進策に限る)
〈特徴〉
健康保険組合の公式サイトは、加入者に向けて保険制度の仕組みや給付内容(高額療養費・出産育児一時金・傷病手当金など)、各種手続き案内、保健事業の詳細を正確かつ分かりやすく提供する情報基盤です。加えて、KENPOSやマイヘルスウェブなどの外部連携ツールを通じて、パーソナルな健康サポートも展開。目的別検索やLINE連携機能も備え、加入者の利便性と能動的な健康行動を促します。
〈戦略的役割〉
単なる案内窓口にとどまず、加入者の健康寿命延伸と医療費適正化を目指す“予防医療推進拠点”として機能させます。健康データの活用やインセンティブ設計を通じ、行動変容を後押ししながら「保険者」から「健康支援パートナー」へと役割を進化させ、組合財政・社会的使命との両立を支える戦略的チャネルとして運用します。
各Webサイトの今後の展望は?
製薬・医療・ヘルスケア業界のWebサイトは、単なる情報発信ツールから多様なステークホルダーとの関係構築、患者支援、研究推進、そして企業価値の向上に不可欠な戦略的プラットフォームへと進化しています。今後も新たな技術や社会ニーズの変化に適応しながら、その役割と影響力が拡大していくことが考えられます。
そのため、サイトの運用担当者は医師や医療従事者のサイト上の行動の意図を深く理解し、CRMなどのツールの連携によるパーソナライズされた情報提供や、ターゲットに合わせた効果的なデジタルコミュニケーションをいかにとることができるかが競争優位性を確立していく鍵となります。
また、薬機法や医療広告ガイドラインなどの厳格な法規制に加え、健康や生命に関わる倫理的責任も今後のWebサイト運営の基盤であり続けます。これらの規制の境界を正しく見極めたうえで、適切にサイトを運営する姿勢が重要です。
■各業界のWebサイト運営のポイント
・正確で信頼される医療情報が企業価値を高める
・UXとアクセシビリティで医療サービスの浸透を後押し
・SEOやCRMなどの活用でパーソナライズ戦略を推進
・法令、倫理遵守が信頼の起点となる
上記をふまえ、信頼・理解・利便性・戦略を兼ね備えたWebサイトで“正確で信頼性のあるデジタル体験”を提供していきましょう。
運用の精度を高め、目的や役割に合わせたデジタル戦略を!

それぞれのWebサイトを種類別に確認することで、各サイトが果たすべき役割を個々に把握することができたのではないでしょうか。各サイトの機能と目的を正しく理解しておくことは、運用方針の軸をぶれさせずにコンテンツ制作をしたり、施策設計の精度を高めるうえでも欠かせません。今回ご紹介した内容なども参考に自社サイトのターゲットや提供価値を明確にし、Web戦略に活かしてみてはいかがでしょう。
メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。Webサイトの運用など、デジタルに関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。
この記事の担当者

加藤 美羽 / Kato Miu
職種: Webディレクター
入社年:2023年
経歴:2023年新卒入社後、Webinar運用案件→イベント事務局運用案件に従事。