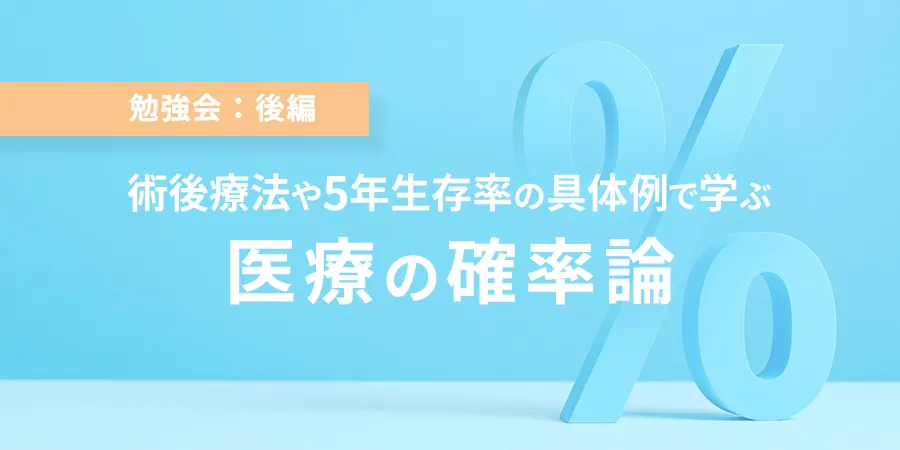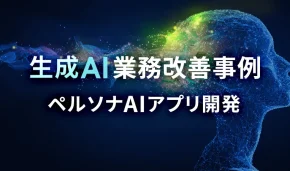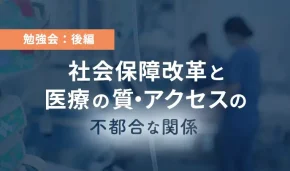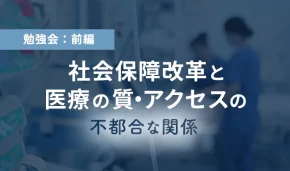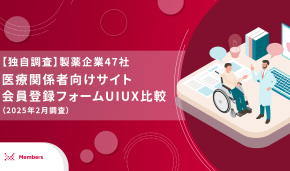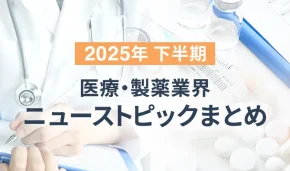私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。テーマは前半に続いて「医療の確率論」について解説します。後半では、余命宣告の考え方の説明を交えて、さらに確率論の話を深堀りしていきます。ぜひ、ご覧ください。
勉強会の参加者

2018年中途入社
営業
佐塚さん

2017年中途入社
Webディレクター
嶋田さん

2008年新卒入社
Webディレクター
安原さん

2022年新卒入社
Webディレクター
土屋さん

2024年新卒入社
Webディレクター
森田さん

2024年新卒入社
Webディレクター
丹羽さん

2019年中途入社
プロデューサー
村田さん

2023年新卒入社
Webディレクター
田辺さん

2023年新卒入社
Webディレクター
上田さん
がんの余命宣告の確実性に迫る!
それでは、よろしくお願いします。出席者は、嶋田さん、安原さん、土屋さん、森田さん、丹羽さん、村田さん、田辺さん、上田さん、鈴木さん、僕です。
よろしくお願いします。
引き続き、『医療の確率論』のお話をしますが、前半(※)では、確率論の考え方について、がんの術後療法をした場合に、再発率をどのくらい下げられるかという話で説明してきました。
後半は、ちょっと違う観点で、がんの余命宣告に関する確率論的な話をしていきましょう。巷で良く出てくる話で、芸能人やYouTuberなどががんに罹り、ステージ4で余命半年と言われた……というようなお話を時々見かけますよね。あの余命って、どれくらい確かだと思いますか?
※前半の記事はコチラ
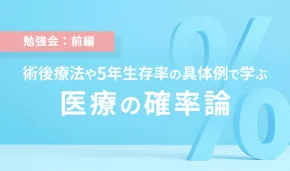
【勉強会:前編】医療は確率論でできている〜術後療法や5年生存率の具体例で学ぶ〜
2025.07.22
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。今回のテーマは「医療の確率論」。前半は確率論の考え方について、がんの術後療法や5年生存率の具体例 […]
それって、それを言っている方に対するバイアスは外して……ということですよね?
そうですね。バイアスは一旦外していただいて
そもそも、余命の定義からして良く分からないですよね。同じような重篤度や症状の方の統計があるのかなとは思うのですが……
さすがに、これは僕もその通りになるんじゃないかと思っていますが……
最近、余命で話題になっていた有名な方でいうと、若手の方はご存じないかもしれませんが、経済アナリストの森永卓郎さんですね。お亡くなりになってしまいましたが。
彼は、自分のがんが見つかってから、主治医に『来年の桜は見られない』と宣告されたなんて言う話をされていましたが、余命宣告を受けてから1年以上も生きていらっしゃいました。で、余命宣告の答えを言うと……あれは、いい加減です。ハッキリ言って
えぇー! そんな不確かなこと、患者さんに何よりも言ってはいけないのでは……
余命が医師にも予測不可能な理由とは?

これについては、医療の中でも問題だなと思う所ではあって。というのは、お医者さんにだって、分かるわけがないんですよ。末期がんになった患者さんに、在宅での緩和医療を提供している友達の先生がいます。患者さんの看取りを何百人、何千人とやっている方ですが、彼曰く『2週間を切ったら分かる。でも、それ以上は嘘です。分からないです』と言っていました
んなことを言われたって……変な話ですけど『余命半年だから、残っているお金を全部使っちゃおう!』っていう人もいるかもしれないですよね?
そうです。お医者さんが『余命半年です』と言ったとして、それが何の根拠で言っているのかですよね。根拠があるとしたら、ちゃんと世の中に出ている数字として、すい臓がんのステージ4の5年生存率が○%とか、3年生存率が○%とか、そういう数字は一応、あるわけです。
例えば、すい臓がんに罹って半年で亡くなる方が50%いると。で、残りの方が半年以上だとしたら、それを根拠として余命半年として宣言するというのは考えられます。でも、本当に半年ぐらいで亡くなる方が殆ど……っていう話ではないんですよ。中には余命を越えて2年ぐらい生きる方もいれば、2~3ケ月で亡くなる方もいるだろうし。なので、基本的にははっきり分かって言っているわけではありません、というのが大前提としてあります。
もう1つ、みなさんもニュースなどで時々は、がんの5年生存率が○%とか出ているのを見たことがあると思いますが、あれって実は古いデータなんですよ。どういうことかって言うと、がんの5年生存率で今ある一番新しいデータって2019年の報告なんですけど、どういう人たちの集団を元に作られているかというと、2009年から2011年にがんと診断された人たちのデータです。古いと思いませんか?
今はそこから十数年経っていて、その間に抗がん剤ってメチャメチャ進歩しているんです。かつてあったデータでは余命3~4年だったものが、今だったら5年以上生きられるのが当たり前、という状況に変わっていることが十二分に考えられます。なので……本当に分からないんです
治療の進化とともに余命の長さは変わっていく!
1つ、治療法がとても進化した例として、血液のがん『多発性骨髄腫』というものがあります。2007年報告の5年生存率が25%。これは結構厳しいですよね。それが2019年では42.8%(※)。で、今は5年以上生きるのが当たり前になってきていますね。この5年でもたくさん新しい薬が出てきていて。
写真家の幡野広志さんという方がいらっしゃるのですが、みなさんも検索してみてください
あっ。出てきましたね。写真家、元狩猟家……
そうそう。幡野さんは狩猟生活送ったりもしていたとか。
で、この方は2017年に多発性骨髄腫になってしまって余命3年と主治医から言われたと。それで結構、自暴自棄になっていた時期があったようなんです。SNSとかでも色々発信していらして。
ただ、僕はなぜ、主治医の方が余命3年と言っているのか不思議で。多発性骨髄腫の治療も進化しているので、そんな事を言う必要はないのになぁ……と。実際、宣言から大分時間が経ちましたけど、今も幡野さんはお元気にしていらっしゃいます。なので、5年生存率になどに基づいて余命○年とかっていうのは、あまり信用しない方が良いですよ。という話です。
でも、これって言われたら、何も知らなければ信じてしまいますよね?だから、医者も罪作りだなと思うんです。あと、良く言われるのは、お医者さんは余命を短めにいうことが多い、と。
……では質問です。みなさんがお医者さんだったとして。これって、どんなメリットがあると思いますか?
ちょっと嫌な見方をしてしまうと……
思ったよりも短かった場合、病院のせいになってしまうというか
そう。それがありますね。
逆に、思ったよりも長ければ名医と思われる、と(笑)。どちらにしても、長めに言うメリットは、先生側にはないわけですよね。だから、余命なんか聞かない方が良いんです。分からないものですし
質問したいんですが、余命って伝えなければいけないものなんでしょうか?
伝えなければいけないものではないですね。
だけど、聞かれたから答える、という感じなのではないでしょうか。僕が医師だったら『正直、分からないです』と言いますけどね
(※)参考:骨髄腫ナビ「がん情報の探し方」
治療選択に迷ったら医師へのキラークエスチョンをヒントに!
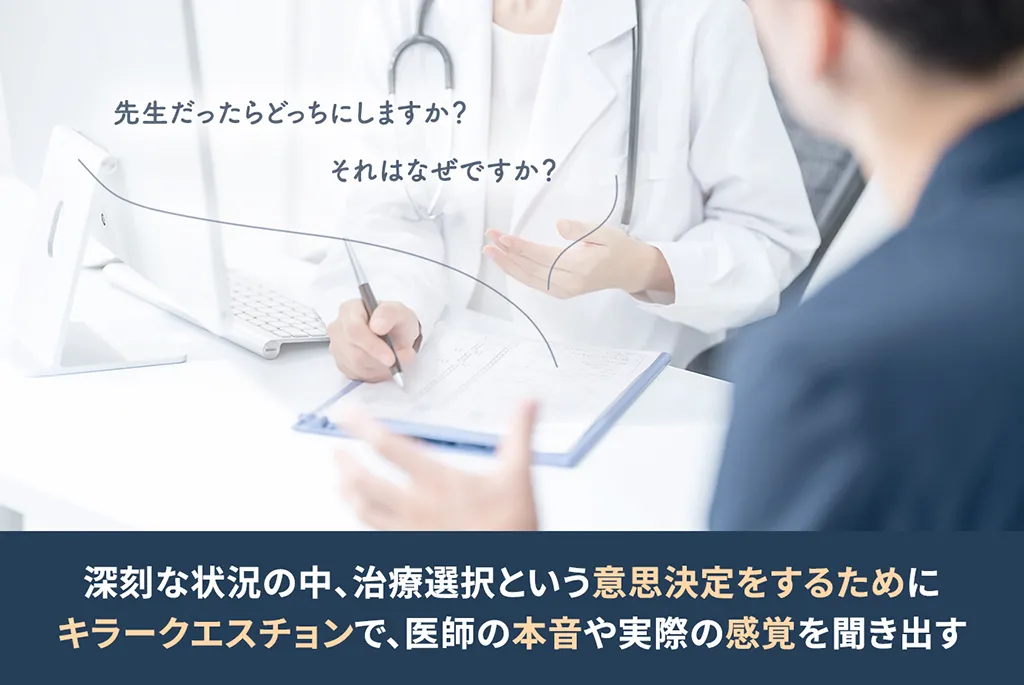
なので、確率論というのは、がん医療の中で本当にいっぱい色んな所に出てくるわけですが、最後に一つ、みなさんも大きな病気になるかもしれないし、その時にこういった確率について考えなくてはいけない場面も出てくるかもしれません。その時、不確実なものがある中、自分で責任を取って治療の選択をすること自体がストレスになる人もいると思うんですよね。その場合、まず迷うということはどちらを取っても悪くはないということ。
で、治療選択で迷うのであれば、主治医のオススメを遠慮なく聞きましょう。『先生だったらどっちにしますか?それはなぜですか?』という事を聞いて、納得する答えが出ることもあると思うので。先生ならどう思うか、というのはキラークエスチョンで、医師の本音や実際の感覚を聞き出せる質問です。
けれど、患者さんの方でこれを聞いてはいけないという風に思っている方もいらっしゃるんですよね。でも、これは聞いて良いことです。それで、どんな選択肢を取ったとしても、あとは最善を祈るのみ。がん患者さんとか、深刻な状況の中で治療選択という意思決定をしていくのは非常にしんどくなることもあるので、こんな風に考えて行動していただいても良いかなと思います。……ということで、今日の僕からのお話は以上です
ありがとうございます。
本日も具体的な例を元に説明いただけたので、出席メンバーも医療の確率論の理解が深まったんじゃないかなと思います。ちなみに、僕はYouTubeで配信されているリアリティ番組の『令和の虎』をよく観るんですけど、少し前に整体師の方が治す、治さないっていう話をしてバズったことがあって。
要するに、医者ではないので『治る』という表現を使ってはいけないということですね。前半で、ブラインド投与の話も出たので、今後、そういうものに絡めた話なんかも面白そうだなと思いました。では、改めて、本日もありがとうございました!
全員「ありがとうございました!」
――今回は、「医療は確率論でできている〜術後療法や5年生存率の具体例で学ぶ〜」の勉強会レポートをお届けしました。確率論を表面的に理解するだけではなく、数字の見え方や医療の進化とともに考えることで、がんの再発リスクや余命についての捉え方が変わったのではないでしょうか。今後も勉強会の模様をお届けしつつ、業界の知識を共有していきますので、ぜひご期待ください。
この記事の担当者

佐塚 亮/Satsuka Ryo
職種:sales
入社年:2020年
経歴:大手スポーツメーカにて店舗sales,エリアマネージメント業務を担当。のちWEB制作会社にてWEBサイトの提案からディレクションをこなし、コンサルタントとしてサイト立ち上げ後の売上向上まで支援。その後2020年にメンバーズへ入社。主にクライアントからのヒアリング及び検証データを基に要件定義を行い、サイトの構築運用を実施。定常的に支援サポートを行う。クライアントはもちろんエンドユーザーの立場・視点に立ち、問題抽出から改善案の立案までを手がける