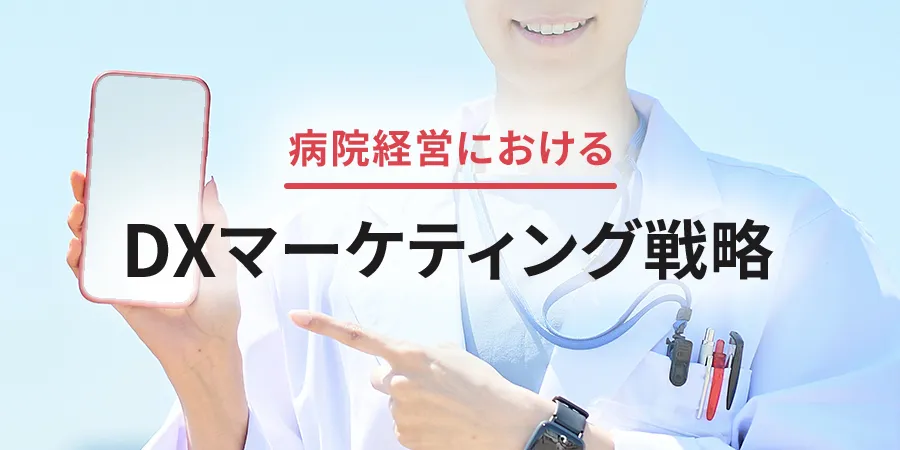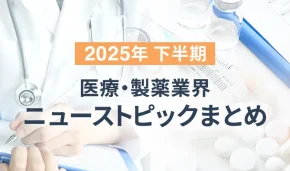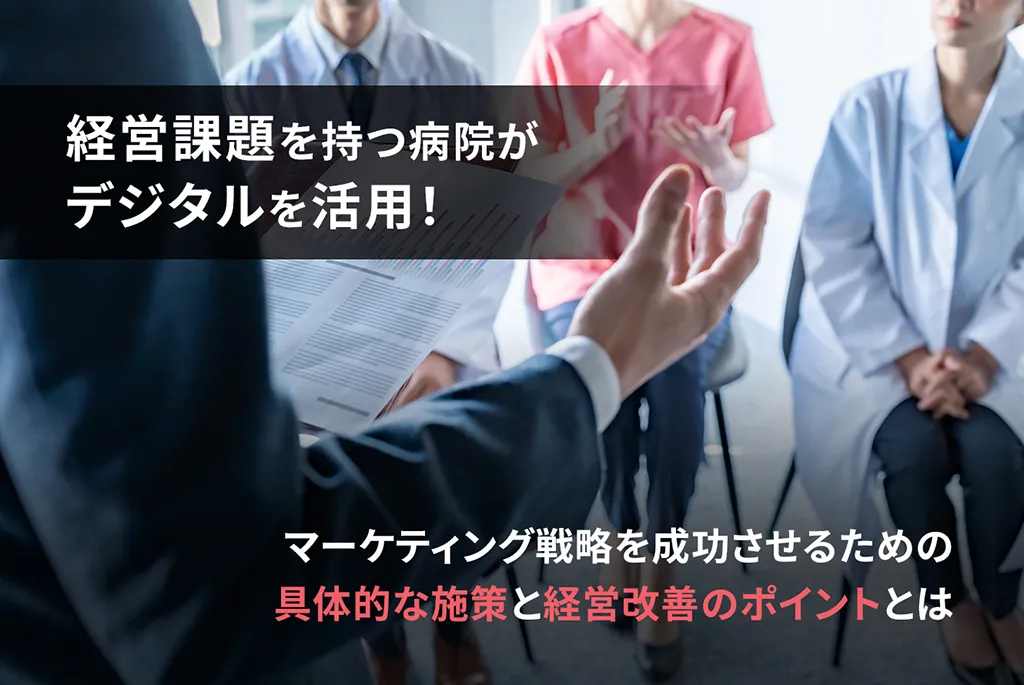
現在の病院経営におけるDXマーケティング戦略について調査しました。多くの病院が深刻な経営難に陥っている中、DXなどを活用し経営再建のカギとして危機的状況を乗り越えている病院も増えつつあります。それらの病院がなぜうまくいったのか、成功の背景にある戦略や具体的な施策を解説します。ぜひご覧ください。
ある日突然、病院がなくなる? 病院は過酷な経営難時代!
現在、多くの医療機関が深刻な経営難に陥っています。この状況については、当ブログでも病院の赤字問題を調査し、その背景や理由を調べましたが(※1)、今回は、次のステップとして経営課題を持つ病院がデジタルを活用し、マーケティング戦略を成功させるための具体的な施策と経営改善のポイントについて解説します。
(※1)過去の記事はこちら!
いま、医療機関が直面している切実な状況は、3月に一般社団法人 日本病院会が発表した「ご存知ですか?あなたの街の病院がいま危機的状況なのを!!」という、要望・提言・調査を含めた文書に記されていました。医療機関は公定価格である診療報酬と、物価および人件費の高騰という三重苦に直面し、深刻な経営難に陥っているということが分かります(※2)。“このままではある日突然、病院がなくなります”という冒頭の文言も含め、緊急性のある状況であることが伝わってくるのではないでしょうか。また、一般社団法人 日本能率協会の「2024 年度 病院経営課題の実態調査」でも、病院の外来や入院診療がコロナ前に戻らない病院が約 40%程度、さらに、多くの病院がDXに活路を見出そうとするも実際にその効果を実感できているのは30%未満にとどまっているというデータがあり(※3)、収益回復の道筋を見出せていない現実を物語っていました。
しかしながら、現在も成長を続けている病院もあり、また、デジタルを駆使した戦略的アプローチにも新たな方法が登場しています。DXに対する本質的な理解を深めるためにも、今回ご紹介する施策を活用してみてはいかがでしょう。
(※2)参考:一般社団法人 日本病院会「ご存知ですか?あなたの街の病院がいま危機的状況なのを!!」
(※3)参考:一般社団法人 日本能率協会「2024 年度 病院経営課題の実態調査」
医療DXの本質と目的を捉え、成功させるための取組み
DXが推進された当初にも繰り返し伝えられてきたことですが、DXは単なるIT化ではありません。単に電子カルテやオンライン診療を導入するだけではなく、デジタル技術を基盤として、医療の提供体制そのものを再構築する取り組みというのがDXの本質と目的です。以下のような施策はDXを実現させるものとして役立ちます。
【データ活用・分析】
経営再建を目指す病院は、最初に自院の現状についてデータを活用し分析することから着手しましょう。
分析をせずに、とにかく新しいシステムの導入を目的にしてしまうと、現場にシステムが浸透しないケースがあります。その影響でかえって手間が増え、より使われないシステムになってしまう可能性が高くなります。
いきなりDXへ取り組むのではなく、まずは現状把握から始めていくことが重要です。自院にデータが存在するのかを確認し、全くデータが無ければデータ取得の仕組みを構築します。データが取れるならばどんなデータがあるのかを確認しましょう。そして、データが取れるようになったらデータを活用し、それに基づいた分析から意思決定をするフローを構築します。DXという響きから画期的なシステムなどに注目されがちですが、DXを成功させるには入念な下準備も必要です。
【業務フロー変革と生産性向上】
■電子カルテ・情報共有システムの活用
多くの病院で、電子カルテや医療情報管理システムの導入が進んでいます。厚生労働省の「電子カルテシステム等の普及状況の推移」に令和5年の集計データが発表されており、電子カルテシステムは、一般病院は65.6%、オーダリングシステムは68.0%でした(※1)。6割以上が電子カルテ・情報共有システムの活用をしており、医療現場における情報の一元管理や複数スタッフによる同時アクセスを可能にした事で、部門間の連携を円滑にし、業務効率を改善に繋げるために導入しています。また、同時に医師や看護師を支援するクラークを採用することで医療現場全体の効率化や情報共有をサポートする取り組みにも注目が集まっています(※2)。
(※1)参考:厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」
(※2)参考:ウェブカルテⅡコラム「電子カルテとクラーク運用の魅力:病院業務が驚くほど効率化する理由」
■AI・RPAによる業務自動化
近年、ニュースなどでもAIによる画像診断が取り入れられた事例などを目にするようになりました。AIの診断支援を取り入れている病院も増えてきているかもしれません。また、事務作業や管理業務の負担が多い医療現場にはRPA(Robotic Process Automation)の活用も進んでいます。電子カルテも同様ですが、これらの技術は作業の効率化を通じて医療従事者がより専門的な業務に集中する環境を構築するためのシステムです。
【患者接点のデジタル化と利便性向上】
■オンライン診療システムの導入
医療におけるDXは、「患者体験」の価値を高めるうえでも不可欠な要素です。オンライン診療システムは自宅にいながら医師の診察や薬剤師の服薬指導を受けられるシステムとして、特にコロナ禍で認知を広げ拡大しました。これは、患者の隠れたニーズを解決するソリューションとしてDX活用に踏み切った好例といえます。オンライン診療を利用することで、患者さんは移動に掛かる費用や待ち時間の負担から解放され、デメリットとなる部分をデジタル技術によって根本的に解消することに繋がります。
■患者向けアプリの活用
患者接点のデジタル化は、利便性向上だけでなく、医療提供者と患者の信頼関係を深める重要な手段としても広まりつつあります。患者向けアプリには、診療サポートアプリ、体調や服薬記録、治療用アプリなどさまざまなタイプがリリースされています。自宅で診察や服薬指導、チャット機能で相談を受けられるというものもあれば、アプリによっては日々の体調や服薬状況を記録・管理することで自己管理能力が高まり、治療へ良い影響を与えるような使い方もできます。もちろん、医療従事者にとって業務効率化などのメリットもありますが、セキュリティや運用面での課題もないわけではありません。それらを考慮して活用するべきか判断する必要があります。
また、ご紹介した取り組みは、それぞれ単独でも一定の効果を発揮しますが、DXの本質的な価値を実感するには、複数の取り組みを連携させて活用することが重要です。例えば、【データ活用・分析】によって現場の課題や改善ポイントを可視化することで、電子カルテやAI・RPAなどの【業務フロー変革】の導入がより的確になります。【患者接点のデジタル化】に取り組む際も、患者向けアプリやオンライン診療の利用状況をデータとして蓄積・分析することで、患者ニーズに即したサービス改善が可能になります。
もちろん、人材やコストの確保という面でも短時間で導入できるものではないと思われますが、出来るところから着手し、連携させながら活用するという視点が重要です。それぞれ相互に好循環を生み出せるように連携させながら活用することで施策同士がつながり、最終的なDX実現に近付きます。
他医院との差別化に向けたマーケティング戦略
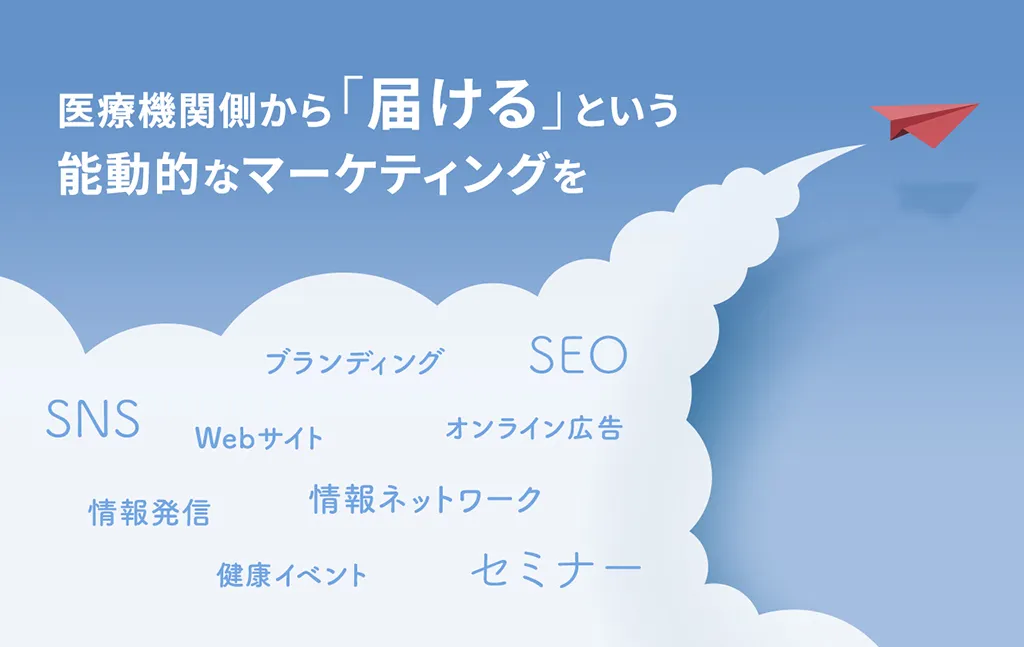
大多数の人がパソコン、スマートフォン、タブレットなどのデジタルデバイスを持つ時代になりましたので、それに伴い集患マーケティングも変化させやすくなりました。従来は看板や電柱広告のようなものが主流で、マーケティングスタイルは「待つ」だけになりがちでしたが、現在はデジタルを通して医療機関側から「届ける」という能動的なスタイルを追加することができます。「届ける」集患コミュニケーションで差別化に向けたマーケティング戦略に取り組んでみましょう。
【デジタルコミュニケーションの活用】
■SNS・Webサイトを活用した情報発信とブランディング
SNSを活用することで医療機関のブランディングに取り組むクリニックも増加しています。InstagramやXなどのSNSは若年層を中心に使われているため、その年齢層に強みを持つクリニックが専門的な内容の発信やキャンペーンの告知などをすることが有効な集患コミュニケーションになります。若年層向けの医療サービスを提供している場合には、これらの活用も視野に入れてみましょう。また、Webサイトも重要なコンテンツです。医療機関を探す際に公式サイトを閲覧する方も多いため、院長や医師の実績、スタッフ紹介ページなどで在籍している方の人柄を伝えるのも効果的です。さらにWeb予約システムが実装されていれば、閲覧後に予約にまで繋げられる可能性もあります。公式サイトは、これから来院しようと検討している方へ、信頼感や安心感を醸成する重要な役割を担うツールとして活用することができます。
■SEO対策とオンライン広告による集患強化
上記で触れたように、Webサイトも集患マーケティングに欠かせません。WebサイトのSEO対策や情報の更新も潜在的な患者への認知度を高めるために実施していきましょう。また、検索エンジンで上位表示される病院検索のポータルサイトも集患に役立つサイトです。地域や駅名、診療科などから医療施設を検索するユーザーも一定数はいるため、病院情報を登録し、ユーザーの目に留まる機会を増やすのも一つの方法です。他にも、コストは掛かりますがインターネット広告を掲載して認知を拡大しながら集患に繋げる方法もあります。
【地域・コミュニティとの連携強化】
■医療機関間の情報ネットワーク構築
クリニックと病院、介護施設の連携は効率的な診療に欠かせません。病院が地域社会で持続的な役割を果たすためには、地域全体のエコシステムに溶け込む必要がありますので、医療機関間の情報ネットワーク構築には積極的に取り組んで行きましょう。診療情報をデジタルで一元管理するシステムとして注目されている電子カルテは、厚生労働省では、“遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す”という目標を掲げています。多職種間の連携や地域医療の情報共有にも不可欠なもののため、医療DX推進の中核を担う存在でもあります。導入コストなども掛かりますが、情報がデータ化されるため、紙カルテに比べて保存や検索が容易で、業務効率も向上させることができます。
また、電子カルテについての詳しい説明は、社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険中央会の「医療機関等向け総合ポータルサイト」に、説明が記載されています(※)。システム要件や手順書・マニュアルなども確認でき、どのような仕組みになっているのかも分かりやすく図で説明されています。
※参考:厚生労働省「医療DXの進捗状況について」
※参考:社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険中央会「医療機関等向け総合ポータルサイト」
■健康イベント・セミナーの開催
こちらはデジタル施策ではありませんが、病院が地域住民に向けて実施するイベントも新規の患者獲得につながる可能性があります。健康増進や病気の予防をテーマにした健康セミナーなどで病院の存在をアピールしたり、自然な形で地域住民との交流を深められ、親しみを感じてもらいやすくなります。また、こうしたイベント企画は、近隣住民へ認知拡大だけでなく、人材確保の面でも良いインパクトを残せます。
超高齢社会に向けた、病院経営の戦略ポイント
日本の医療環境は多くの課題を抱えていますが、2040年の「超高齢社会」に向けて病院経営は地域の医療・介護施設、行政や民間企業と連携し、医療ネットワークの中で効率的かつ柔軟な経営モデルを築く必要があります。持続可能な経営を実現するために、以下の5つの要素を要点としておさえることで、ブレのない戦略を策定できます。
【1:データ主導文化の醸成】
DXを成功させるためには、データ活用・分析が必要であることに触れました。自院の経営状況を正確に把握することにも繋がるため、今後は、データを基にした判断を取り入れていく“データ主導文化”を醸成していくことも重要です。医療施設内のデータの多くがデジタル化されている場合、さまざまな数値やコストなどがシステムに蓄積された状態になっています。電子カルテの分析ツールなどを使ってデータを収集し、それらを分析して使うことによって客観的なデータに基づいた判断ができます。“データ主導文化”を浸透させるには、定期的なレポート作成や報告会のスケジュールを組み、データを参考にしながら戦略や方向性を決める場を設けて、雰囲気を作り出していきます。
【2:「患者体験」を中心とした経営理念の再構築】
医療施設は、治療を提供するサービス業です。そのため、患者さんが院内で経験するすべてのプロセスにどのような付加価値を付けられるかを考えながら、それを経営理念にまで落とし込んでいく必要があります。また、経営理念を策定する際、患者アンケートを実施するのも一つの方法です。自院がどのような立ち位置であるか、客観的な意見を通して患者が求めるニーズを把握することができ、それを見据えた改善施策や経営理念の再構築に取り組むことができます。
【3:組織力向上の取り組み】
組織のエンゲージメントを強めるには、経営理念の共有も大切です。例えば、上記のように経営理念を再構築したら、必ず院内スタッフへ理念を共有しましょう。病院の理念は上層部とともに現場のスタッフも理解している状況が望ましいです。自院の経営を「自分ごと」として捉えることでチームの一体感を醸成でき、モチベーションアップにもなります。スタッフのモチベーションの高さは従業員の定着率にも繋がる要素になるため、組織力を向上させる職場づくりにも積極的に取り組みましょう。
【4:地域連携、他施設とのネットワーク強化】
電子カルテやオンラインでの情報共有システムの活用は、医療の2040年問題に向け、欠かせない要素です。人材不足に陥っている医療機関での対応には限界があるため、急性期・慢性期・在宅医療をつなぐ連携体制は整えておかねばなりません。紹介・逆紹介の循環を促進し、安定した患者フローと収益構造を確立することで、医療の質と経営の両立が可能になります。信頼される地域のハブ病院としての立ち位置が、将来の競争力を左右します。
【5:改善サイクルの確立】
経営戦略は、一度決定して実施したら終了というものではありません。実施した取り組みについて振り返り、「分析→実行→検証」のサイクルを継続的に回し、戦略を見直し続ける必要があります。また、医療を取り巻く環境も変化が激しい時代となっているため、一度成功したマーケティング施策が次に良い結果につながらないということもあり得ます。市場や患者のニーズを常に把握しながら新たな戦略に取り組みましょう。DXで導入したシステムがあれば、導入後の効果を数値データで検証し、改善を繰り返すことで価値を最大化できます。
本質を捉えたデジタル技術の活用で戦略的な変革を!
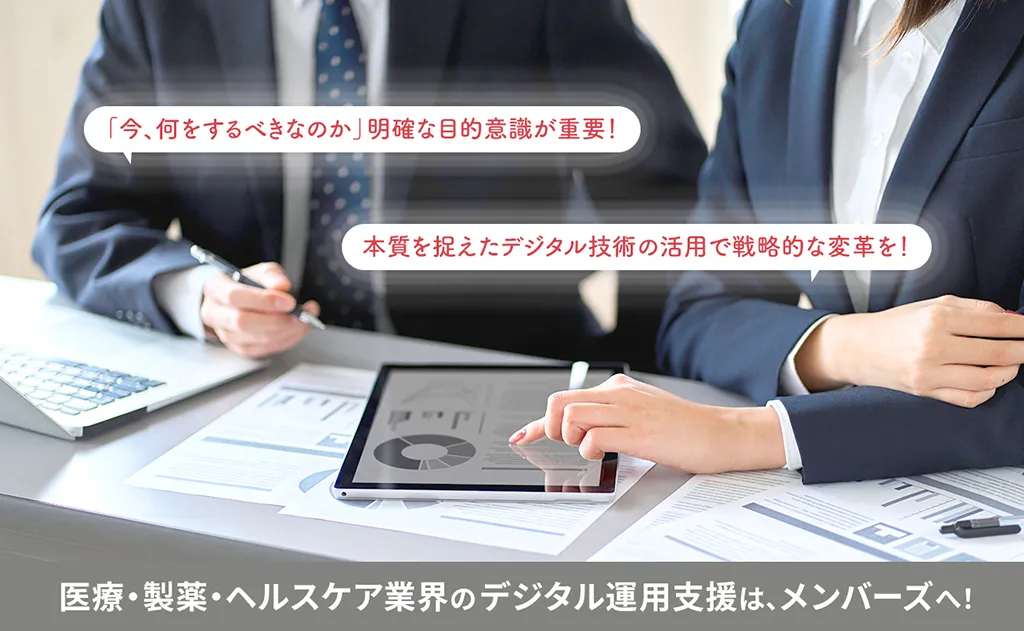
病院経営におけるデジタル活用の施策や考え方のポイントについて解説しましたが、これらに取り掛かる前にはデータ分析などで自院の強みと弱みを正確に把握し、「今、何をするべきなのか」という点についてDXを先導する経営者層が明確な目的意識を持つことが重要です。そして、その目的を達成するためにも、デジタル技術を単なるツールではなく、「患者体験の向上」や「信頼関係の構築」といった価値を創造する“手段”として活用していきましょう。
メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。AI導入・活用全般のご相談、デジタル全般に関してスキルのある人材が足りないなど、お悩みをお持ちの医療関係者や製薬企業の方はお気軽にお問い合わせください。
この記事の担当者

鈴木 まりあ / Suzuki Maria
職種: Webディレクター
入社年:2024年
経歴:2024年新卒入社後、コーダーとしてWebサイトの運用・リニューアル業務に従事。現在はWebディレクターとしてWebサイトの運用案件を担当。