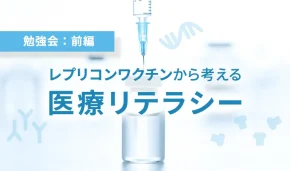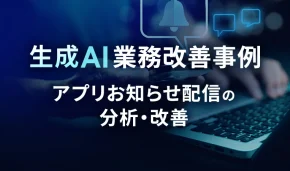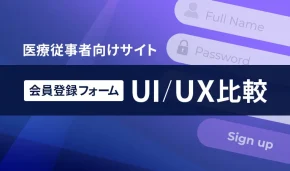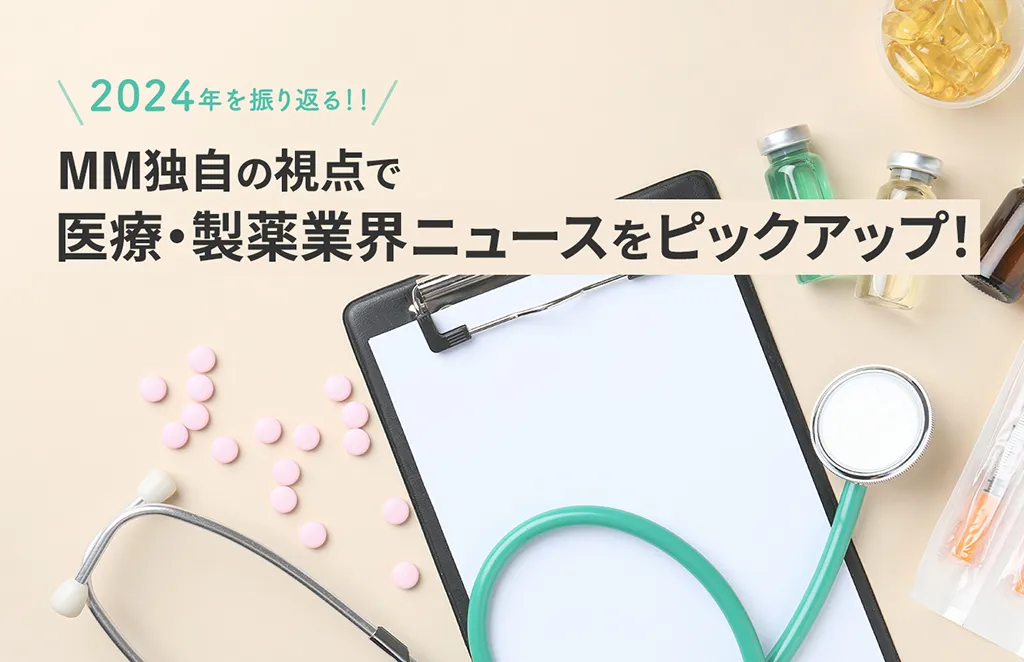
2024年も終わりに近づいてきたということで、私たち独自の視点でピックアップした医療・製薬に関するニュースをご紹介します。
デジタル化推進の流れから変化し続けている医療・製薬業界。この1年間で話題になったニュースを振り返っていきましょう。
デジタル推進の促進と課題が浮き彫りとなった2024年
今回は1年間の振り返りとして、医療・製薬業界において注目度の高かったニュースを私たち独自の視点でピックアップして紹介していきます。
日本の医療サービスの需要が増加の一途を辿っていることはすでに国民の共通認識となり、医療の安定的な提供には構造的な改革が必要になっています。
2024年は高齢化社会に向けて仕組みも変わり始め、医療財政や人材の持続的な確保に関わるニュースも多くなりました。そして、今後必須となる予防医療の推進や生成AIなどのデジタルテクノロジーの活用はどこまで広がったのでしょうか。
以下から、2024年の医療や製薬のニュースを振り返ります。
医療関連トピック
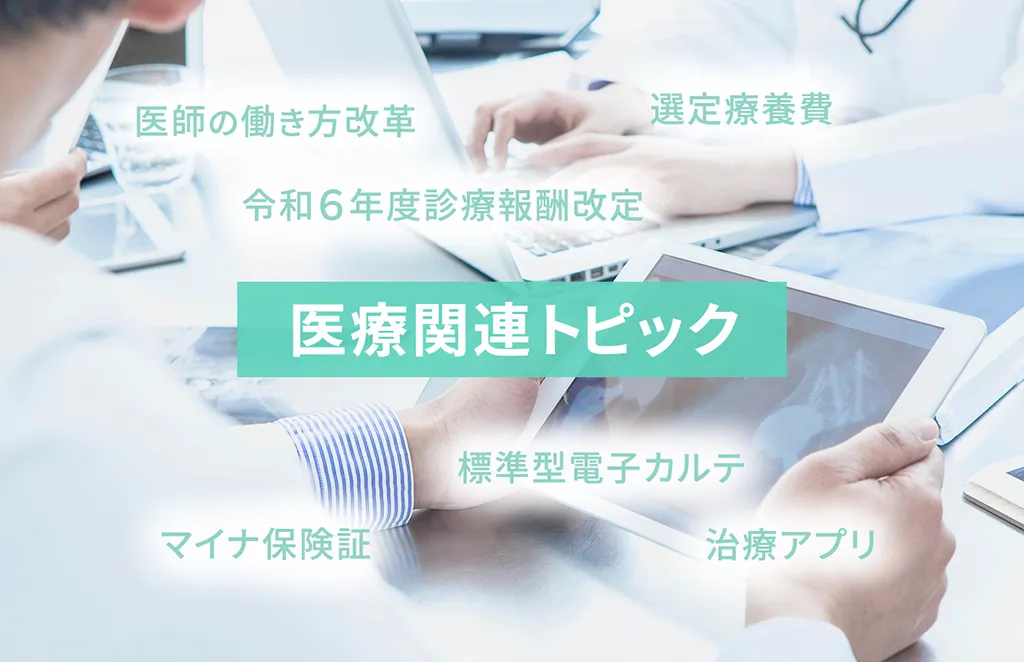
■業界動向
日本の医療業界は高齢化社会に向け、さまざまな仕組みの改革が進んでいます。
令和6年の診療報酬改定では、医療機関への報酬の見直しが行われ、医療の質の向上や効率化、医療従事者の働き方改革、患者の負担軽減を目指しています。4月には医師の働き方改革が導入され、10月には医薬品の自己負担の新たな仕組みである選定療養費が導入されました。
【医師の働き方改革】
医師の長時間労働や労務管理が不十分だったことから4月に「医師の働き方改革」が始まりました。患者さんに医療を提供する医師が健康に働き続けられないというのは大きな問題であり、この改革によってどれほど改善が進むのか私たちもウォッチしていきます。
出典:厚生労働省「医師の働き方改革」
【選定療養費】
選定療養費は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品を希望される場合に特別料金の負担が発生するというもの。もちろん先発医薬品を使用する“医療上の必要性がある場合”や 流通などの問題で在庫がない場合には特別料金は発生しません。
この仕組みによって比較的価格の安価な後発医薬品への置き換えを進めて医療費を抑え、効率的な医薬品使用を図る目的で導入されています。
出典:厚生労働省「長期収載品の選定療養」導入 Q&A
【令和6年度診療報酬改定】
今回の改定の内容を確認すると、医療環境の改善と維持に重点を置いていることが分かります。医療従事者の賃上げと人材確保、医療DXの推進、そして感染症対策の強化などが盛り込まれていました。
また、今回の診療報酬改定は、医療・介護・障害福祉サービスの報酬変更を含んだ「トリプル改定」となっています。医療DX推進体制整備加算も盛り込まれていたため、後述のマイナ保険証や電子カルテが活用できるように整備する必要があります。
他にも特定疾患療養管理料の対象疾患から生活習慣病を除外し生活習慣病管理料(II)を新設すること、地域包括医療病棟の新設などが記載されています。
出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の主なポイント」
■デジタル推進
「医療DX」推進の一環である電子カルテの標準化が始まり、2025年度中には本格的に運用がスタートします。さらに「マイナ保険証」を利用することで電子カルテの診療情報や過去の薬剤情報の共有ができ、医療機関の窓口での負担が軽減されるメリットなどもあります。
しかし、マイナ保険証については、移行や運用がなかなかスムーズに進まず、移行後は従来の保険証が発行されないことやシステムのトラブルも大きな話題となりました。また、コロナ禍をきっかけにさまざまな疾患に対応する治療アプリの開発が進んでおり、デジタル医療の進化も感じられました。
【標準型電子カルテ】
電子カルテ情報を標準化することで、ほかの医療機関の患者情報等が参照できる「全国医療情報プラットフォーム」の利用や民間事業者が提供するシステムとの連携が可能になります。
そして、標準規格(HL7 FHIR)に準拠したクラウドベースの電子カルテが「標準型電子カルテ」であり、4月にクラウドネイティブカンパニーである株式会社FIXERは、デジタル庁より「標準型電子カルテシステムα版の設計・開発業務」を受託し、システム開発に着手しはじめました。2025年より試験的運用が開始されます。
出典:株式会社FIXER:FIXER、デジタル庁より「標準型電子カルテシステムα版の設計・開発業務」を受託、プロジェクトを開始
【マイナ保険証】
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行されなくなると発表されました。しかし、マイナ保険証に関する医療機関でのトラブルが相次ぎました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みは、本来、患者にとって便利なシステムとして設計されています。具体的には、マイナポータルで特定健診の情報や薬の履歴、受けた治療内容や医療費が確認できるほか、確定申告時の医療費控除が簡単になるといったメリットがあります。これらを円滑に利用するためにも、トラブル防止策やシステムの安定運用を目指さなくてはなりません。
出典:政府広報オンライン:マイナ保険証「2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」
【治療アプリ】
病気の予防や治療をサポートできるアプリケーションとして開発が進む治療アプリ。
患者の通院頻度を減らしたり、検査の効率化にも役立っており、さまざまな治療アプリがリリースされています。8月には減酒治療アプリが発売されたというニュースもありましたが、その一方で医学的有用性が十分に示されていないとして不眠障害用アプリは保険適用を取り下げられました。
出典:サワイグループホールディングス株式会社:株式会社CureAppと日本初(※1)の減酒治療アプリ販売ライセンス契約を締結
※1: CureApp調べ ・調査年月:2024年8月 ・調査範囲: 日本国内で製造販売承認および保険適用を受けたアルコール依存症および減酒治療アプリ
出典:サスメド株式会社「サスメド Med CBT-i 不眠障害用アプリ」令和 6 年度診療報酬改定時における保険適用希望書の取り下げについて
製薬関連トピック

■業界動向
公益財団法人MR認定センター「2024年版 MR白書」によると、MR数が10年連続で減少しているということが分かり、MRの新卒採用も減っているようです(※)。しかし、その一方で夏に大手製薬企業で早期退職の発表が相次いだ影響もあってか、職種などによっては秋に転職市場の動きが活発化していました。
また、大きな話題となったのは新型コロナウイルス感染症の予防を目的とした「レプリコンワクチン」です。これについては、ワクチン開発会社であるMeiji Seikaファルマが反ワクチン団体の提訴に発展していました。
他には話題性の高い新薬の発売もありましたが、それによってダイエット目的で糖尿病治療薬の違反広告が増加し、厚労省がガイドラインを見直す方針を示しています。インターネットやSNSの多大な影響を感じる出来事も多い1年でした。
(※)出典:公益財団法人MR認定センター「2024年版 MR白書」
【人材採用】
夏に大手製薬企業の早期退職募集のニュースが続きました。
勤続年数や対象部門の条件はさまざまですが、多くの企業は経営のスリム化や組織体制の見直しを目的として実施していました。
その流れもあってか、秋には関西エリアで製造職の転職市場の動きが活発化しているということが取り上げられていました。ミドル層の人材が早期退職者となったため、良い人材の獲得に動いた企業もあるということが分かります。
出典:AnswersNews:住友ファーマ、田辺三菱、協和キリン、武田薬品…国内製薬 早期退職募集相次ぐ
出典:AnswersNews:相次ぐ早期退職で求職者の動き活発化…企業側の採用姿勢にも変化が|製薬業界 今月の転職求人動向(2024年10月)
【レプリコンワクチン】
コロナウイルス感染症予防のワクチンですが、接種者の入店拒否をする美容院や飲食店があるということから騒動になりました。
ワクチンが危険という根拠のない情報をSNSなどで拡散したり、チラシの配布をしたことも影響していましたが、一般社団法人日本看護倫理学会の緊急声明も反ワクチン派が活気づくきっかけとなったようです。それによってワクチンの供給に支障が出ているとした、レプリコンワクチンの製造販売をするMeiji Seikaファルマは、誤った認識がこれ以上流布するのを防ぐためということで訴訟に踏み切っています。
出典:一般社団法人日本看護倫理学会【緊急声明】新型コロナウイルス感染症予防接種に導入されるレプリコンワクチンへの懸念 自分と周りの人々のために
出典:日経電子版:明治HD系、反ワクチン団体を提訴へ 名誉毀損で
【広告規制】
特にダイエット治療薬や美容医療の分野は需要がどんどん高まっているため、虚偽・誇大広告も増加し続けています。それに対応する形で厚生労働省が「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説」を発行しました。
インターネット社会となり、消費者のネットリテラシーも高まっていますが、過激な宣伝により消費者が誤解しやすい状況もまだ続いています。医療機関や業者の法令遵守を促し、国民の安全を守るための施策として、違反や健康被害を未然に防ぐように働きかけることになりました。
出典:厚生労働省:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)
■新薬開発
多くの業務にAIが取り入れられ始めていますが、創薬にもAIが導入されています。創薬にAIを導入すれば医薬品の開発スピードが向上し、産業の振興や保険医療の高度化につながります。この流れがスタンダードになれば、いずれは人々の健康に貢献できるシステムとなるのではないでしょうか。
新薬開発では、OCTに注力した大正製薬から内蔵脂肪減少薬「アライ」の発売や、昨年12月に発売されたアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」も注目されました。
その一方、小林製薬の紅麹サプリ問題が起き、品質管理や製造手順の不備などで製薬メーカーの行政処分も発生していました。
【AI創薬】
AIの業務活用が多くの業界に広がっていますが、すでに約5年前からAI創薬に取り組んでいたアステラス製薬で、AI創薬が成果を上げ始めているという話題がありました。
製薬企業だけでなく、AI技術を活用して創薬を行うスタートアップやテクノロジー企業も増えているため、今後はAI創薬の分野にこれまでに登場しなかった新たな企業名が出てくる可能性もありそうです。
出典:AnswersNews:「最初は拒否反応あった」アステラスのケミストが「ほぼ全員」創薬研究にAIを使うようになったきっかけ
【内蔵脂肪減少薬「アライ」】
4月に販売開始されたのは、大正製薬株式会社の日本初となる内臓脂肪減少薬「アライ」です。
医療用医薬品から市販薬に転用された要指導医薬品であるため、薬剤師がいる薬局・薬店のみで購入ができるお薬です。肥満を改善させる薬なので内臓脂肪および腹囲の減少が効果となるわけですが、腹痛や油漏れなどの特有の事象もあることから、使用には慎重さが求められる医薬品のようです。
出典:大正製薬:日本初の内臓脂肪減少薬「アライ」発売!
【品質管理・行政処分】
小林製薬株式会社が紅麹を使用したサプリメントの摂取による健康被害が報告され、大きなニュースになりました。2024年8月には紅麹事業からの撤退も発表され、製薬業界における品質管理の重要性を再認識させるものとなりました。
他にも、製造時に承認された手順を守らず、品質が保証されない製品が市場に流通するなどで行政処分を受けた企業もいくつかありました。重大な被害が起きる前に、GMP(医薬品やサプリメントの製造で厳格な品質管理基準)の遵守を含めた再発防止策の徹底と法令遵守の強化が求められます。
出典:小林製薬株式会社:再発防止策の策定に関するお知らせ
出典:キョクトウ株式会社:行政処分に関するお詫びとお知らせ
出典:長生堂製薬株式会社:当社川内工場における不適切な方法による製造行為及び業務改善施策の強化について
社会課題をデジタルで解決へ導くために
2024年の1年間も医薬品開発のAI活用や医療体制の変化など、テクノロジーの進化から制度改革までさまざまなニュースがありました。
現在の物価高騰や少子高齢化といった社会情勢も医療・製薬業界に影響を及ぼします。私たちを取り巻く環境が常に目まぐるしく動き続けていることをみなさまも感じているのではないでしょうか。
そして、このような変化の激しい時代の中だからこそ、私たちは提供する技術やサービスを社会のニーズに合わせてフレキシブルに変化させ、提供していくデジタルマーケティング企業であり続けます。
今後もブログを通じて医療・製薬に関する情報、社会課題解決に繋ぐサービスを発信していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
この記事の担当者

内海 篤人/Uchiumi Atsuto
職種:プロデューサー
入社年:2023年
経歴:Web業界(企画・ディレクター)→ゲーム業界(プランナー・カスタマサポート)→ヘルステック企業(カスタマーサクセス・事業責任者)に従事