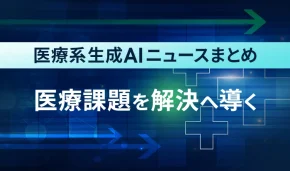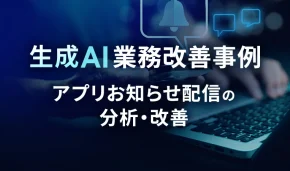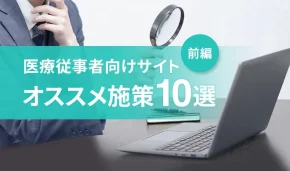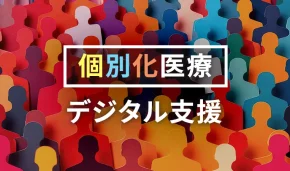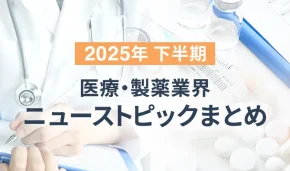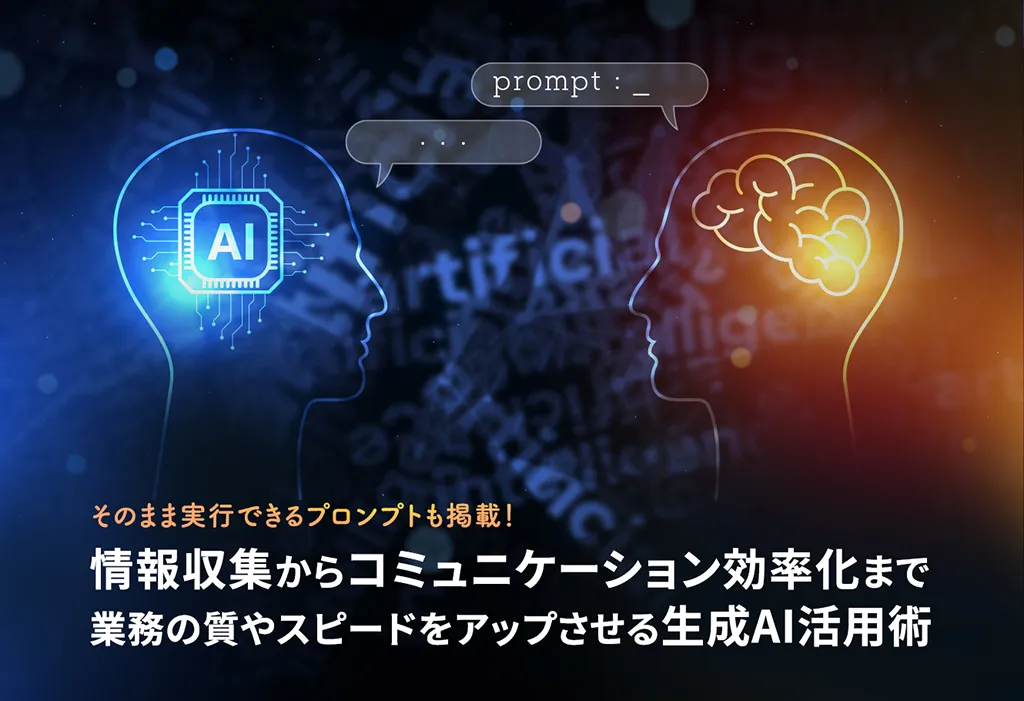
製薬企業のデジタルマーケターに向けた生成AI活用術をお伝えします。業務ですぐにお使いいただけるよう、活用シーンとともに、そのまま実行できるプロンプトも掲載しています。情報収集からコミュニケーションの効率化まで、業務の質やスピードをアップさせる良きパートナーとして生成AIを活用してみてください。
製薬業界でもますます拡大!生成AIの活用シーン
今回は、製薬企業のデジタルマーケターに向けた生成AI活用術をお伝えします。 本記事では業界に特化した活用術として、「どのような業務で使えるのだろう?」「実用的なプロンプトを知りたい」という方に向けて、一歩踏み込んだ内容をご紹介します。
以前の記事(※)では、初心者に向けて生成AIの基本的な使い方や良い回答を得るためのコツなどを解説しましたが、今回は特にマーケティング担当者や営業企画の方に使っていただけるような活用方法に着目し、事例やプロンプトを紹介していきます。
生成AIといえば、情報収集や資料作成、文章作成ができるというイメージは定着しつつありますが、マーケティング担当者が必要とする詳細な分析や営業力強化などにも応用することができます。ぜひ、日々の業務に合った生成AI活用方法を発見し、業務内での活用シーンを少しずつ拡大していきましょう。
(※)以前の記事はコチラ!

【初級者向け】知っておくと便利!生成AIの基本的な使い方4選
2025.05.15
生成AI初級者に向けて仕事で役立つ基本的な使い方を紹介していきます。業務に生成AIを取り入れた場合に何ができるのか、どう使えばよいのか、一般社員だけではなく部門トップ層にも実務に紐づいた使い方を分かりやすく解説します。生 […]
マーケティング・営業に特化した活用メリット&アイデアをご紹介!
製薬企業のマーケティングや営業企画に使える活用アイデアを紹介していきます。
プロンプトの例も掲載していますので、そのままお使いいただけます。もちろん、自社の業務に合わせてアレンジしても構いません。より良いアウトプットを追求するために活用してみてください。
【コンテンツ企画・作成】
■アイデア出し
<メリット>
自分だけでは思いつきにくいパターンまで引き出してくれるのが生成AIの強みです。複数案を瞬時に生成できるので、ブレストや壁打ち相手にも最適です。異なる切り口やトレンドを踏まえた発想をスピーディーに提案することができます。
<プロンプト例:ウェビナー・イベント企画の壁打ち>
あなたはプロのマーケティングコンサルタントです。
新製品[製品名]の発売にあたり、医療従事者向けのオンラインセミナーを企画しています。ターゲットは[専門領域]の医師です。以下の要素を含む、魅力的で参加価値の高いセミナーのアイデアを5つ提案してください。
・セミナータイトル案
・主要な講演内容
・集客のためのキャッチコピー
■コンテンツドラフト作成
<メリット>
コンテンツの全体構成や導入文をトーンに合わせた文体のパターンで “たたき台”を作ることができます。比較・検討も容易にでき、構成を生成AIに任せられるため、特に書き出しに掛かる時間を省いてスムーズに作成できます。
<プロンプト例:患者向け疾患啓発記事の骨子作成>
あなたは経験豊富なメディカルライターです。
[疾患名]について、最近診断されたばかりの患者さん(50代男性)が理解しやすいように、ブログ記事の構成案を作成してください。以下の要素を必ず含めてください。
1. 疾患の基本的な説明(専門用語を避ける)
2. 代表的な治療法の選択肢
3. 日常生活で気をつけるべきこと
4. 前向きな気持ちになれるメッセージ
■コピーライティング
<メリット>
トーン別・目的別に素早く提案することが可能です。情報提供用、啓発用、広告用など目的に合わせたコピー生成ができ、発想疲れや表現のマンネリを防ぐツールとしても有効に使えます。
<プロンプト例:医療従事者向けメールマガジンの件名作成>
あなたはコピーライティングの専門家です。
以下のメールマガジンの内容を要約し、開封率が高まるような件名を10個提案してください。ターゲットは多忙な勤務医です。
【件名に含めるべき要素】
・製品名:[製品名]
・トピック:最新の臨床試験データ公表
・メリット:明日の診療に役立つ情報』
【情報収集・分析】
■競合・市場調査
<メリット>
短時間で幅広い視点の情報を収集できます。最新の市場動向や競合施策の情報について要点を押さえたサマリー形式で抽出できるため、調査に掛ける時間を大幅に削減し、要点までまとめられた調査が手軽に実施できます。
<プロンプト例:競合製品のプロモーション活動分析>
あなたはマーケティングアナリストです。
公開情報(プレスリリース、ニュース記事、学会発表情報)に基づき、競合製品である[競合製品名]の過去6ヶ月間のマーケティング活動を分析し、以下の項目で要約してください。
・主要なメッセージ ・ターゲットとしている医療従事者層
・主な活動チャネル(Web、学会など)
・考えられる戦略的意図
■論文・文献調査
<メリット>
競合・市場調査とほぼ同じですが、専門情報の整理・要点の把握を効率化できるメリットがあります。論文やガイドラインの長文も要点や対象疾患などを抜き出してまとめ、複数の文献を横断的に比較することも可能です。
<プロンプト例:論文の要約と特定情報の抽出>
以下の論文の要約を400字で作成してください。
特に「研究方法」と「結論」に焦点を当ててください。[論文のURLまたはテキストを貼り付け] さらに、この論文における[特定のキーワード、例:副作用A]に関する記述をすべて抜き出してください。
■顧客ニーズ分析
<メリット>
営業日報や面談記録、イベント実施後のアンケートの自由回答欄などを整理・集約して、ニーズや課題を抽出できます。そのため、マーケティング施策の改善点の“あたり”や優先度がつけやすくなるメリットがあります。また、SNSやWebサイトの口コミの内容から製品や情報提供に対する反応を分析することも可能です。
<プロンプト例:面談記録からのインサイト抽出>
以下のMRの面談記録テキストから、医師が抱える潜在的なニーズや不満点を抽出し、箇条書きで3つ挙げてください。また、それぞれのニーズに対して、次回提案すべき情報やアクションを提案してください。 [面談記録のテキストを貼り付け]
【コミュニケーション】
■メール作成
<メリット>
言い回しを調整したり、お礼・お詫びの文章を作る際に時間が掛かることがありますが、目的とトーンに合わせて “伝わる文章”を素早く作れるのもメリットです。また、件名や導入文など引きとなる要素を生成AIの提案で工夫することも可能です。
<プロンプト例:KOLへのアドバイザリーボード会議の御礼とフォローアップ>
あなたは製薬企業のマーケティング担当者です。
先日開催した[製品名]に関するアドバイザリーボード会議に参加いただいた[医師名]先生へ、感謝の気持ちを伝える丁寧なメールを作成してください。以下の要素を含めてください。
・会議での貴重なご意見への具体的な言及と感謝
・議論の要点の簡潔なサマリー
・今後の継続的なご協力のお願い
■会議運営
<メリット>
会議アジェンダの構成や話し合いを整理するファシリテーションのヒントも提案できるので、運営がスムーズになります。また、会議中の議事メモや要点整理を補助し、要約・アクション抽出も支援可能なので、準備〜記録まで、会議運営全体の効率と質を底上げする使い方も可能です。
<プロンプト例:会議アジェンダの作成>
あなたはプロのファシリテーターです。
「[製品名]の次期マーケティング戦略」というテーマで90分のオンライン会議を実施します。目的は「具体的な施策案を3つに絞り込むこと」です。目的達成のための効果的なアジェンダを、時間配分も含めて作成してください。
■営業トレーニング
<メリット>
生成AIなら忙しい上司や同僚の都合を気にせず、自分のタイミングで反復トレーニングをすることができます。生成AIの質問・反応に基づいた模擬会話のシナリオを生成し、ロールプレイ形式で応答力を強化できます。また、ロールプレイ後のフィードバック例も提示できるため、自己評価・指導支援にも活用可能です。
<プロンプト例: MR向けロープレの相手役と評価>
あなたは[疾患名]を専門とする60代の男性医師です。
新人のMRが[製品名]の紹介に来ました。あなたは非常に多忙で、専門的な質問を投げかけ、MRの説明に納得できない点があれば厳しく指摘します。では、ロールプレイングを始めてください。
生成AIを戦略的に使いこなすためのヒント
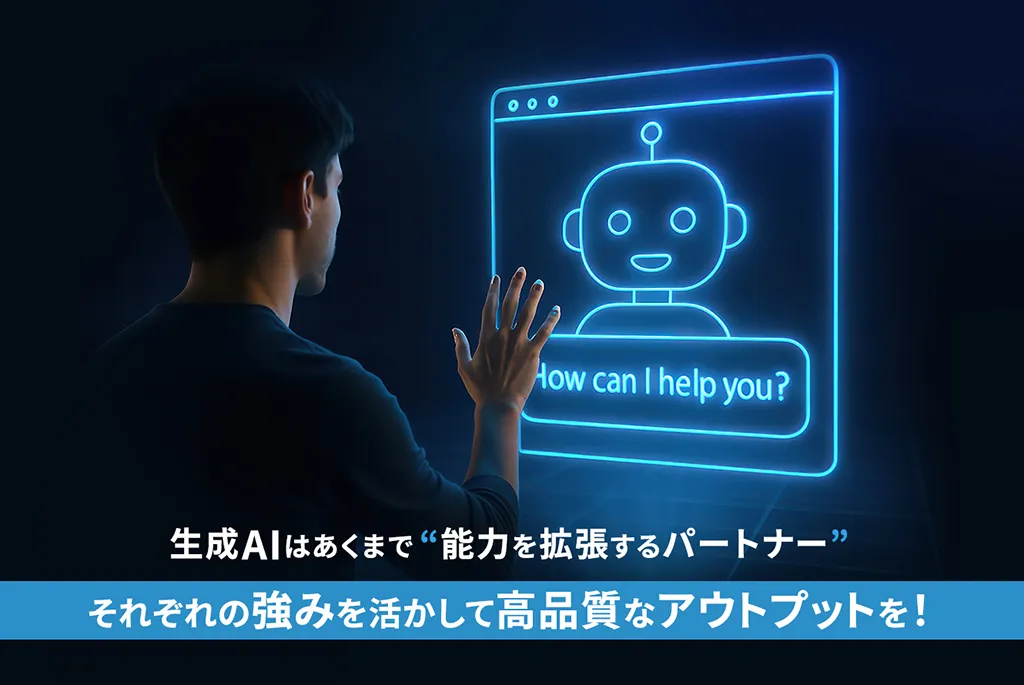
生成AIは非常に便利ではあるものの、現段階では生成AIが人間の仕事を丸ごと引き受けてくれるわけではありません。まずは、AIと人間、それぞれの強みを切り分けたワークフロー「AI支援 → 人間の判断 →活用(アウトプット)」で、明確な役割分担をしましょう。特に製薬業界のような厳しい規制がある環境では、このワークフローをしっかり整えることが効率性と信頼性を両立させるための原則となります。
【AIと人間の協調ワークフローイメージ】
■AI支援
内容:データ処理、アイデア提案、コンテンツ骨子生成、要約、レコメンデーション
生成AIの強みは、膨大な情報を短時間で処理し、それをすぐに“使える形”に整えられることです。これらを人の手のみでやろうとすると集中力と時間を要する作業になります。大量の資料を読み込むだけで時間も掛かり、さらにその内容を比較・整理するとなると資料の量に比較して時間が掛かる作業になります。しかし、生成AIはこのような時間が掛かりがちな作業を同時並行かつ瞬時に処理できます。
↓
■人間の判断
内容:ファクトチェック、最終承認、戦略的な意思決定、倫理的・法的レビュー(薬事規制遵守)、顧客との関係構築
人間の強みは、意図や背景、感情を汲み取る能力にあります。文脈と目的に照らし合わせ、正しさや妥当性を判断することについては、まだAIには理解しきれない部分も多くあります。そのため、生成AIに依頼した作業の結果をそのまま使うことはできません。最終的なアウトプットにする前には人間のチェックが必要です。このフローでは必ず、内容の正確性のチェック、文脈に即した判断、目的との整合性を確認しましょう。
↓
■活用(アウトプット)
内容:スピードと信頼性を両立し、規制に準拠したマーケティング活動、MR活動
この手順からも分かるように、生成AIはあくまで“能力を拡張するパートナー”として人間の作業効率や作業内容の質を上げるために活用するツールの一つであり、現状のAI活用にはこのフローが必要です。これを理解したうえで高品質なアウトプットに繋げるためにどう使うかを検討するのが、生成AIを戦略的に使いこなすためのヒントになります。
生成AI導入に向けた注意点と対策
業務に生成AIを取り入れる際に注意すべきポイントもあります。特に生成AIに不慣れな方は、これらの点に配慮しつつ導入していきましょう。
■セキュリティ対策やガイドラインの明確化
<注意点>
企業内で生成AIを使う際には機密情報・個人情報の扱いに対する懸念もあるのではないでしょうか。AIは既存の著作物を学習データとして使っていることが多く、そこから生成されたコンテンツによって著作権侵害のリスクが発生することもあります。また、そのデータに偏りがあれば、アウトプットにバイアスが掛かってしまう可能性が出てきます。
<対策>
生成AIが学んだ内容がそのまま再学習に使われないように設定を確認、徹底しましょう。社内では「何に使ってよいか」「どこに注意が必要か」といったルールやガイドラインを明確にし、ツールを使用する社員への周知と教育を行います。そのうえで、生成AIの提案をどう使うか、最終的な判断や責任は人間がしっかり持つようにしましょう。
■情報の正確性チェック
<注意点>
もっともらしいけれど実は間違っている情報(=ハルシネーション)を生成AIが出してくることもあります。近年生成AIの精度も上がってきましたが、正確性のチェックは必ず行う必要があります。特に製薬・医療に関する内容は誤った情報をもとに判断してしまうと健康や安全に関わるリスクがあるため、十分な注意が必要です。
<対策>
RAG(検索拡張生成)の技術を活用し、信頼できる社内データや認証済みの複数の情報源をもとに生成させることで、精度と根拠のある回答が得られやすくなります。または、プロンプトに工夫を加えて(「根拠を示せ」や「推測で答えないで」と入力)内容の信頼性を高めましょう。
■研修プログラムの実施
<注意点>
個人のスキル不足や業務フローのどこで生成AIを使えば効果的なのかが分からないというようなケースもあり、生成AIを業務に組み込むノウハウが不足している現場もあります。また、一部の使える人だけが活用を進めてしまうというのも良い使い方とは言えません。
<対策>
これらの課題には、実際の業務に即した研修やサポートでフォローすることができます。各業務に紐づいた研修プログラムを実施するのも良いですし、効果的なプロンプトの例や活用シナリオをテンプレートとして共有する機会を定期的に持つなどで対策していきましょう。まずは小さな業務から試して、うまくいった事例を少しずつ積み上げていくという、“スモールスタート”のアプローチも現場に生成AIを展開させていく方法として有効です。
「協働」の視点で製薬業界の生成AI活用はもっと広がる!

生成AIを人間と協働するパートナーとして使うことでマーケティングや営業活動の質・スピード・発想の幅を広げられる可能性が見えてきたのではないでしょうか。
生成AIの活用は「まずはやってみる」ことが重要です。ぜひ、この可能性に目を向けて、今回ご紹介したプロンプトを1つ実行してみてください。小さな1歩が、製薬業界のデジタルマーケティングを大きく前進させるはずです。
メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。生成AI活用に関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。
この記事の担当者

加藤 美羽 / Kato Miu
職種: Webディレクター
入社年:2023年
経歴:2023年新卒入社後、Webinar運用案件→ イベント事務局運用案件に従事。