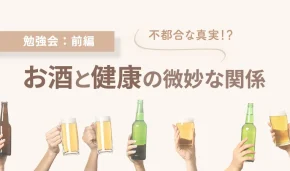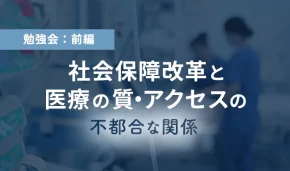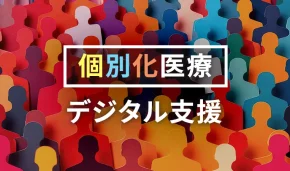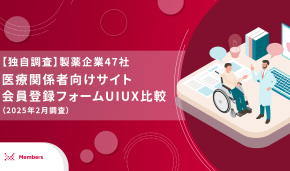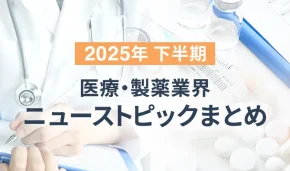病院の赤字問題について調査しました。日本の医療を取り巻く環境が問題を抱えたものであることは多くの人に知られていますが、今回はその背景や理由をたどり、さらに今後の国や地域を含めた対策も調べています。病院経営や医療の動向を把握し、潮流を捉えていきましょう。
医療の未来に深刻な影響を及ぼす病院の赤字経営
日本の病院の赤字経営は、どの程度深刻な状況に陥っているのでしょう。多くの方が日本の医療制度が危機的な状況にあることを感じているいま、病院が直面している深刻な赤字問題について背景や現状の対策も含めて調査しました。
そもそも、この問題には複合的な要因が重なっており、少子高齢化となった人口構造、病院運営コストの高騰や診療報酬制度の限界などで元々赤字でしたが、近年はコロナ禍と言われていた時期にコロナ関連補助金で一時、黒字化した病院があったものの、補助金の縮小後に再び赤字経営に陥っています。さらに、コロナ禍後の患者の行動に変容が見られたことによる影響もあるようです。
病院の財務悪化は医療の質や制度の持続性にも深刻な影響を及ぼすため、日本で医療を受ける可能性がある私たち一人ひとりがこの問題について関心を高め、医療の持続にどのように貢献できるかを考える必要があります。また、医療・ヘルスケア・製薬などのマーケティングや経営に関わっている方は政府や地域社会との関係性なども参考に、これからの戦略に活用してみてはいかがでしょうか。
病院財政の危機的な現状
まずは、病院財政の現状について近年の調査報告書などを参考に調べてみました。日本の病院経営は、コロナ補助金の縮小を機に急速に悪化し、2023年度の967病院を対象とした調査では、前年1億3,000万円超の黒字だった経常利益が約3,700万円の赤字に転落。補助金を除くと赤字額は8,400万円を超えています(※1)。経常赤字の病院割合は、2022年度の23.0%から2023年度には53.4%に急増。これは補助金が一時的な延命措置に過ぎず、病院経営の根本的な脆弱さが発覚したことを示しています。
実際、多くの病院では医療サービスだけでは利益が出ず、補助金頼みの経営が常態化していたということになります。さらに、2024年度も赤字病院が6~7割に達する見通しであり(※2)、現在の診療報酬制度では物価高や人件費増に対応しきれず、構造的な赤字体質の速やかな改善が必要となっている状況です。
(※1)参考:一般社団法人日本病院会「2024 年度 病院経営定期調査 概要版 -最終報告(集計結果)」
(※2)参考:一般社団法人日本病院会「<公表用資料>【緊急調査】2024年度診療報酬改定後の病院経営状況 調査結果_確定版.pdf」
赤字に傾く主な要因とは?

病院経営が赤字となっている主な要因を個別に解説します。
【人件費の高騰・人材不足】
人件費は病院経費の中で最も大きな割合を占め、一般的に5割を超えるとされています。
民間の一般病院では2022年度で55.7%に達しており(※1)、医師や看護師をはじめとする医療専門職の給与水準の上昇は、病院経営を直接的に圧迫するものになっています。特に看護師の平均給与は、2017年から2024年にかけて毎年増加傾向にあります。都内の病院のみのデータではありますが、8割程度の病院で人材紹介会社を利用しており(※2)、これらの手数料の影響もあるものと考えられます。
さらに、「医師の働き方改革」の推進により、時間外労働の抑制や追加の人員配置が必要となり、これがさらなる人件費増加につながっています。また、医療事務(※3)を含めた医療従事者の不足も深刻化しており、特に地方や特定の診療科では人材確保が難しく、採用コストや給与水準の高騰を招いています。公立病院では、公務員給与体系や定員条例の制約から柔軟な人材獲得が困難な場合も少なくないようです(※4)。
(※1)参考: 厚生労働省「医療施設経営安定化推進事業 令和4年度 病院経営管理指標」
(※2)参考:公益社団法人 東京都医師会「都内病院の運営状況 〜人材紹介会社への手数料の影響〜」
(※3)参考:株式会社タナカサトル技術支援「医療事務が人手不足の理由は?労働環境の問題点と人手不足の解消方法を解説」
(※4)参考: 一般財団法人 日本公衆衛生協会「令和6年度 公立病院の経営に関する調査 結果報告書」
【物価上昇・光熱費の高騰】
医薬品費や材料費、水道光熱費の高騰も大きな負担です。2022年度には前年度比で医薬品費が5.7%増加したとの報告がありました(※1)。医療材料や医療機器の価格も、物価上昇、円安、供給網の混乱などを背景に上昇傾向にあります(※2)。
さらに深刻なのは光熱費の急騰で、2022年度には水道光熱費が全体で38.8%増(電気料金47.6%増、ガス料金47.9%増)という異常な上昇率を記録しました(※1)。2024年の診療報酬改定後においても、医業収益の伸びが1.9%であったのに対し、医薬品を除く全ての経費の伸びがこれを上回ったとされます(※2)。病院側はこれらの増加したコストを診療報酬に転嫁することが困難な状況に置かれ、収益を圧迫しています。
(※1)参考: 公益社団法人 全日本病院協会「2023 年度 病院経営定期調査 概要版 -最終報告(集計結果)」
(※2)参考:一般社団法人日本病院会「<公表用資料>【緊急調査】2024年度診療報酬改定後の病院経営状況 調査結果_確定版.pdf」
【診療報酬制度の硬直性】
診療報酬は保険医療機関の全収益の90%以上を占める重要財源ですが、2024年度改定では収益は+1.9%にとどまる一方で、人件費や物価の増加 (+2.6%以上) に追いつかず、多くの病院が増収減益に転じました。2024年度では医業赤字病院が69%、経常赤字は61.2%に達し、病院団体からは「賃金・物価に対応できる診療報酬制度」への抜本的改革が求められています(※)。現在の工程ごとの価格設定では、コスト増に柔軟に対応できず、制度の硬直性が赤字を構造化しています。
(※)参考:一般社団法人日本病院会「<公表用資料>【緊急調査】2024年度診療報酬改定後の病院経営状況 調査結果_確定版.pdf」
【人口動態の変化】
2025年は国民の3人に1人が65歳以上になると見込まれ(※1)、慢性期医療や在宅需要、リハビリの拡充が求められています。一方、少子化によって小児科・産科のニーズが低下し、これらの科を維持する病院の収益バランスが悪化しています(※2)。旧来の急性期・高回転モデルでは収益確保が難しくなり、報酬体系も需給への対応が不十分です。特に外科については、2012年から減少が続いており(※3)、これは勤務時間が長い事や訴訟リスクの高さ、女性医師への配慮が乏しいことなどから外科医希望者が減っているようです(※4)。医療需要の構造変化が現行の診療報酬体系と乖離し、「機能と報酬のミスマッチ」が赤字を生んでいることがわかりました。
(※1)参考: 内閣府「令和4年版高齢社会白書(全体版)」
(※2)参考: 日本経営グループ「【レポート】コロナ禍を経て変化する医療需要と病院経営の方向性」
(※3)参考:厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
(※4)参考:一般社団法人 日本外科学会「外科医希望者の伸び悩みについての再考」
【受療行動の変化】
新型コロナ禍以降の受診控えや入院短縮化により、病床利用率が以前の水準に戻らない病院が多くなっています。2024年調査では黒字病院の利用率85.5%に対し、赤字病院は77.5%で、8ポイントもの差が収益へ直結しています(※1)。さらに、DPC制度等による在院日数短縮や外来化も固定費の高い病院モデルには収益悪化の要因です(※2)。入院中心モデルが機能しにくくなった結果、赤字転落の典型的要因となっています。
(※1)参考:GemMed「 2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体」
(※2)参考: 日本経営グループ「【レポート】コロナ禍を経て変化する医療需要と病院経営の方向性」
病院種別によって変わる経営状況・経営課題
病院の種別ごとに経営状況を比較し、動向を把握してみましょう。 公立病院、民間病院、大学病院といった、設立主体や機能の違いによって経営課題の状況や深刻度には差異があることが見えてきます。
【公立病院・自治体病院】
公立病院や自治体病院は特に厳しい経営状況に置かれ、2023年度には公立病院の69.4%が赤字であり、これはコロナ禍以前と比較して約12%増加していました(※1)。その要因は、公立病院・自治体病院は、救急医療、精神科医療、小児・周産期医療といった、採算性は低いものの地域にとって不可欠な政策医療を担うことで赤字率が高くなっています。公務員としての給与体系や職員定数条例といった制度的制約が柔軟な人事・採用を困難にし、競争力のある人材獲得を難しくしている側面もあります(※2)。
(※1)参考: 一般財団法人 日本公衆衛生協会「令和6年度 公立病院の経営に関する調査 結果報告書」
(※2)参考: Open Insight「病院の経営が赤字にならない対策と戦略|医療経済実態調査から」
【民間病院】
民間病院も経営難に直面しており、2022年度には約73%が医業赤字となりました(※)。診療報酬に強く依存する構造のため、報酬改定や物価・人件費の上昇に直撃されやすく、コロナ補助金の打ち切りは経営悪化の引き金となったようです。柔軟な運営体制を持つ反面、競争が激しく、病床利用率の低下や患者数減少も経営不安定化の要因です。コスト増と収益構造の不均衡が明らかとなり、民間病院の経営状況は診療報酬制度の現行水準が医療提供の持続性を担保できていないことを象徴しています。
(※)参考: 公益社団法人 全日本病院協会「2023 年度 病院経営定期調査 概要版 -最終報告(集計結果)」
【大学病院】
大学病院は診療・教育・研究の三本柱を担うため、構造的に赤字体質です。2020年度には大学病院全体で1,992億円の赤字を2,637億円の補助金で補填し(※)、補助金への依存が際立っていました。コロナ禍で患者数が減少し、近年は赤字拡大傾向が顕著となり、42の国立大学病院中32の病院が2024年度に経常赤字を見込んでいます。高度医療・教育・研究への診療報酬の評価が不十分なため、病床稼働率が高くても経費増により赤字を免れられない状況です。
(※)参考: GemMed「2020年度、大学病院全体で1992億円の医業赤字、ただし支援金等が2637億円投入される—医学部長病院長会議」
構造的危機を改善させるための対策と解決案
【政府の対応】
政府は診療報酬改定や財政支援で対応を図っていますが、2024年度の診療報酬改定では物価・人件費の上昇に十分に対応できていないという批判が多い状況です(※)。国としては、産科・小児科など政策医療分野や災害対応力強化、創薬エコシステムなど特定領域への支援を行うものの、赤字病院の一般運営を直接的に補填するような包括的支援は不十分です。診療報酬体系が変動コストに対応しきれておらず、柔軟性のある制度設計が強く求められています。また、医療財源の制限や地方財政力の格差も課題であり、全国的な均衡支援の仕組みが急務とされています。
(※)参考:一般社団法人日本病院会「<公表用資料>【緊急調査】2024年度診療報酬改定後の病院経営状況 調査結果_確定版.pdf」
【病院の取り組み】
病院側は、自助努力による経営改善策を進めている状況です。診療報酬請求の正確化や係数改善、地域医療連携強化などの基本的施策のほか、医薬品・材料の共同購入、省エネ、在庫管理などのコスト削減策が実施されています(※)。しかしながら、RPAや電子カルテの導入による医療DX推進は初期費用が大きく、特に中小病院には負担が重く、導入の障壁となっています。このような業務効率化と同時に、慢性期医療やリハビリ、健診外来などの多角化も図られていますが、経営余力がない病院では実行が困難なようです。行政によるDX導入支援の強化や資金的なブリッジ策の整備がなければ、構造改革のスピードは上がりにくい状況です。
(※)参考: 株式会社ニューハンプシャーMC コラム「病院・クリニック経営の課題は?赤字の要因や改善策成功のポイントを解説」
【地域連携】
2017年にスタートした制度「地域医療連携推進法人」は、地域の複数医療機関が連携し、患者紹介、共同購買、研修・人材再配置、施設の共用などを通じて効率化とサービス強化を図る仕組みです。2025年1月時点では、45法人が地域医療連携推進法人として認定されています(※1)。連携後に患者数が安定した例もあるものの、法人立ち上げ初期には一時的に手術件数が減少することや、都市部に比べ地方では医療機関間の距離や医師不足の影響もあり、連携の課題も残しています(※2)。今後は、国や自治体が制度設計を支援し、法人設立促進のためのインセンティブや成功事例を共有し改善に向かわせる対策も必要です。
(※1)参考:厚生労働省「地域医療連携推進法人制度について」
(※2)参考:厚生労働省「第19回 地域医療構想に関するワーキンググループー議事録」
【政府側への要望】
現在の状況に対して医療団体や専門家から政府側へ出された要望をまとめると、以下のようなものがあります。
・大幅な診療報酬の引き上げ
・病院の即時的経営支援
・医療従事者の給与・労働環境の改善
・DX推進支援
・診療報酬改定を待たずに行う期中改定の検討
現場の危機感に比べ、国の対応が鈍く見える中でも各団体は抜本的な構造改革を求めています。直近では6月に公益社団法人 日本医師会が病床再編の拡大と医療DXの加速化について複数の政党と合意に至りました(※)。また、こうした要望が今後の制度設計にどう反映されるかも注目していきたいと思います。
(※)参考:公益社団法人 日本医師会「【プレスリリース】3党(自由民主党、公明党、日本維新の会)合意について」
多面的な対策で赤字問題を解決へ!
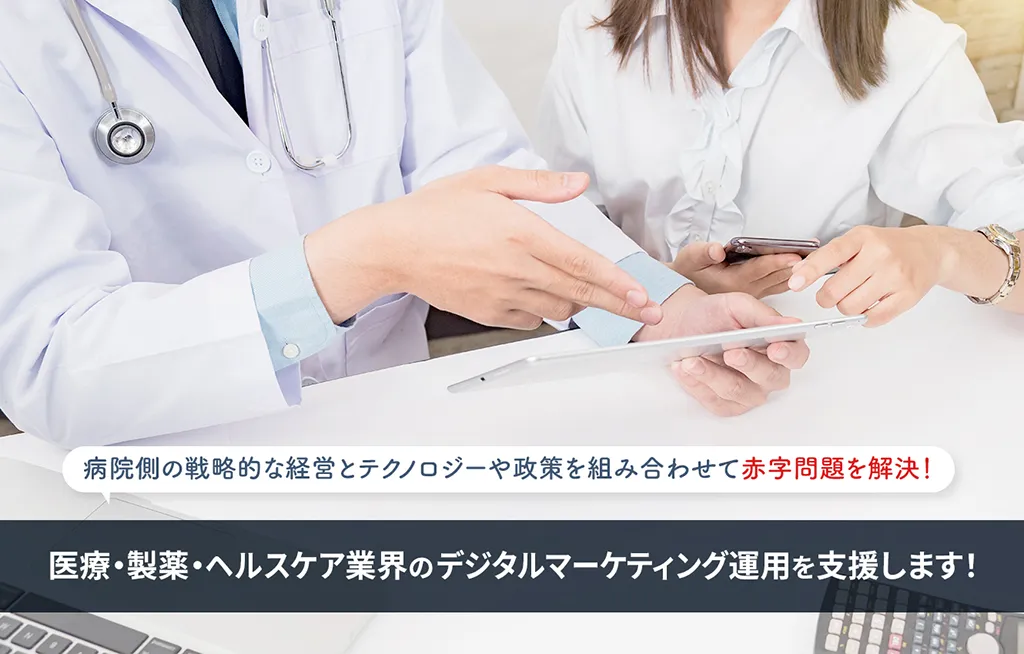
病院が赤字経営に陥る本質は構造的な問題にありますが、私たちも実感しているように、すでに制度の限界が露呈し始めています。病院側が経営を戦略的なものへと舵を切って問題を解決に導くことは必要であり、それに加えてテクノロジーや政策を組み合わせてこの局面を乗り切っていかなくてはなりません。医療・製薬・ヘルスケア業界も今後はさらに柔軟に多面的な対応ができるような組織や人材が赤字問題の解決には不可欠です。
メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。デジタルに関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。
この記事の担当者

内海 篤人/Uchiumi Atsuto
職種:プロデューサー
入社年:2023年
経歴:Web業界(企画・ディレクター)→ゲーム業界(プランナー・カスタマサポート)→ヘルステック企業(カスタマーサクセス・事業責任者)に従事