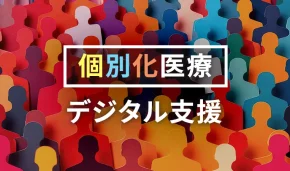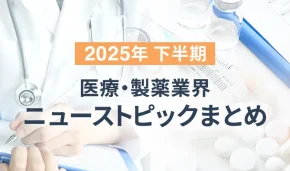私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。テーマは前半に引き続き「専門医資格の重要性」です。後半は、自由標榜制を採用している理由やジェネラリスト的な総合診療専門医について解説していきます。ぜひ、ご覧ください。
勉強会の参加者

2018年中途入社
営業
佐塚さん

2017年中途入社
Webディレクター
嶋田さん

2008年新卒入社
Webディレクター
安原さん

2023年中途入社
プロデューサー
内海さん

2024年新卒入社
Webディレクター
及川さん

2012年中途入社
Webディレクター
大畑さん

2024年新卒入社
UIUXデザイナー
田川さん

2024年新卒入社
Webディレクター
森田さん

2023年新卒入社
Webディレクター
横山さん

2023年新卒入社
Webディレクター
中村さん
なぜ自由標榜制が採用されているのか?
後半もよろしくお願いします。出席者も同じで、嶋田さん、安原さん、内海さん、及川さん、大畑さん、田川さん、森田さん、横山さん、中村さん、僕です
よろしくお願いします。
前半は、そもそも専門医とは? という基本的なお話をして来ました。
後半の最初は、前半(※)でお話した自由標榜制の話に少し戻りますね。では、なんで自由標榜制という変な制度が残っているのかというところの最大の理由から説明していきます
※前半の記事はコチラ
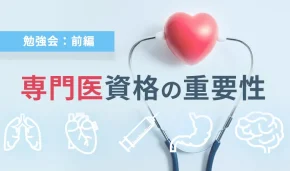
【勉強会:前編】知っていますか?“専門医資格”の重要性
2025.09.17
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。今回のテーマは「専門医資格の重要性」です。前半はどのように研修医が専門医の資格を取得していくのか […]
全員「よろしくお願いします!」
外科系の先生って、当然ですけれど病院で手術をしますよね。
でも、クリニックでは普通は手術をしません。基本的に大きな病院で手術をやっていくわけですが、外科の先生ってスポーツ選手みたいに体力がメチャクチャ要るんです。体力がいるのと、目と手先の器用さみたいなものがすごく大事。なので、年を重ねると結構きつくなるんです。
外科系だと、40代ぐらいになると脂が乗ってきて良い時期と言われますが、その後50代、60代になると何時間も長時間手術をするのがきつくなってきて、メスを置く時期が来るんです。野球選手がバットを置く時期が来るように。で、メスを置いた後にどうするかっていう時に、クリニックを開業する……というのがよくあるパターンなんですね。でも、外科系の先生なので、その時に持っている資格って当然、外科専門医とか、前半で話したように消化器外科専門医、呼吸器外科専門医とかですよね。内科ではない。
だけど、クリニックを開業する時に外科って書いても、そこで手術をしなければ患者さんは来ないわけじゃないですか。クリニックには圧倒的に内科の患者さんが多いわけで。だから内科を名乗るんですよ。世の中にある内科クリニックについていうと、外科系の専門医資格を持っているけど、内科の専門医資格を持っていない先生というのは結構いるんじゃないかなと。
でも、これがダメだという話になると商売を続けられなくなっちゃう先生がいるから、そういった大人の事情があるからこそ、自由標榜制というのが残っているんじゃないかな、というのが僕の仮説です
「直美(チョクビ)」の問題にも繋がる専門医資格の重要性
ちょっと聞きたいことが2点ほどありまして。
まず、専門医資格というのは、お医者さんのみなさん何らかの資格は持っているのか。それとも、全くもっていない先生はいるのかということと、
もう1点は、先ほど年齢や体力の限界でメスを置いてしまって、自分の専門領域ではない科に鞍替えしちゃうケースはあると思うのですが、普通の流れで考えたら自分の持っている専門医資格に関するクリニックを開業するのが一番良いわけじゃないですか。だけど、色々な事情があって違う科のクリニックを開業するお医者さんというのがどれくらいの比率でいるのか。気にするレベルで沢山いるのかどうかというのが知りたいなと
1つ目の専門医資格を全く持っていないお医者さんという点ですが、専門医資格を取るまでの修行に段階があって。
まず、医者になるためには大学の医学部を卒業して、国家試験である医師免許を取って医師になる、というのが大前提としてあります。で、医師になった後は、みなさんも研修医という言葉を聞いたことがあると思いますが、免許を取っただけでは何も分からない状態なので研修をしなければならないわけです。業界用語でローテーションと言いますが、色んな診療科をつまみ食いをするように回って基本的な知識を身に付けていく。これは初期研修と言って2年ぐらいやる。
その後、診療科を固定したような形で後期研修というのをやります。大きな診療科に分かれて、例えば、皮膚科、泌尿器科、内科とか、そこで3年間位修業して、その先で専門医資格を取っていく。
だから、医者免許を取って4~5年の人は専門医資格を持っていません。だけど、そういう先生も大きい病院の中で診療に従事していることはあります。あとは、たまに開業医でバイトしていることもないわけではないですね
そんな風に段階を踏んでお医者さんになられるんですね
で、最近ちょっと問題になっているケース。
このお話は以前の勉強会(※)でもしましたが、直美(チョクビ)ですね。直接、美容外科クリニックに就職してしまうパターン。これは先ほどお話した初期研修の2年を終えてまだピヨピヨのヒヨコにちょっと毛が生えたぐらいの状態で直接、美容外科クリニックに就職してしまうんです。この場合は当たり前ですけれど、専門医資格を持っていないですよね。
でも、そういう先生が美容外科クリニックにどんどんどんどん流入しているというのが現状なんです。ある意味恐ろしいですよね。そんな状態で本当に大丈夫? って思いますけれど、これが1つ目のご質問に対する回答です
※「直美(チョクビ)」に関する以前の勉強会はコチラ!

【勉強会:前編】増加する「直美」から日本の医療における構造的問題を考える
2025.03.19
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。テーマは、「日本の医療における構造的問題」について、増加する「直美」の医師の話題に絡めてお届けし […]
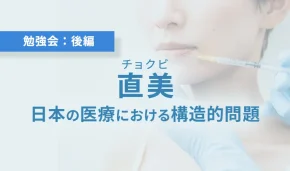
【勉強会:後編】増加する「直美」の医師から日本の医療における構造的問題を考える
2025.03.19
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。後半も引き続き「日本の医療における構造的問題」について、「直美」の医師の増加にスポットを当てつつ […]
2つ目のご質問が、色々事情があって本来の専門領域と違う診療科で開業している先生はどれくらいの割合でいるかという話ですけれど、眼科や皮膚科の辺りならせいぜい数パーセントだと思います。ただ、内科に関しては先ほど話したような形で、元・外科の先生がやっているというケースは結構あるかなと。だから、内科は違う科からきている先生が1割ぐらいはいるかなというイメージがあります。
あと、診療科の話で言うと、看板で色々な診療科を名乗っているクリニックもあるじゃないですか。内科、外科、皮膚科etc.特に田舎の方に行くと看板がまるで総合病院みたいなものもあったりしますけど、診療科のてんこ盛りをやっているところは要注意です(笑)。その内の診療科の1つぐらいは専門医資格を持っているかもしれないですけどね。地方では、まだそういうケースもあります
かかりつけ医にしたい「総合診療専門医」とは?
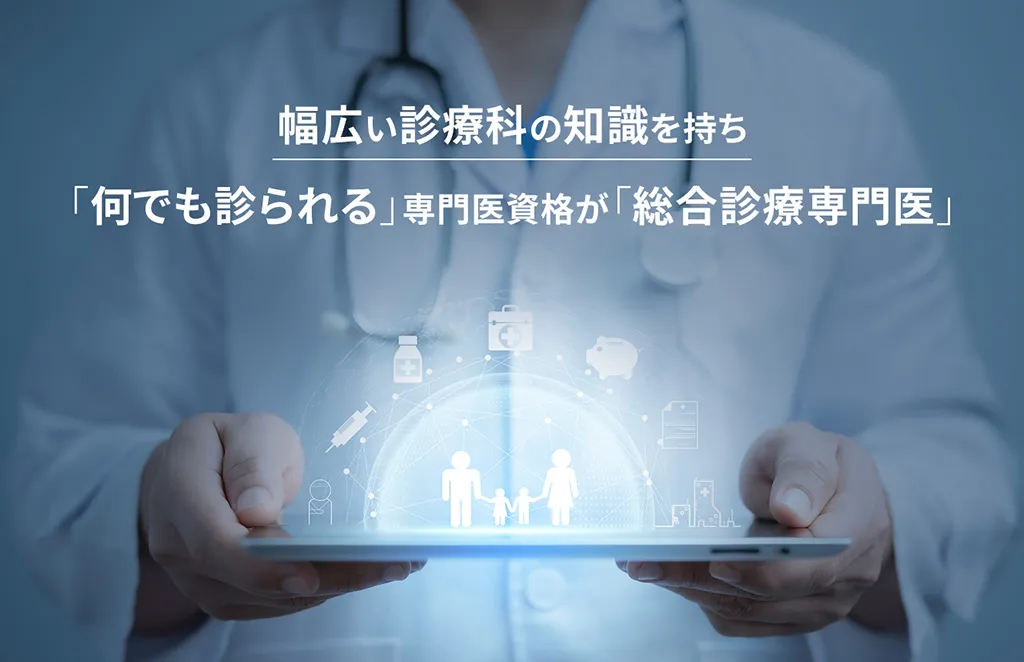
そう言えば、地元の病院で総合診療専門医の先生というのがいますね
すごい!ちょうどその話をしようと思っていました(笑)。
専門医資格については、さっき言ったような状況ではあるんですが、とはいえ、最初にかかりつけの病院で診てもらう先生は、何でも診てくれる先生の方が良いじゃないですか。実は、何でも診られるという意味での専門医というのは必要ですが、日本の医療システムではそんなに育てられてきていなかったんですね。診療科が縦割りになっていたので。
それで、今まさに嶋田さんが言われた、総合診療という部門を作ろうという話になっています。何でも診られるという意味での専門医資格が総合診療専門医なんですね。で、今はその資格で統一されてきているんですが、それまでは『家庭医療専門医』とか、ちょっと違う名前の専門医資格みたいな名前だったりしていたんですけどね。
少し前にNHK-BSで放送された『総合診療医ドクターG』という番組があったんですが、それはまさに総合診療専門医のドクターGが壇上に立って、自分が関わった症例の再現ドラマの後、この症状は何病でしょうか?といった形で若手の研修医に聞いて、その時点で考えられる病名を考えて診断を付けるようなものでした
一般人が観ても勉強になりそうですね
で、この番組と同じで、実は診断を付けるっていうのは簡単ではないんですよね。
例えば、お腹が痛いという症状でも、消化器の病気ってこともあるけれど、精神的なものからきている場合もあるし、心臓に問題があるけど、お腹が痛いという言い方をしている場合もある。やはり病名を的確に診断するなら幅広い診療科の知識が必要で、それができるのが総合診療専門医なんです。
だけど、日本の医療システムでは総合診療専門医をちゃんと育ててこなかった。総合診療専門医はまだまだ全然足りないんです。だから、近くに総合診療専門医の資格を持って開業している先生がいるなら、かかりつけ医にするには一番もってこいの先生なんですね。初期的な治療はしてくれるし、見立てもしっかりしています。例えば、ここが怪しい、と思ったらその専門の先生にちゃんと繋いでくれる。そういう役割を果たすのが、総合診療専門医です
患者にとって分かりやすいのは症状ベースの専門医!

その他、みなさんから何か質問などはありますか?
専門医同士の繋がりというか、その領域の専門医の会、みたいなのはあるんですか?
これは、前半でお話した学会がそうですね。
学術集会は全国規模の学会もあるんですが、地域単位の形で開催する学会もあります。
あとは、専門医資格を認定している学会ではなくても、同じ科の中でももっと細分化された下部団体のようなものもあります。例えば、皮膚科学会だったら美容皮膚科学会というような領域もあります。美容皮膚科の専門医資格というものはないんですが、そういった学術集会はやっていますというような団体はありますね
ありがとうございます
なので、専門医の中でも『どの先生がすごいのか』みたいな情報は良く知っていたりしますね。あと、もう1つ専門医資格の話を付け加えるとすると、患者さんにとってはお腹が痛いというのは自覚できる症状ですよね。だけど、先ほどの話のように腹痛の原因には色々あったりするわけです。そういう時に総合診療専門医に行けば見立てをしてくれる。
でも、その症状に応じた専門医資格があるなら、そこに行くのが一番なわけで。例えば、頭痛専門医というのがあるんですが、その専門医資格を持っている先生は脳神経内科の先生が一番多いとは思いますが、脳神経外科の先生が持っている場合もあります。あとは一部にはペインクリニック系、麻酔科系の方もいたり、そういった診療科横断で症状ベースの専門医資格というのがたまにあったりします。そういうのを知っておくと便利ですね。僕が知っている症状に応じた専門医資格は、頭痛、めまいなんかもあります。もっと症状ベースの専門医が出て来ると良いのかなとは思いますが
あの、急を要さない病気の時に病院を調べようと思った時に、総合的な検索サイトで探すことってあると思うんですけど、そういうサイトを見ていたら『総合内科専門医のいる病院』とかでも検索ができるんですね。これで調べても安心するのかな、と。総合内科専門医のいる病院は評判が良いみたいです
あっ!その『総合内科専門医』と『総合診療専門医』は違うんですよね。
総合内科専門医は内科の先生が持っている普通の専門医資格です。外科専門医と対になるのが総合内科専門医で、ちょっと前までは『内科専門医』と言われていたんですけど、なぜか“総合”を付け始めたんです(笑)
そうなんですね。混同してしまいました(笑)。では、自分の症状が良く分からないときは『総合診療専門医』で検索すれば良いんですね。ありがとうございます
じゃあ、今日はこんな感じでしょうか。では、みなさん、お疲れさまでした
鈴木さん、本日もありがとうございました。今回の内容は業務だけではなく、僕らが日常で通院することになった時に役立つ情報だったかと思います。みなさんも鈴木さんに色々質問をしながらヘルスリテラシーを上げていく機会にして行きましょう
全員「ありがとうございました!」
―― 今回は、「専門医資格の重要性」の勉強会レポートをお届けしました。専門医資格の認定プロセスや自由標榜制の背景を知ることで、医療機関を選ぶ際に何を基準にすべきか、より明確な視点を持てるようになったのではないでしょうか。今後も勉強会の模様をお届けしつつ、業界の知識を共有していきますので、ぜひご期待ください。
この記事の担当者

佐塚 亮/Satsuka Ryo
職種:sales
入社年:2020年
経歴:大手スポーツメーカにて店舗sales,エリアマネージメント業務を担当。のちWEB制作会社にてWEBサイトの提案からディレクションをこなし、コンサルタントとしてサイト立ち上げ後の売上向上まで支援。その後2020年にメンバーズへ入社。主にクライアントからのヒアリング及び検証データを基に要件定義を行い、サイトの構築運用を実施。定常的に支援サポートを行う。クライアントはもちろんエンドユーザーの立場・視点に立ち、問題抽出から改善案の立案までを手がける