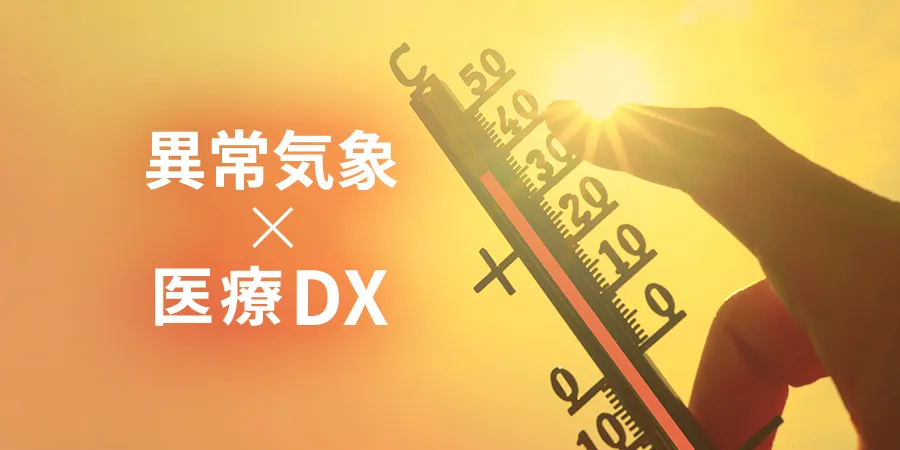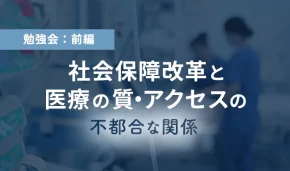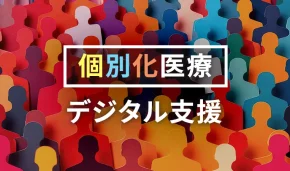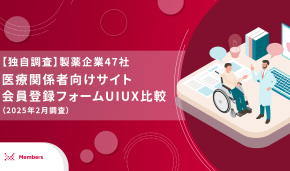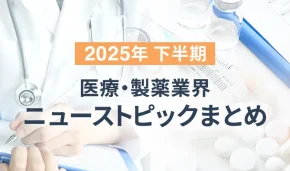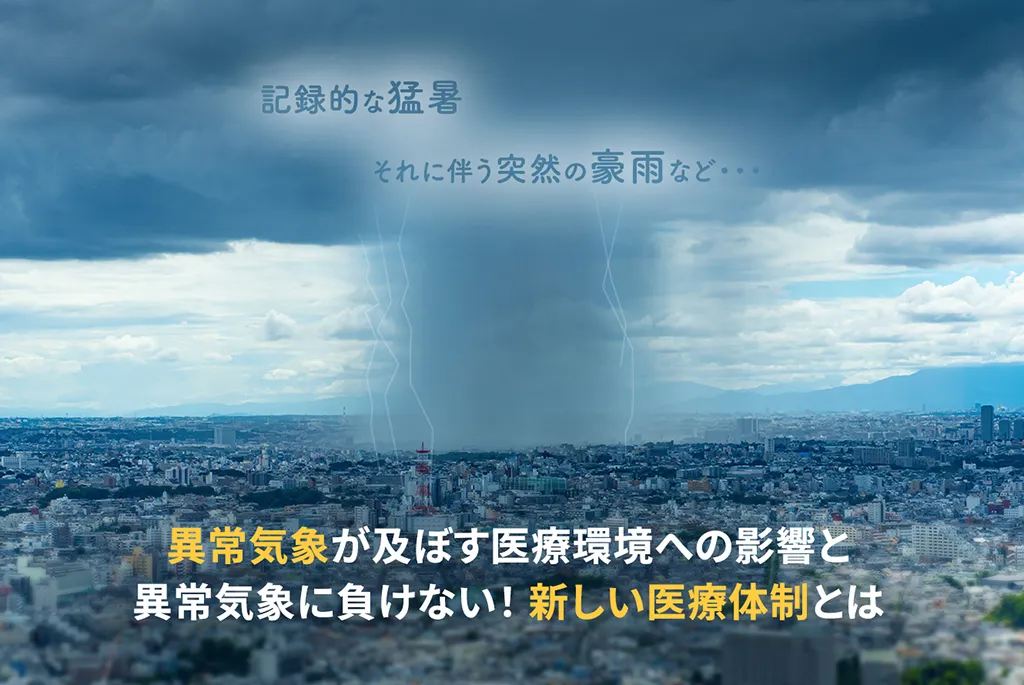
毎年猛暑となる夏。すでに春先から夏のような暑さとなる日が増え、秋まで暑いという気候に変わっています。今回は、この猛暑や暑さが引き起こす豪雨などの異常気象が私たちの医療環境にどのような影響を及ぼし、また今後はデジタルを活用した医療がどのように役立つのかについて調査してみました。ぜひご覧ください。
深刻化する異常気象の実態とは?
近年、記録的な猛暑やそれに伴う突然の豪雨などの異常気象により、医療現場は体制がひっ迫し、医療システムへの負荷が増加するなど、さまざまな問題に悩まされています。
また、この“暑すぎる夏”の問題は医療従事者の方だけではなく、日常生活を送る私たちの健康にも影響を与えており、特に猛暑に見舞われる夏の期間は「熱中症に気を付けなければ」「このまま気温が高い状況が続くとどうなるのだろう?」と不安になっている方も多いのではないでしょうか。
そして、この気候変動に影響を与えているといわれているのが、私たち人間の社会活動・経済活動ということも指摘されています。さらに世界気象機関(WMO)の予測によれば、2025年から2029年にかけての5年間のうち、少なくとも1年が観測史上最も暑い年となる確率が80%とされており(※1)、異常気象のさらなる激化に繋がる可能性が高いということです。
今回は異常気象が医療現場に与える影響を掘り下げ、この危機を乗り越えるために私たちが取り組むべき新しい医療体制のあり方について考察していきます。
(※1)参考:WMO「Global Annual to Decadal Climate Update2025」
異常気象による医療現場への影響は?
では、具体的に医療現場では何が起きるのでしょうか。考慮すべき課題をピックアップしていきます。
【熱中症の発生と死亡者数の増加】
特に熱中症に関しては多くの方が体感している問題と思われます。実際、厚生労働省の熱中症による死亡数の年次推移のレポートでは、平成12年(2000年)の207人から、令和5年(2023年)には1,651人と8倍ほどの増加が見られます(※2)。コロナ禍で減少した令和3年(2021年)は、755人という数字もありますが、基本的には上昇傾向であることが感じられるデータです。
さらに、世界レベルでも気候変動には危機感を抱いており、世界経済フォーラムの報告書によると「気候変動は2050年までに世界中で1,450万人の死亡と12兆5,000億ドルの経済損失をもたらす可能性が高い」(※3)とされています。
(※2)参考:厚生労働省「年齢(5歳階級)別にみた熱中症による死亡数の年次推移(平成7年~令和5年)」
(※3)参考:World Economic Forum「Quantifying the Impact of Climate Change on Human Health」
【慢性疾患の悪化、新たな健康問題】
暑さによって熱中症が増えていることからも慢性疾患の悪化や新たな健康問題が発生することは想像に難くありません。この暑さによって引き起こされる豪雨や大型台風が発生することを想定すると、さらに二次災害として土砂崩れや洪水が起こる可能性があります。厚生労働省のレポート「災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について」では、災害が発生すると医療へのアクセスが障害されることで持病や障害の悪化につながり、避難生活における健康リスクが増加することについて触れています(※4)。アストラゼネカ株式会社のサステナビリティでも気候変動対策に真剣に取り組む理由が宣言されており、そこに「異常気象による脱水症状や体重減少などは、慢性疾患を持つ患者さんの病気のコントロールも難しくさせ、また病気を発症する新たなリスクとなり得る」(※5)ことが述べられています。災害時においては、急性期の外傷治療だけでなく、既存の疾患管理や新たな健康問題への対応が同時に求められるということです。
(※4)参考:厚生労働省「災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について」
(※5)参考:アストラゼネカ株式会社「気候変動と健康」
【気圧変動による体調不良】
気圧の変化で頭痛を感じるなど、気圧変動は一部の人々にとって深刻な体調不良を引き起こします。頭痛以外にも、肩こり、気分の落ち込み、耳鳴り、めまい、自律神経失調症、低血圧、ぜんそく、関節痛etc.のように、幅広い症状が発生します(※6)。気圧の影響からこのような症状になりやすい方は、気圧の変動が交感神経を刺激することで自律神経のバランスが乱れ、心身に不調が表れると考えられています。
このような気圧変動による頭痛や体調不良は直接的な生命の危機には直結しないものの、日常生活の質(QOL)を著しく低下させる要因です。これは医療を提供する側にとって、気候変動が常態化する中で増加する、健康から病気に向かいつつある“未病”という状態や慢性的な不調への対応も強化する必要があることを示唆しているといえます。
(※6)参考:頭痛ーる「低気圧頭痛・不調の原因や症状とは?」
【気候変動関連死増加の危機】
上記、「熱中症の発生と死亡者数の増加」の項目で、2050年までに気候変動関連死による死亡者数が1,450万人に達すると予測されていることに触れましたが、この数字は新型コロナウイルス感染症による年間最大死亡者数を大きく上回り(WHOに報告されている全世界の累積死亡者数は2023年4月で約691万人(※7))、このレベルの感染症に匹敵するか、それ以上の影響を人類社会に与える可能性があるということです。また、新型コロナウイルスにはワクチン接種で対抗することができましたが、気候変動が引き起こした関連死を防ぐには、公衆衛生の戦略として治療から予防・適応へと根本的にシフトさせ、長期的な視点での対策を緊急に講じる必要性があります。
そして、日本医療政策機構の「日本の看護職者を対象とした気候変動と健康に関する調査」では、多くの看護職者(72%)は、気候変動は重要な課題であると回答しているという調査結果(※8)もありました。これは、医療システム自体も温室効果ガスを排出する気候変動の加害者としての側面も持ち合わせている事実から、医療機関は、廃棄物管理、デジタル技術の利用、エネルギー管理、環境に配慮した施設管理、持続可能なサプライチェーンの利用、移動・輸送に関する取り組みなどを通じて、自らの環境負荷を低減する努力を強化する必要性に迫られているということです。
(※7)参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の世界の状況報告」
(※8)参考:日本医療政策機構「【調査報告】日本の看護職者を対象とした気候変動と健康に関する調査(最終報告)(2024年11月14日)」
【医療資源不足と供給網の課題】
異常気象による災害が起きた場合には、電力、通信、交通といった基幹インフラに壊滅的な影響があり、医療提供体制の脆弱性が露呈します。例えば、電気の供給がストップすれば空調停止による熱中症増加だけでなく、人工呼吸器や吸引器、透析医療設備などの生命維持に必要な医療機器の停止、さらにはさまざまな通信が断絶したことで医療機能が停止してしまいます。また、道路の損壊や交通網の寸断によって医療機関へのアクセスが困難になり、道路が混雑して患者の搬送に長時間を要する状況に陥る可能性があります。このような状況下では患者の所在地の把握ができなくなり、搬送ルートが途絶えて命に関わるようなケースも想定されます。さらに、道路状況の悪化は医療資源の不足も招きかねません。特に医療従事者の人材と医薬品・医療器具などの物資の不足、必要な薬や医療ケア用具、衛生材料などが患者の健康状態を悪化させる要因となります。
こういった連鎖的な影響を断ち切るためには、インフラ間の相互依存性を考慮した多層的なレジリエンス強化が必要であり、単なる復旧だけでなく、事前対策と代替手段の確保をしなければならないといえます。
異常気象に対応する新たな医療技術
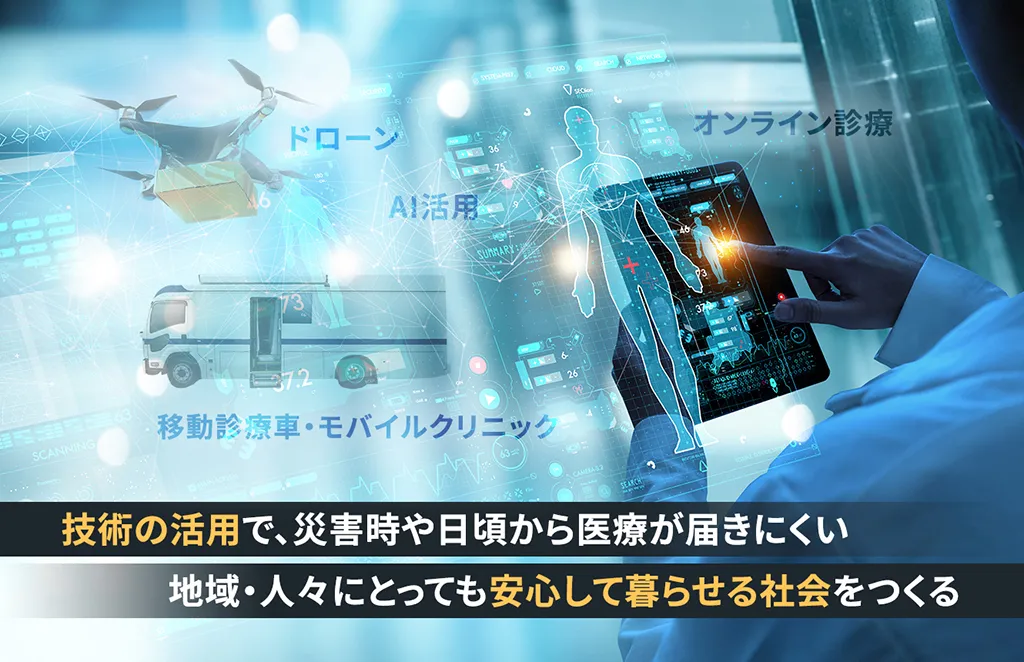
気候変動による影響は、電力、通信、交通さまざまな場面に及びますが、これらに対応するデジタル技術も進化を続けています。以下から異常気象や災害時を想定して備えられた医療技術や体制について紹介していきます。
【オンライン診療】
コロナ禍の時期、一気に広まった感のあるオンライン診療ですが、異常気象に対応する新たな医療技術として多くの可能性を秘めている診療体制といえます。
直近では、2024年の1月に発生した能登半島地震でオンライン診療が被災地医療において重要な役割を果たしたという報告(※9)もありました。物理的なアクセスが困難な状況下でも、患者と医療従事者のつながりを維持することができたという、災害時医療における事例です。
オンライン診療は、このような災害時だけではなく、普段から病院にアクセスしにくい地域、高齢者やけがなどで外出しにくい方々にとって医療を受けやすくする手段にもなりつつあります。または、雪が積もったり道路が凍ったりして外出が難しくなるような、一部の地域だけで起こる災害でも医療を続けることができます。
そして、能登半島地震では、「災害時モード」と呼ばれるオンライン資格確認システムの特別な機能が役立ったという事例もありました(※10)。この機能を使うことによって、マイナンバーカードや健康保険証を使う患者さんの名前や住所などの基本情報から本人を特定し、同意を得たうえでこれまでの薬の履歴や診療内容、健康診断の結果などを医療スタッフが確認できるというものです。これによって避難先の病院や薬局でも、普段とは違う医療機関であっても、患者さんに合った治療をスムーズに続けることができます。災害時に医療スタッフ同士が情報を共有しやすくなり、患者さんにとって最適な治療を考えるうえで役立つツールだと実証された好例です。
つまり、オンライン診療には『普段の生活で便利に使える』ことと、『災害などの非常時に使える強さ』という2つのメリットがあります。そのため、オンライン診療は平時から使っておくことで有事でも利便性が発揮されます。例えば、ヘルスケアアプリでは登録したデータをオンライン診療時に連動できることもあります。アプリで健康チェックなどをしている方は、より良い診療・治療に繋げやすくなるため、普段から利活用してみても良いかもしれません。
こうした利便性に期待が高まる一方で、オンライン診療を拡大するために考慮しなければならない課題もいくつかあります。
■診療報酬制度の見直しと柔軟なルール策定
・オンライン診療を導入しやすくするために、診療報酬制度を見直し、オンライン診療でも十分な収入が得られるようにする。
・災害時などは、「初診は対面で」という原則についても緊急時の医療ニーズに迅速に対応できる制度設計にしておく。
■ユーザーサポートと通信・セキュリティ強化
・高齢者やスマホ・パソコンの操作が苦手な人でも安心して使えるよう、使い方のサポートや相談窓口を全国で整える。
・通信が安定してつながる環境を整えるとともに、個人情報が漏れないようにセキュリティ対策をしっかり行う。
■情報共有システムとの連携強化
・オンライン診療のシステムと、電子カルテや災害時の医療情報共有システム(EMISなど)をつなげて、患者の情報をスムーズに共有できるようにする。
このように、オンライン医療システムの普及を進めるには単に技術を導入するだけでは不十分です。医療従事者に負担をかけすぎない制度の整備とともに、患者さんや医療従事者も含め、それぞれ違った使い方や理解度を持っているため、使用者に合わせた人間中心設計が大切です。具体的には、「操作が難しくない」「見た目が分かりやすい」「直感的に使える(説明がなくても自然に使える)」システムを導入することで、災害時でも多くの人が迷わず使え、医療へとスムーズに繋げられます。
(※9)参考:山口県医師会報「オンライン診療に係る情報共有会」
(※10)参考:厚生労働省「避難先の医療機関・薬局で患者の薬剤情報等を活用」
【移動診療車・モバイルクリニック】
災害発生時に被災地へ迅速に医療を提供するための重要な手段として移動診療車やモバイルクリニックは欠かせません。
さらに、移動診療車にデジタル機器やオンライン診療システムを搭載し、遠隔で医師や看護師が連携して診察や指導を行うことは、災害発生時の人々の健康や医師不足の地域で暮らす人々を守りつつ、医師自身の負担を分散させるためにも有効な手段といえます。
これを取り入れた事例として、長野県伊那市では、オンライン診療システムを搭載した移動診療車が開発されていました(※11)。看護師が車両に同乗して患者の元まで移動し、患者が車内に乗り込んだ後、遠隔地の医師がテレビ電話を通じて患者を診察し、看護師が医師の指示に従って診察の補助を行うといったもので、車内でオンライン診療を行う新しい医療を推進していました。少子高齢化と、それに伴う医師不足をテクノロジーで解消しようとしている試みです。
このように、移動診療車とオンライン診療システムの連携は、これからの日本における医療提供の効率性と対応能力を大幅に向上させる可能性を秘めています。
(※11)参考:伊那市「モバイルクリニック」
【ドローン、AI活用】
災害時や過疎地域、高齢者が多い地域などでは、病院へのアクセスが難しくなることも予測されます。そんな時、AIやドローンなどの最新技術が医療と人命を守るための大きな力になります。ニュースなどでも見ることがありますが、ドローンは人が近づけない危険な場所でも飛ぶことができるため、逃げ遅れた人の捜索、医薬品や食料などの物資の運搬に活用され、救助活動をスピーディに進められます。例えば、山間部や孤立した地域、高齢者が多く移動が困難な場所でも医療支援を届ける手段として非常に有効です。
また、私たちにも身近なツールであるAIは、過去の災害データやリアルタイムの情報をもとに、災害が起こる可能性を予測したり、どこに避難すべきか、どんな支援が必要かを判断したりすることができます。これにより、医療機関や自治体が迅速に動けるようになり、患者さんの命を守るための判断がより正確かつ早く行えるようになります。
このような技術の活用は、災害時だけでなく、日頃から医療が届きにくい地域や人々にとっても安心して暮らせる社会づくりにつながります。
進化を続ける医療DXで気候変動へ挑む!

現代の異常気象による医療現場への影響は、私たちが過ごしている日常生活の中でも実感できる内容だったのではないでしょうか。それほどに多くの方が危機を感じる気候になっているということでもありますが、今後に備え医療体制がどのような状況であるのかを把握し、デジタルを駆使した便利なサービスが豊富にあることを知っておくと非常時にも役立ちます。
当ブログでは、業界ニュースやデジタルに関する知識なども発信しています。また、今回のようにヘルスケアに関する情報も紹介していきますので、ぜひ、今後もチェックしてみてください。
メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。業界に特化したDX、AI導入や活用全般のご相談など、デジタルに関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。
この記事の担当者

鈴木 まりあ / Suzuki Maria
職種: Webディレクター
入社年:2024年
経歴:2024年新卒入社後、コーダーとしてWebサイトの運用・リニューアル業務に従事。現在はWebディレクターとしてWebサイトの運用案件を担当。