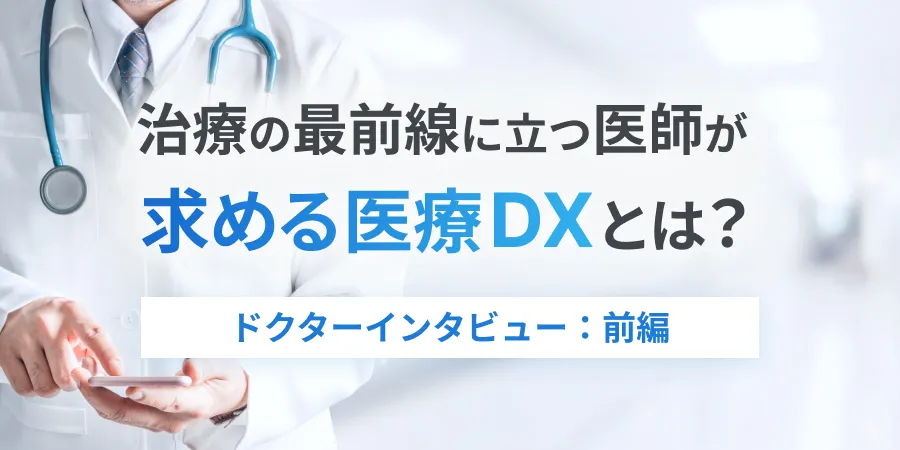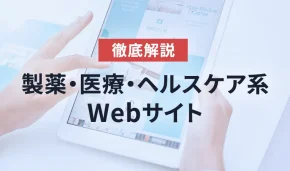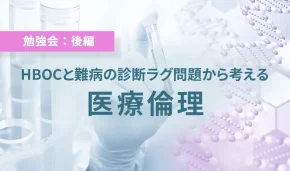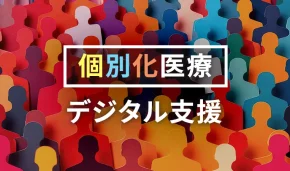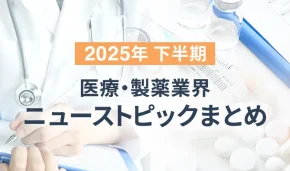今回は、“リアルな医療現場の声を伝える”ドクターインタビューです。お答えいただいたのは、社会福祉法人 三井記念病院 泌尿器科・地域医療部部長、がん診療センター副部長 榎本 裕 医師です。医療の最前線で治療を行いながら日々の情報やMRとのやり取りについてどのように感じているのか、また、榎本先生ご自身の医師としての信念なども含めてお話を伺いました。ぜひご覧ください。
泌尿器科を選ぶきっかけは未知への探求心!
―― 本日は、よろしくお願いいたします。最初に、先生のご経歴や現職についてご紹介をお願いいたします。
よろしくお願いします。
東京大学を平成6年に卒業し、その後すぐに東大の泌尿器科に入局しました。当時はストレート研修がメインでしたが、わがままを言って1年ぐらいの間、スーパーローテーションと言う程ではないですが、内科などを回り、その後はずっと泌尿器科医をやっています。
―― 基本的には、最初に入られた医局にずっと在籍されるのでしょうか?
僕らの頃は卒業時に科を決めて、そこに入局するのがメインの方式ですね。何らかの理由があってキャリアチェンジをする先生もいますが、多くの方は最初に選んだ科をそのまま進んでいきます。
―― 先生が泌尿器科を選ばれた理由は何でしょう?
僕の場合は、泌尿器科の実習の時に何度もがんの部分切除をしている患者さんを見たんです。腎臓に腫瘍が次々と生じる“フォン・ヒッペル リンドウ病”という疾患があるのですが、それが腎臓にできた患者さんがいて。それを見て、泌尿器科は想像以上にすごいことをやっているな……と感じたことがありました。
あとは、当時の泌尿器科の教科書はものすごく薄かったんですよ(笑)。内科は分厚いのに、こんなに(指でジェスチャー)薄くて。だからこそ、泌尿器科には分かっていないことがまだたくさんあるのではないか、面白いかもしれないぞ!
と思ったんです。
―― 未知の探求、というような感覚だったのでしょうか?
そういうところもありましたね。
で、大学卒業後は大学院に行き、その間に少し臨床もやるんですが、4年間は臨床をまるまる離れ、さらに留学にも2年間行きましたので、臨床を6年間離れた期間もありました。
で、留学が終わり、大学に戻ったら『泌尿器科の透析室に行け』と言われて。泌尿器科の中では透析(※)は特殊分野になるので、これではオペができないな……と少し不安に思ったのですが、どうせならそこで透析専門医資格を取ろうと。
※透析療法:腎臓の働きの一部を人工的に補う治療方法
―― ホームページの榎本先生の専門分野に腎不全が入っていたので、泌尿器科なのに腎不全ってちょっと違うなと思いましたが、そういった理由だったのですね。
腎不全にも外科の分野があるので、透析から離れた後も腎移植などにも関わらせてもらいつつ、そこからのメインはがんという感じでしょうかね。
―― 科のスタッフの方は先生を含めて何名いらっしゃるのでしょうか?
常勤6名です。非常勤の先生は、手術の日の外来を担当してもらうような形ですね。
―― 先生は、やはり外科寄りの志向が強いのでしょうか?
手術は好きですけれどね。泌尿器科は診断から手術、薬物治療までを一貫して行い、最後まで患者を診ます。消化器内科と消化器外科のように同じ臓器で外科と内科が分かれている科と違い、基本的に泌尿器科に対応する内科というのは無いんですよ。
腎臓内科は腎不全など一部を扱いますが、腎臓がんなど泌尿器の腫瘍を診るのは泌尿器科です。泌尿器科は泌尿器疾患全般を担う科ですから、外科の手術だけではだめなんですね。ここに来て13年目になるのですが、当院は泌尿器科としては他の病院と比較して大きな病院なので、手術しかできないというわけにはいきません。
知識のアップデートは真面目にやらないと下からも突き上げられますから、そこは頑張っています。
―― 優秀な先生も研修に来られるのでは?
そうですね。手術もそれなりにやっていますし、患者さんも多くいらっしゃいますから、真面目に取り組もうと思っている方が来ます。なので、こちらもそれに応えられるようなものを持ち続けなければいけないと思っています。
泌尿器科はロボット手術のトップランナー!
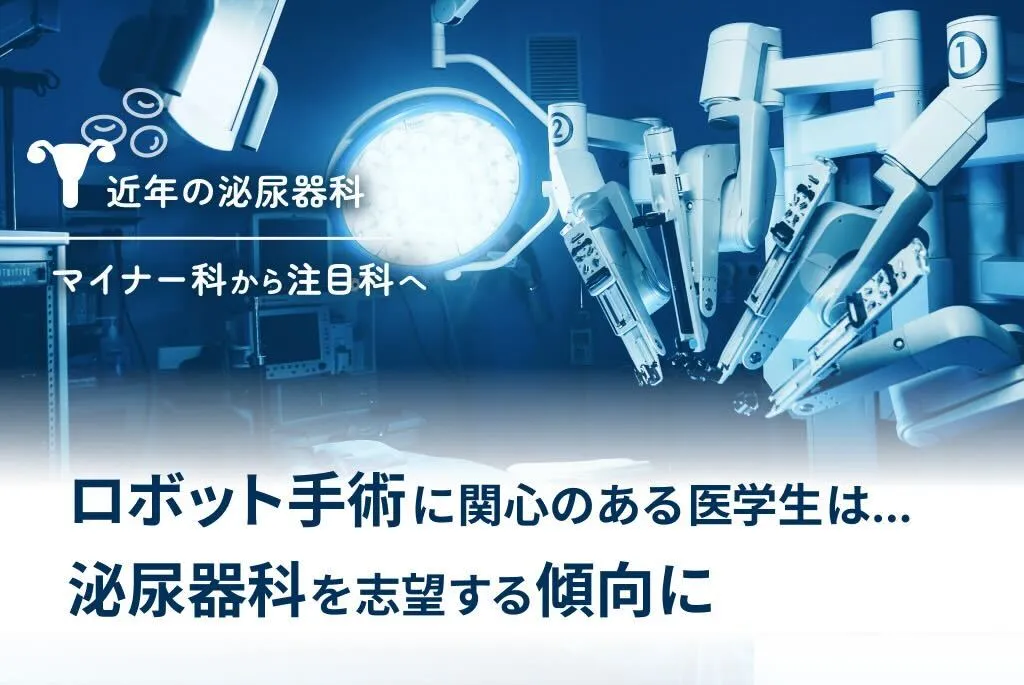
―― 泌尿器科は医学生からどれくらい人気があるのでしょうか。
今、手術の中ではロボット手術(ダ・ヴィンチ手術)というのがクローズアップされていて、やはり外科志向の学生にとっては魅力的な選択肢となっていますね。泌尿器科がロボット手術のトップを走っていたので。
―― 泌尿器科が先行していたのですね。
はい。泌尿器科がトップで、消化器外科、産婦人科、呼吸器外科……今は他の科でもやるようになりましたけど。
でも、最初の数年間は泌尿器科しかやっていませんでしたし、数も多かったですから。なので、ロボット手術というと、学生からすると泌尿器科のイメージが強いのでしょうね。その影響もあり、ロボット手術に関心のある学生が泌尿器科を志望する傾向が見られます。
―― 泌尿器科がロボット手術のトップということは初めて知りました……!
一般の方からすると、そう思われるかもしれません。『泌尿器科も手術をするんですね』なんて言われるぐらいですし、ロボット手術が一番多いというイメージを持っている方の方が少ないと思います。
でも、正直に言えば、泌尿器科の人気が出たのはロボット手術をするようになってからじゃないでしょうか。それまではやはり、マイナーな科でしたから。
―― 先ほど、先生も教科書が薄いとおっしゃっていましたからね。
そうです。でも今は大分教科書も厚くなりましたけれど(笑)
―― (笑)。泌尿器科のことについて詳しく知ることができました。ありがとうございました。また、先生はがんも診ていらっしゃいますが、泌尿器科のがんというのはどういったタイミングで見つかるのでしょうか?
泌尿器では腎臓、膀胱、前立腺、精巣などを診療対象としています。症状があって見つかる方もいらっしゃるんですが、腎臓とか前立腺のがんの場合、ほとんどは検診ですね。
膀胱のがんだったら、血尿とか。血尿だったり頻尿だったり、尿に関わる症状がきっかけになることもありますけど、圧倒的に検診によって発見されます。
あとは、症状のない方は、他の病気の検査でCTを撮った時に見つかるケースもあります。
医師として大事にしているのは、患者さんの要望を知り、寄り添うこと
―― 検診の重要性がよく分かりました。続いて、先生が患者さんとの付き合い方で大事にしていることは何かありますでしょうか? 診療スタイルは医師によって異なるかと思いますが、先生のお考えをお聞かせください。
そうですね。僕は患者さんが何を求めているのかを把握することを最も重視しています。こういうがんで、こういうステージだから、標準的な治療はこれ……という案を持っているわけですが、その案について患者さんにも納得して受けてもらうためには、意見を押し付けるわけではなく、患者さんが何を求めているのかを知っておくことが重要だと考えています。
例えば患者さんが『その手術は受けたくない!』と言うこともあって、『医者の勧めることを聞かない患者の方が良くないんだ!』というスタンスになる医師もいるわけです。ただ、そういった場合、なぜ患者さんがその手術を受けたくないのかをきちんと聞けば理由があります。こちらとしてもそれは仕方がないね、ということもあれば、単なる誤解ということも多々あります。
多くの場合は、きちんと話をすれば我々の言うことを理解していただけて、治療に進むことができる。最初に患者さん側の理解がないと最後まで絶対に上手く行きません。僕の場合、例えばがんが進行していて、治療が上手く行かないことが予想される患者さんだったら、ある程度先のことまで話してしまいます。現段階でのベストな治療と、それに対する患者さんの意見はどうなのか。そこを聞きながら治療していくことを心掛けていますね。
―― 自分の意見を尊重してくれる先生というのは患者さんからすれば嬉しいでしょうね。ただ、そのような診療スタイルですと、I・C(インフォームド・コンセント)の機会も多くなるのではないでしょうか。
そうなってしまいますよね。診療時間が限られている中ですが、重要な局面では時間を確保し、丁寧に説明するよう努めています。
―― 先生が担当されている泌尿器科およびがん診療センターにおける診療方針や、病院経営に対するお考えについてお聞かせください。
管理職としての立場になると、診療に加えて経営面への配慮も不可欠になります。手術をたくさんやらなくてはいけない、患者さんをたくさん診なくてはいけない、ダイレクトに言ってしまえば売上を上げなくてはいけないというのは1つの目標としてはあります。
ただ、それは、患者さんにとって良い医療をしたうえで、ということが絶対です。手術をするにしても、何でこんなところまで手術してしまうの? という疑問が無いように、科の中でも一定の基準を保ちながら業務に取り組んでいます。
日々のカンファレンスなどで明言することはありませんが、スタッフに対しては一貫した姿勢を示すことで、理念が自然と共有されるよう努めています。
最新情報の収集源は幅広く、使い分け方もさまざま

―― 次は、情報の入手についてお聞きします。先生は日々、技術の研鑽をされていらっしゃると思いますが、情報源はたくさんお持ちですよね。例えば、エムスリー、ケアネットといった国内の医療情報サイト、パブメド(PubMed:米国立医学図書館作成の医学文献データベース)などの海外論文サイト、MRさん、学会など、様々な選択肢があるかと思います。その中で、特によく利用されているものや使い分けの工夫などはあるのでしょうか?
今挙げていただいたものはいずれも活用しています。定期的にメールマガジンなども届きますし、気になるものは見ますね。泌尿器科を指定しておけば、関連する情報がリストに上がってきますし。特に関心のあるテーマについては、元となる情報まで遡って確認するようにしています。
ただし、パブメドなどの海外論文データベースは情報量が膨大で、玉石混交の面もあるため、一次情報の確認というよりは、既に目にした情報の裏付けとして利用することが多いです。
―― 二次調査というか、ある程度、情報を絞った状態で見に行くという感じですね。
はい。他には、医療メーカーさんですね。もちろん、製品に関する情報が中心ではありますが、その中でも面白い情報があれば『それはどこに載っているの?』なんて聞くこともあります。
また、僕は海外の医療情報を日本語に翻訳して紹介するサイトの翻訳の監修を20年ほど担当しており、FDA(Food and Drug Administration:アメリカ食品医薬品局)の医薬品や医療機器が承認されたという情報も入って来ます。そこから、FDAで承認されたなら、そろそろ日本にも入って来るかな、と予測したりしますね。そのサイトについては、泌尿器科医でその監修をやっているのは僕だけですので、意外と良い情報源になっていたりします。
―― そういった翻訳の監修を手掛けている先生というのは、初めてお聞きしました。
とはいえ、最近はAI翻訳、なんていうものもありますので、翻訳に関しては以前に比べると直すところも少ないんですけどね(笑)
―― 医師同士の交流を通じた情報収集の機会についてもお伺いしたいのですが、ドクター同士の集まりというような形で情報収集の機会はあるのでしょうか?
医師が自発的に集まる会合は、実際にはそれほど多くありません。みなさん忙しくて予定が合わないので、メーカーの講演会の後の懇親会などで話すことはあるにはありますけれど、医療情報を交換し合うというより、単に世間話をするような形の方が多いですかね。
あとは、学会も大事です。最近はこういう手術がある、というような新しい情報はなかなか上がってこないので。
―― 情報収集の主戦場としては、メインは学会という感じなのですね。
そうですね。あとは、ガイドライン(※)が新しく出たら見ます。情報という意味では固定されたものですが、おさらいという意味で見落としが無いようにそこは必ず確認します。
※ガイドライン:エビデンスなどに基づいて、最良と考えられる検査や治療法などを提示する文書
―― 泌尿器科のガイドラインというのは、どれくらいあるのでしょう。
非常に多岐にわたります。良性疾患、悪性疾患、色々ありますから。なので、ガイドラインが出れば必ず目を通すようにしています。
―― ガイドラインは毎年公開されているわけではないのですか?
毎年、というわけではないですが、更新があると学会のホームページに公開されるので見るようにしています。今、推奨されている治療法を把握することは、診療の質を保つうえで不可欠です。また、こんなことも書いてあったのか、という発見もありますし。
あとは、がんに関しては海外のガイドラインも定期的に見ます。薬などに関しては向こうの方が早いので。僕はスマホで見ていますよ。全部クラウドに上げて、いつでも閲覧できるようにしています。
スマホでの情報チェックは忙しい医師には必須!
―― やはり、今は榎本先生のようにスマホやAIなどのツールを使いこなすような先生の方が多いのでしょうか? ステレオタイプというか、自分なりのこだわりを貫くアナログ派の先生もいらっしゃるのでしょうか。
ガイドラインを使用する時代になって長いですから、そういった “マイルール”でやっている方は少なくなりましたね。それに、そういったスタイルですと若手医師の理解や協力を得ることが難しくなるため、標準化された指針に沿った診療が求められる時代になっていると感じます。
―― スマホなどを使って多くの情報に触れる中で先生が特に重視されている情報の特徴についてもお聞かせください。例えば、視認性が低くても信頼性が高い情報や、費用がかかっても価値があると判断される情報など、選定の基準があれば教えてください。
情報の信頼性はもちろん重要ですが、スマホで見られるというのは大事かもしれませんね。
―― 病院といえば、オンプレミスの電子カルテで、インターネットの閲覧が制限されるケースあると思うのですが、その辺りは、みなさんが個人の端末で見ているイメージがありますが、どのように対応されていますか。
当院では、電子カルテはイントラネット上で運用されていますが、外部ネットワークへの接続も可能です。切り替えによって対応できるため、大きな不便はありません。
ただし、実際には自身のスマホの利便性が高いため、そちらを活用することが多いです。
近年のMRやMSにはやや不満も……
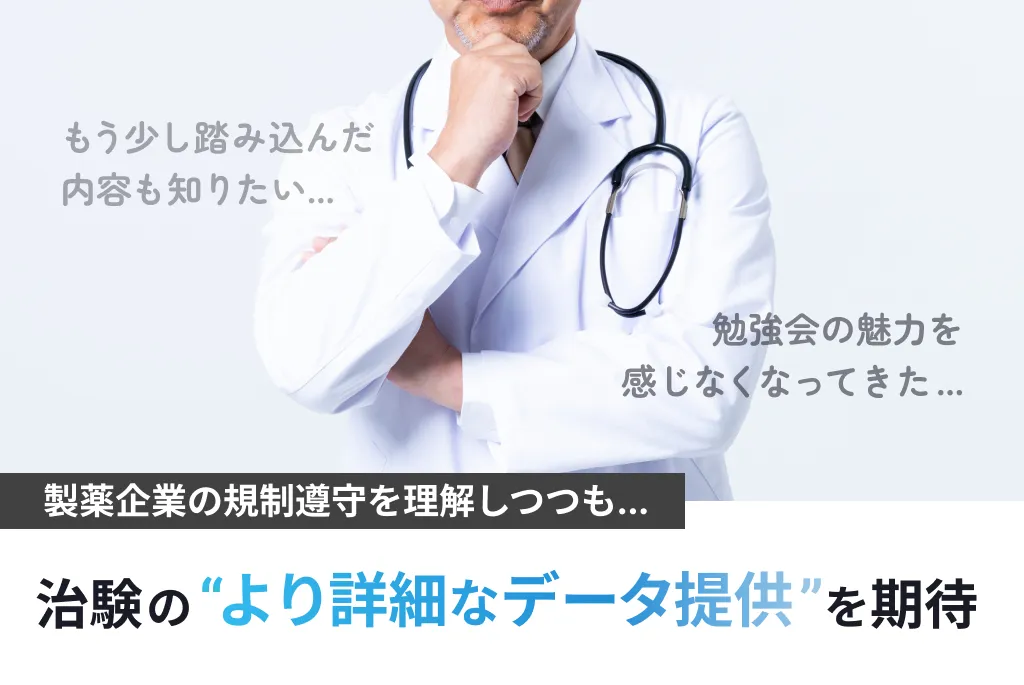
―― 先生は、製薬企業(もしくはヘルスケアテック)からさまざまな情報や資材、勉強会やウェビナーなどを提案されていると思いますが、もっとこういう情報が欲しい、こういう工夫やサポートが欲しい、などと思われていることはありますか?
最近は製薬企業さんも規制が厳しく、決められた規制の中でやってらっしゃるので、製薬企業さんの苦労は理解しています。
ただ、正直な事を言えば、製薬企業の勉強会に以前ほど魅力を感じなくなりつつあるのは事実です。新薬の情報は聞きたいですが、1回、2回ぐらい聞けば大体理解できますし、RWD(リアルワールドデータ)などの新情報が出れば聞きますが、その先はあまり聞かなくなる。なので、講演会で手術に関する内容などを聞ける方が、僕らにとってはよっぽど興味があることなんですよね。
手術に関して言えば、腹腔鏡手術の時代になってからは画像の質も良いので、開腹手術の時代とは全然違う良い情報源になっています。そういった画像を見て、今度はこれをやってみようかな。と思ったりしますし、時にはYouTubeなどの手術動画を視聴することもあります。
―― では、過去、先生を担当されていたMRやMSとの付き合いで、それぞれ時代や個人によって対応が変わる部分もあったかと思いますが、「この担当者なら信頼できる」と感じた担当者の方はいらっしゃいましたか?
以前は、非常に知識が豊富で、領域を超えた情報提供をしてくださるMRの方もいらっしゃいました。『自社製品とは直接関係ありませんが、こういった情報もあります』といった形で、幅広い知見を共有していただける方には信頼を寄せていましたね。
ただ、現在は規制が厳しくなり、情報提供の範囲が制限されているため、そうしたやり取りは難しくなっている印象です。
―― 昔はできたことも、今だと違反になるからできない。というのもあるのでしょうね。
そうですね。また、MSLになると持っている情報が異なるので、たまに面白い情報を持ってくる方もいらっしゃるのですが、自社の治験の細かいデータを持っているのかな? と思って聞いてみると、持っていなかったりして。
例えば、治験の主要解析結果は把握されていても、サブ解析やさらに詳細なデータについては把握されていないケースも見受けられます。せっかくMSLとしていらしていますので、もう少し踏み込んだ情報まで把握していただけるとありがたいと感じることがあります。
―― 今、先生がMRさんとお話する際にはどのくらいお話しされるのでしょうか。
通常は10分程度の面談が多いですが、内容が興味深い場合には15〜20分ほどお話しすることもあります。患者さんが増えていて、以前に比べて一人の患者さんに掛けられる時間が少なくなっており、長時間の面談を行うことは難しくなっています。
―― それは先生にとっても悩ましい所ですね。患者さんを診るのが何より最優先ですし、MRさんとも話さなくてはならないですし……。泌尿器科ならではの事情や患者さんとの関係性など、お話を深いところまでお聞きすることができ、色々と学ばせていただきました。ありがとうございました!
一旦、前半はここまでとなりますが、インタビューを受けて下さった榎本先生個人の経歴とともに、現在、診察や手術などをこなす中でどのように情報と付き合っているのかが感じ取れたのではないでしょうか。後半では、医療DXなどを含めたデジタル技術の期待やコミュニケーションについてのお話です。楽しみにお待ちください。
この記事の担当者

内海 篤人/Uchiumi Atsuto
職種:プロデューサー
入社年:2023年
経歴:Web業界(企画・ディレクター)→ゲーム業界(プランナー・カスタマサポート)→ヘルステック企業(カスタマーサクセス・事業責任者)に従事