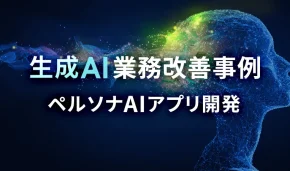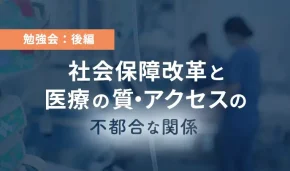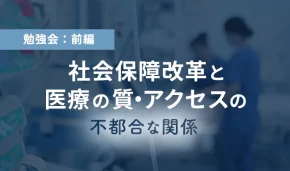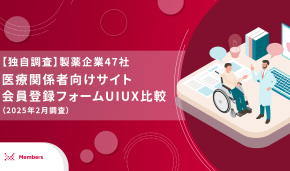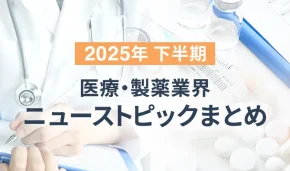ヘルスケア市場の最新トレンドを調査しました。厚生労働省が「保健医療2035提言書」を発表してから10年。2035年の“健康先進国”の実現に向けて、次々と新しいサービスが登場しています。本記事では、その具体的な事例を取り上げて紹介しています。ヘルスケア分野でのマーケティング戦略を考える際の参考に、ぜひご活用ください。
ヘルスケア業界にチャンス到来!「キュア」から「ケア」の時代へ
人生100年時代を迎え、高齢化や医療費の高騰など、社会全体がさまざまな課題に直面する中、日本のヘルスケア業界は本格的に転換期を迎えています。今回は、このヘルスケア市場で成功するための羅針盤として、現在注目されているトレンドに焦点を当てていきます。
また、ヘルスケアに関する行政の取り組みを振り返っていくと、2015年に厚生労働省は「保健医療2035提言書」を公表しています(※)。2035年の日本における保健医療政策のビジョンと道筋を示したものですが、提言書ではすでに「キュア中心からケア中心へ」ということが触れられていました。病気の治療をする「キュア中心」の時代から、生活の質を維持・向上させ、身体的のみならず精神的・社会的な意味も含めた健康を保つことを目指す「ケア中心」の時代へ転換することが記載されています。これは、言い換えればヘルスケア業界のマーケティング担当者にとって事業成長の鍵を握る巨大な機会です。特に、公的保険外のサービス市場は、まさに「次の波」として次の戦略のヒントになり得ます。
厚労省の提言から10年が経ち、ビジョンを示した2035年まで10年となった現在、ヘルスケア分野においてマーケティング担当者が把握するべき「次の波」とはどのようなものなのでしょうか。
今のニーズが分かる!「ヘルスケア最新トレンド5選」
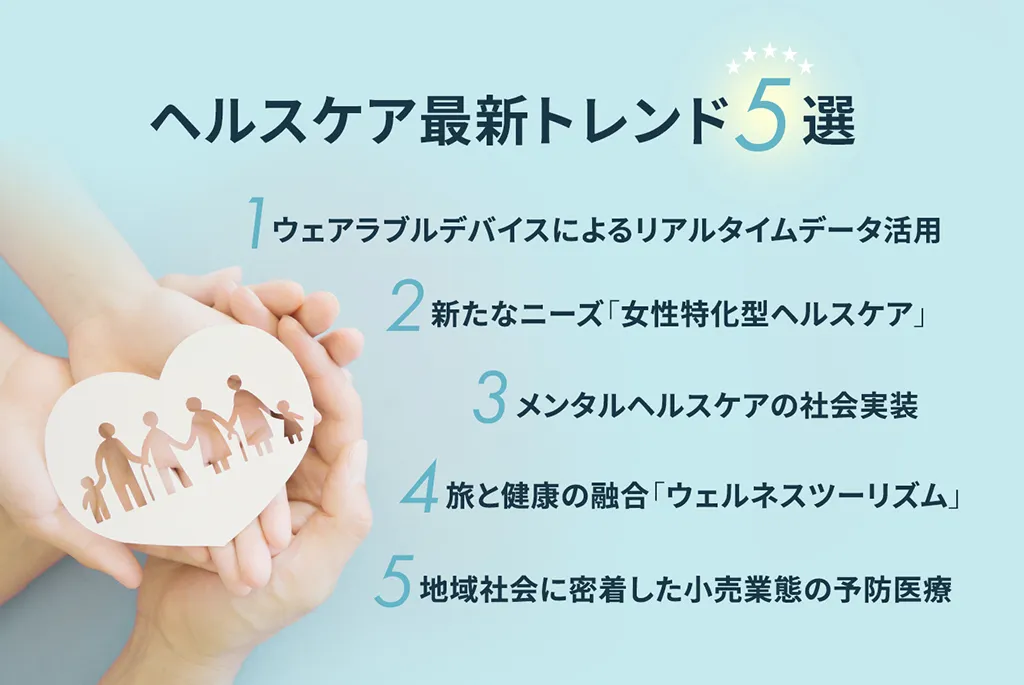
実際に、ヘルスケア業界の市場規模は大きく成長すると予測されています。2023年に経済産業省が発表した、新しい健康社会の実現に向けた「アクションプラン2023」によると、2020年には24兆円だった公的保険外のヘルスケア・介護市場は、2050年には約3倍の77兆円にまで拡大する見通しです(※)。この市場拡大を牽引するのは、OTC(市販薬)やサプリメント、ヘルスツーリズムなど、個人の「健康づくり」を支援するサービスとされています。
ここから、その潮流を感じられる5つのトレンドを掘り下げながらマーケティングの戦略立案に役立つヒントを解説していきます。今回ご紹介するものは、2025年現在の消費者行動や社会構造の変化を反映して登場したサービスの事例です。各トレンドの背景にある消費者ニーズ、技術的要因、そしてビジネスモデルにも目を向けながらチェックしていきましょう。
※参考:経済産業省 新しい健康社会の実現に向けた「アクションプラン2023」
【1.ウェアラブルデバイスによるリアルタイムデータ活用】
新しい形のパーソナルヘルスケアとして広まっている、スマートウォッチやスマートリングといったウェアラブルデバイス。その多くが心拍数、睡眠パターン、活動量などの生体データをリアルタイムで収集し、パーソナルなアドバイスを提供できる機能を搭載しています。これらが日常生活に浸透することによって、より健康的な行動を意識するようになり、個人の健康増進が促進されます。さらに、これらを企業が取り入れることによって、従業員の健康管理や生産性向上にも影響を与えるものになりつつあります。
【個人向け健康管理サービス】
■「Fitbit」:
Googleが提供するFitbitは、スマートウォッチやフィットネストラッカーを使って、日々の健康データを記録・分析し、生活をサポートするサービスです。歩数・心拍数・消費カロリー・睡眠・ストレスなどの生体データを記録・分析し、専用アプリと連携することで活動状況や健康指標をグラフで可視化できます。ユーザーはこれらから健康状態の変化を把握し、生活習慣の改善に役立てられます。さらに、有料版の「Fitbit Premium」では、詳細な睡眠スコアの内訳やストレス管理スコア、ガイド付きワークアウト、マインドフルネスセッション、健康レポートなどが利用可能。自分自身の健康状態をより深く理解したい方、科学的な根拠に基づいた改善提案を受けたい方に向けたサービスとなっています。
・Google LLC:「Fitbit」
■NEC「見守りソリューション」:
NECでは、ウェアラブルデバイスを活用したIoTソリューション(見守りソリューション)を開発しています。「見守りソリューション」の具体的な活用例は、ドライバーの運転中の疲労度(眠気)を検知・通知するものや、高齢者や要介護状態の方を対象に、睡眠の状態や体表温度・心拍などを計測して通常と異なる状態を検出、メールやアラートで通知するものがあります。特に高齢者の見守りは、離れて暮らす家族や介護者に異常を通知する仕組みとして、利用者の安心と家族の負担軽減に貢献するものです。これらは管理者や介護者の“見守り”を、場所や時間にとらわれず、バイタルデータを活用してサポートするサービスへと繋げている事例です。
・日本電気株式会社:「ウェアラブルデバイスを用いた安全・安心・便利な見守りサービス」
【企業向け健康管理サービス事例】
■「みまもりがじゅ丸®」:
NTTPCコミュニケーションズ株式会社が開発した、建設業、製造業、運送業など多くのフィールドワーク業界の人材の高齢化と人手不足に対応した企業向けの健康管理サービスです。従業員の脈拍や位置情報を専用のウェアラブル端末で取得し、体調の変化を計測・分析することで安全管理をサポートするもので、熱中症対策や過労などの体調の変化に早急に気付けます。重大事故の防止に貢献し、作業現場の人材の安全と健康管理の強化に欠かせないBtoB向けのヘルスケアソリューションです。
・NTTPCコミュニケーションズ株式会社:「みまもりがじゅ丸®」
■「SelfBase」:
株式会社テックドクターは、ウェアラブルデバイスなどから取得した日常の連続データを解析し、病気の有無や病状の変化、治療の効果などを客観的に示す指標、“デジタルバイオマーカー”を活用した医療・ヘルスケアDXを推進する企業です。「SelfBase」は、研究者や企業向けのクラウド型解析プラットフォームで、ウェアラブルデバイス(Fitbit、Apple Watchなど)から取得したデータを可視化し、医学的視点を反映したアルゴリズム解析やレポート生成などが可能です。そして、「SelfBase」で蓄積・解析されたデータを外部サービスに組み込むための開発基盤「Health Portal」も提供しており、製薬企業や保険会社のウェアラブルデータの活用と新たなヘルスケアサービス開発を技術的に支援しています。
・株式会社テックドクター:「SelfBase」「HealthPortal」
【2.新たなニーズ「女性特化型ヘルスケア」】
女性のライフステージ特有の健康課題(月経、妊活、更年期など)が、新たなビジネス領域として急速に拡大しています。特に潮流の中心にあるのが「フェムテック(Femtech)」です。テクノロジーの力で女性が自身の身体と健康に主体的に向き合うことを可能にし、これまで潜在化していたニーズを顕在化させています。従来のヘルスケアサービスでは、ピル処方や妊活タイミングのチェックなど、心理的・物理的な障壁を感じる方も多かったかもしれませんが、それらの障壁を下げるサービスが特に若い世代を中心に支持を広げています。
今回は、それらの中から、月経、妊活、更年期に対するアプローチ事例をご紹介します。
【月経・PMSへのアプローチ事例】
■「ルナルナ」:
生理・体調管理アプリ「ルナルナ」は、累計2100万DL(2024年8月時点)を突破した、フェムテックの先駆け的存在です。「ルナルナオンライン診療」はその延長線上にあるサービスで、スマホを通じて産婦人科医の診療を自宅や職場から受けられる仕組みです。特に低用量ピルの処方や継続的な服用支援に強みがあり、女性のライフスタイルに寄り添った医療アクセスを実現しているサービスです。
・株式会社エムティーアイ「ルナルナ」
■「スマルナ」:
アプリ上で医師による診療を受けられるオンライン診療プラットフォームです。お薬の相談・診察・処方まででき、低用量ピルやアフターピルを自宅に届けられるサービスです。他にも、メディカルダイエット・メディカルスキンケア・女性AGAがオンラインで診療可能となっており、時間的・心理的なハードルを大きく下げられます。
・株式会社ネクイノ「スマルナ」:
【妊活へのアプローチ事例】
■「ソフィ 妊活タイミングをチェックできるおりものシート」:
ショーツに装着するだけで、おりものに含まれる「妊活おしらせ物質」に反応し、妊娠しやすいタイミングを判定サインで知らせてくれます。排卵期を含む約6日間の妊活タイミングを、日常生活の中で自然に把握できるのが特徴で、生理管理アプリ「ソフィBe」と連携することで使用開始日や通知もサポートされ、妊活の心理的・物理的負担を軽減しながら自身の身体と向き合うきっかけ支援するフェムテック製品です。
・ユニ・チャーム株式会社「ソフィ 妊活タイミングをチェックできるおりものシート」
【更年期へのアプローチ事例】
■「Lumino」:
個人のセルフケア支援に特化し、プレ更年期〜更年期世代の女性を対象にしたフェムテックサービスです。月経記録を登録することで、現在の更年期ステージを推定することができます。また、出血や体調、気分の変化の記録をもとに、AIが分析した体調の振り返りレポートを月1回作成します。アプリ不要でLINEの友達登録だけで利用できます。
・株式会社menopeer「Lumino」
■「TRULY for Business」:
企業や自治体向けに提供されるフェムテックサービスで、男女の更年期症状やホルモン変化に関する理解を深めることを目的としています。LINEを活用したeラーニングや専門家によるチャット相談、動画・記事コンテンツを通じて従業員のヘルスリテラシーを向上でき、職場内の相互理解やコミュニケーション改善を促進し、仕事のパフォーマンス維持と女性活躍を支援する仕組みです。
・株式会社TRULY「TRULY for Business」
【3.メンタルヘルスケアの社会実装】
多くの業界で高齢化が進み人手が不足し、ストレス社会とも言われる現代ですが、それに比例してメンタルヘルスへの関心はかつてないほど高まっています。しかし、従来のカウンセリングや精神科医療を受けるには物理的・心理的なアクセス障壁が大きな課題でした。現在はこれらの課題を克服する手段として、デジタル技術を応用して心の健康を測定し、それを維持・増進するための介入プログラムを提供する技術や、それを用いたサービス(デジタルメンタルヘルス)が登場しています。また、AIチャットボットや自然言語処理(NLP)の技術の進歩によって、AIツールが人間のように共感的な対話をリアルタイムで実行できるようになったこともサービスの普及を後押ししているようです。このような技術の進歩によって、高い匿名性を保ったまま相談できる相手としてAIツールは若年層へ広がり、新しい形のケアとして定着しつつあります。
ここでは、スマホで手軽に利用できるメンタルヘルスアプリの具体例をいくつかご紹介します。
■「Awarefy」:
「Awarefy(アウェアファイ)」は、個人のメンタルヘルスを日常的に支えるAIメンタルパートナーアプリです。ユーザー自身がスマホアプリを通じて認知行動療法(CBT)やマインドフルネスの理論をベースに、日々の感情や思考を記録・整理することで自己理解と心の安定を支援します。AIキャラクター「ファイさん」との対話や感情日記、セルフケアワークを通じて、ストレスや不安への対処力を高めていきます。
・株式会社Awarefy「Awarefy」:
■「Emol」:
「Emol(エモル)」もAIチャット型のメンタルヘルスケアアプリで、アプリ内のAIキャラクター「ロク」との感情の記録と対話を通じ、ユーザー自身の心の状態を可視化・整理することを目的としています。インターネット認知行動療法(iCBT)に基づくプログラムで複数の大学や医療機関と共同研究を実施し、働く人のメンタルヘルスや特定の精神疾患を対象とした検証も行われており、学術的なアプローチをしている点が特徴です。
・emol株式会社「Emol」
■「muute」:
「muute(ミュート)」は、AIジャーナリング型メンタルヘルスケアアプリです。日々の思いや感情を自由に書き出すことでAIがその内容を分析し、客観的なフィードバックやインサイト(気付き)を届けてくれる仕組みです。毎日書くきっかけや、週・月単位で届く分析レポートによって、自分の感情の傾向や変化を振り返ることができ、日記でもSNSでも、カウンセリングでもない、自分と向き合うための静かで優しいデジタル空間を提供しています。
・ミッドナイトブレックファスト株式会社「muute」
【4.旅と健康の融合「ウェルネスツーリズム」】
単なる観光ではなく、旅を通じて“自分自身を整える”ことに重点を置いた新しい旅の形とされるのが「ウェルネスツーリズム」です。ヨガや瞑想、温泉、自然体験、ヘルシーな食事などを通じて、積極的に心身のバランスを整えることに焦点を当てるものとなり、地域の自然や文化を活かした体験は旅行者に活力を与え、地域経済の活性化にも貢献するとして注目されています。上記【3.メンタルヘルスケアの社会実装】で、現代社会のストレスの多さについて触れていますが、その対応策としてウェルネスツーリズムに注目が集まるのは自然なことかもしれません。また、経済産業省委託事業 調査協力「令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業(国内外での健康経営の普及促進に係る調査)報告書」でも、特にヘルスツーリズム市場は継続的に拡大することが想定されるとされており、2050年までに12.7兆円規模への拡大を目指す政府の方針とも連動し、その将来性は極めて有望といえます(※)。
以下の事例は、地域経済の活性化にもつながる、その地域ならではのユニークな資源をヘルスケアと融合させた取り組みです。
※参考: 経済産業省委託事業 調査協力「令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業(国内外での健康経営の普及促進に係る調査)報告書」
■和歌山「高野山」:
ユネスコ世界文化遺産である和歌山県の高野山は、心と体を整えるウェルネスツーリズムの聖地として国内外から注目を集めています。弘法大師・空海が開いた真言密教の聖地であり、静寂に包まれた空間で日常から離れた深い癒しと自己探求の時間を過ごせます。117寺院のうち52寺院は宿坊として一般の参拝客も宿泊でき、宿坊で精進料理を味わいながら、写経や瞑想など、仏教文化に触れる体験が可能です。また、「森林セラピー 体験ツアー」では心身の元気を取り戻す癒しのプログラムが実施されています。
・高野山真言宗 総本山金剛峯寺「高野山で体験」
■新潟県「松之山温泉」:
新潟県十日町市にある「松之山温泉」は、心身を整えるウェルネスツーリズムの体験地として人気スポットになっています。日本三大薬湯の一つに数えられるほど泉質の効能が高く、湯上がり後も体がぽかぽかと温まり続けるのが特徴です。地元食材を使った湯治豚や温泉玉子などの食体験も内側からの癒しを促し、その他、地元アートとのふれあいなども充実。単なる湯治を超えた自然・文化・食・静寂の融合を体験できます。
・新潟県十日町市「日本三大薬湯・松之山温泉のひみつ」
【5.地域社会に密着した小売業態の予防医療】
予防医療を地域社会に根付かせる取り組みとして、ドラッグストアやショッピングモールが進出しています。これらの場所は地域住民にとって日常的な買い物場所であり、医療機関や専門施設へ訪れるのに比較して、物理的・心理的なハードルが低い状態のまま、“ついでに健康管理”をする形の予防医療となります。また、この取り組みを成功させるには、消費者がドラッグストアやショッピングモールに訪れた際に健康行動を楽しく、無理なく継続させるための戦略が必要です。インセンティブやゲーミフィケーションの要素を取り入れ、単なる販売チャネルから「健康相談のハブ」に転換していきましょう。
小売業がどのように地域社会に密着した予防医療を実践しているか、いくつかの事例を紹介します。
■スギ薬局 健康相談:
スギ薬局では、地域の健康教育にも積極的に取り組んでいます。店舗を活用して地域住民への包括的な健康支援サービスを提供し、全国250店舗の店舗に在籍する管理栄養士が健康相談会や個別のカウンセリングを通じて、普段の食生活、運動習慣についてヒアリング。測定結果やカウンセリング内容から、食生活・生活週間で心掛ける点をアドバイスし、検査値を改善するための方法を提案していました。一部の店舗では、クリニックやフィットネスクラブと連携し、医療・運動・栄養の観点から総合的な健康支援も行い、地域住民の健康増進に貢献しています。
・株式会社スギ薬局:「健康相談」
■ウエルシア薬局 健康相談サービス:
ウエルシア薬局は、一部店舗に設置された専用ブースのPCを通じてオンラインで看護師と遠隔で健康相談できるサービスを開始しています。事前予約が不要で無料で利用できるため、地域住民のセルフメディケーションを支援し、身近な健康のハブとしての役割を強化しています。地域密着型の予防医療を推進する取り組みとして実施店舗を順次拡大していく予定です。
・ウエルシアホールディングス株式会社:「ドラッグストア店舗から看護師と相談ができる オンライン健康相談(遠隔健康医療相談)サービスの提供を開始」
■イオンモール「イオンモールウォーキング」:
広々としたショッピングモールを活用し、ユニークな取り組みを行っているのがイオンモールの「イオンモールウォーキング」です。元々、モール・ウォーキングとは、ショッピングモールをウォーキングコースとして活用するというアメリカで生まれた健康法で、イオンはこの取り組みを積極的に行い、全国142施設の館内にコースを設置しているとのこと。また、イオンモールアプリを利用することで、日々の歩数データや消費カロリーの管理ができるほか、ユーザーの歩数ランキングを表示するなど、楽しみながら健康づくりができます。天気や気候を気にせず、気軽に始められるため、幅広い世代に親しまれています。
・イオンモール株式会社「HEALTH & WELLNESS」
社会の動向から「次の波」のヒントを掴もう!
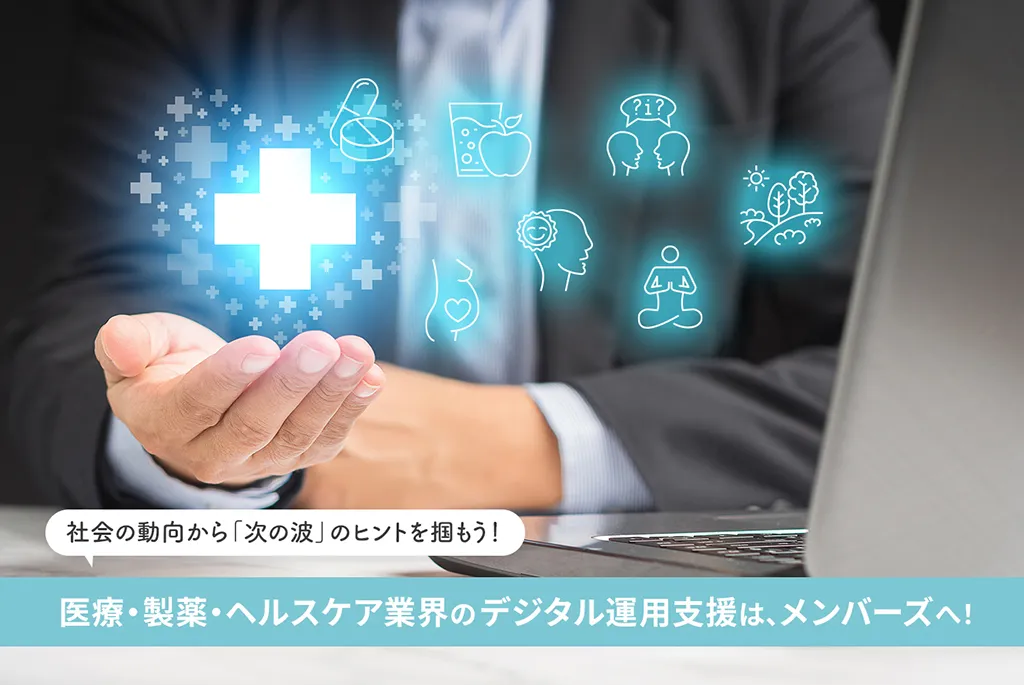
現代の消費者行動や社会構造の変化に伴い、さまざまなヘルスケア関連サービスが登場していることを感じ取っていただけたのではないでしょうか。注目されているサービスには、デジタル技術(データ解析、AI、アプリ)を駆使し、健康寿命の延伸を後押しするものや、高齢化社会に向けたもの、女性ニーズ、ストレス社会へ対応したものが中心となっていました。これらを参考に、時代の動きを常に感じ取りながら「次の波」を予測し、具体的なロードマップを策定しながら自社の強みを活かした画期的なサービス開発に繋げていきましょう。
メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。AI導入・活用全般のご相談、デジタル全般に関してスキルのある人材が足りないなど、お悩みをお持ち企業の方はお気軽にお問い合わせください。
この記事の担当者

丹羽 絢咲 / Niwa Ayana
職種: Webディレクター
入社年:2024年
経歴:2024年新卒入社後、Webinar運用案件→ イベント事務局運用案件に従事。