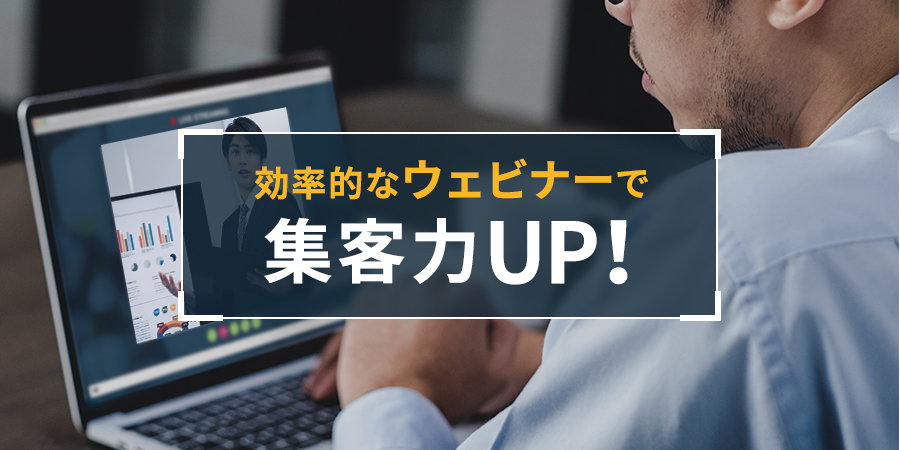みなさん、こんにちは。広報担当です。今回は、コロナ禍以降、医療業界でも活用されているウェビナーについて解説していきます。
製薬会社各社のMRが病院への訪問を規制され、医局説明会なども開催されにくい状況となった今、インターネットの映像配信システムを利用した勉強会や商品説明にビジネスチャンスが潜んでいます。医療従事者へ商品の魅力を伝える新たな手段としてウェビナー導入を考えている方は、ぜひご覧ください。
コロナ禍以降需要が高まり続けるウェビナー!
MRの数自体が減少して行く中でコロナ禍も重なり、MRの活動量が減少した製薬業界のマーケティング活動は大きな転換期へ差し掛かっています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)への対応が早い企業は既に医療関係者向けウェビナーを取り入れた活動に切り替えていますが、配信プラットフォームの予約も取れない場合にはZoom等の配信システムを使い、自分たちで開催を試みている製薬企業も多いかもしれません。しかし、映像配信専門ではないMRがウェビナーを開こうとしても手順があやふやになってしまったり、ナレッジもないため、かえって膨大な時間を費やすことになってしまった…というケースもあるのではないでしょうか。
今回は、そのような製薬会社の方々のウェビナー開催に役立てていただけるよう、製薬業界のデジタルマーケティングを支援している私たちのウェビナー運営サービスについて紹介していきます。
事前準備やアフターフォロー、ウェビナー開催は一大イベント!
とても便利なウェビナーですが、ウェビナーでイベントを成功させるためには事前準備やアフターフォローも大切です。配信システムを使えるようになること以外にも準備しておくべきことは多いため、自社で開催しようとしている方にとっては少々負担が大きいかもしれません。
以下がウェビナー開催に最低限必要な手順です。
【STEP1:企画】
・配信内容の決定
・開催日の決定
・登壇者、関係者のスケジュール調整
・ターゲット設定
・企画書作成
【SETP2:集客】
・参加者の登録用ページ作成
・ウェビナー参加用のURL送信
・(必要な場合のみ)集客用広告のプラン作成、配信
【STEP3:事前準備】
・リマインドメールの送付
・システムチェック
・リハーサル
・トラブル対応マニュアル作成
・(必要な場合のみ)アンケート作成
・(必要な場合のみ)司会者の手配
【STEP4:実施】
・登壇者(司会者)&参加者のアテンド、フォロー
【STEP5:事後】
・アンケート集計
・レポート作成
上記を一つひとつ明確にすることで必要な時間・人材・機材・システム利用費等がハッキリしてきます。これらを元に費用を見積もったり、スケジュールを逆算することができます。
ウェビナー活用でビジネスチャンスを無限に!

実際に開催すると実感できますが、ウェビナー運営は簡単な事ではありません。
しかし、それを上回るメリットがあるからこそ、ウェビナーがスタンダードなものになりつつある理由とも言えます。
なぜならば、ウェビナーはインターネットを経由したPR活動となるため、距離の制約を超えて対応できるお客さまが確実に増えてゆくからです。これまでは遠方だったためにセミナーに来ることができなかったお客さまも気軽に参加でき、ターゲット層を自由に広げることができます。病院の所在地や規模で展開していたビジネスが、ウェビナーという開催形式へと変更しただけで取引先を広げられるチャンスに変わります。
また、開催者側もウェビナーによって病院に出向く必要もなくなります。複数回のウェビナー開催があっても、時間、体力、コスト共に長期的な観点で考慮しても多くのメリットがあると言えるでしょう。
MMはウェビナーにまつわる作業がワンストップでOK!
私たちのウェビナーサポートにご相談したい方は、これまでのセミナーや医局説明会の内容と共に「企画している医局説明会を集客からサポートしてほしい」、「事務局運営を任せたい」、「開催までのマニュアルを制作して欲しい」など、ご要望をお伝えください。医療業界とデジタルマーケティングのプロが、みなさまのウェビナーを成功に導くために全面サポートをさせていただきます。
また、ワンストップのご依頼であれば、私たちがウェビナー運用の全般を担当し、みなさまには本来の業務に集中していただくことも可能になります。ぜひ、新たなセミナーや医局説明会の形としてウェビナーを使い、みなさまの商品をより便利な形式で多くの方へ広めていきましょう。
・ウェビナー運営についてのお問い合わせはこちらへ。
https://marke.members.co.jp/contact.service.html