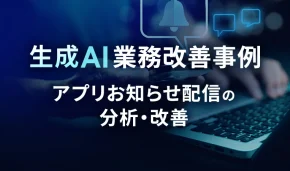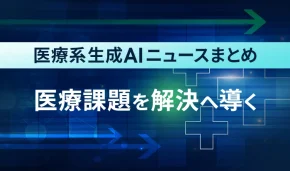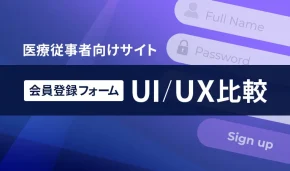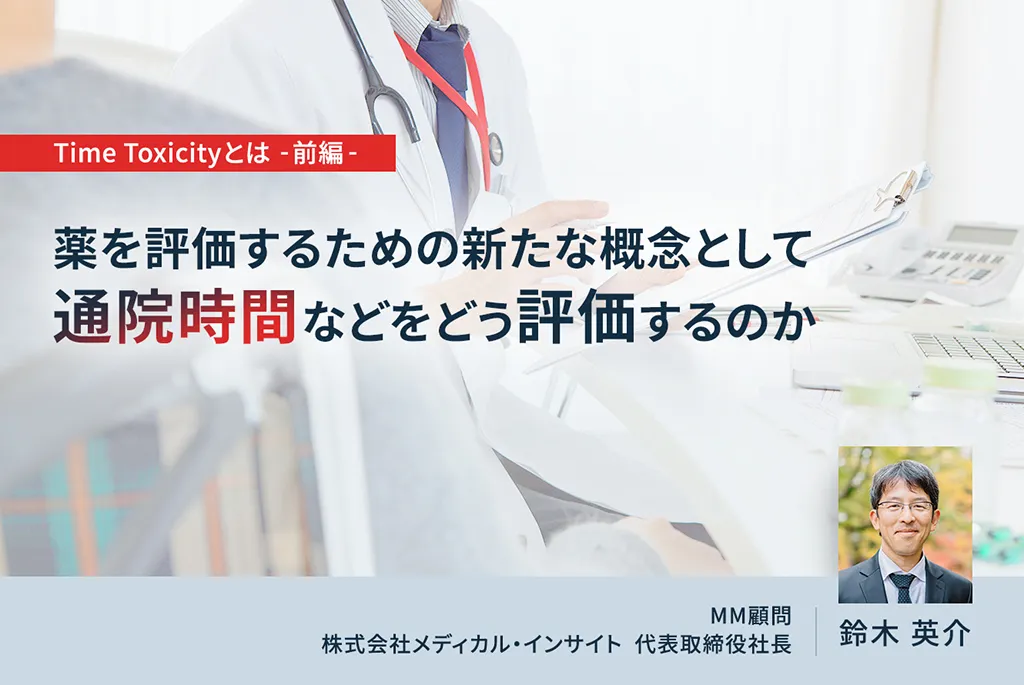
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。
テーマは、「Time Toxicity(時間毒性)」。薬を評価するための新たな概念として通院時間などをどう評価するのかという考え方です。高額な新薬や治療期間が長い病気などに関わる注目度の高いトピックです。ぜひ、ご覧ください。
勉強会の参加者

2018年中途入社
営業
佐塚さん

2023年中途入社
プロデューサー
内海さん

2023年新卒入社
Webディレクター
マルダンさん
新たな概念Time Toxicity(時間毒性)とは?
それでは鈴木さん、今日もよろしくお願いします!
出席者は僕と、内海さん、マルダンさんです
よろしくお願いします。
今日のテーマは『Time Toxicity』です。Time Toxicityを日本語に訳すと『時間毒性』ですね。今回はこのTime Toxicityについてお話をしていきます。これは僕も割と最近知った言葉で、7月に日本婦人科腫瘍学会に出席するために鹿児島へ行ったのですが、その時に腫瘍内科の先生が講演された中で出てきたコンセプトです。結構大事だと思ったので、こちらをテーマに選びました。
で、Time Toxicityのお話に入る前に、そもそも薬の評価というのをどうやってしているかについて考えてみましょう。例えば、使った薬が効いたどうか、どちらの薬が良かったとか……こういったことはどうやって評価してきたと思いますか?
薬を発売する前には臨床試験をしなければならないので、そこで効果があるかどうかを調べていると思います
そうですね。じゃあ、治験では具体的に何を評価していると思いますか?
その薬で病気が治ったかどうか、あとは副作用が有るか無いか……そういったことをみているのではないかなと
うん、そうですね。治験では薬が効いたかどうか、つまり感染症などの病気が治ったかとか、血圧や血糖値が下がったかとかの効果面を、まずみています。
そういった何らかの効果の数値に関する指標の中でも一番重要と考えられるものは主要評価項目と呼ばれていて、治験の成否を決める最重要の指標です。もう1つ大事なのは、マルダンさんが言ってくださった副作用についての評価で、安全性を確認します。高い確率で重篤な副作用が起きてしまう患者さんが出てしまうのであれば、効果があってもその薬は承認できませんので、まずは“効果”と“安全性”という側面を見ていくというのが大原則です。
一方、効果の良し悪しと安全性だけを見ていれば良いんですか? という話があって。
安全性にも関わる話なんですが、QOL(Quality Of Life)をきちんと評価した方が良いという話が近年になって出てきたんですね
薬の評価に反映されるべきQOLの視点
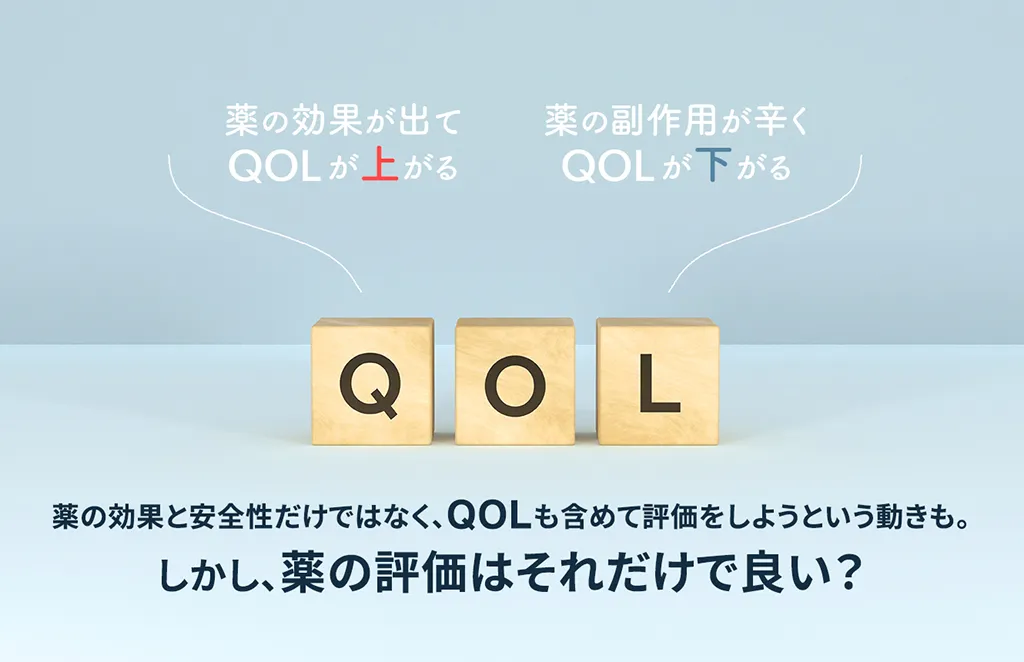
例えば、抗がん剤の副作用で吐き気があって苦しい、脱毛してしまって辛い……となったらQOLが下がるというのは想像できますよね? もちろん、抗がん剤自体の効果が出てQOLが上がるという側面もあると思いますけれど。そういったこともあって、近年は効果と安全性だけではなく、QOLも含めて評価をしようという動きがあります。でも、薬の評価ってそれだけで良いんだっけ、というところが今日のお話のポイントです。
ちなみに、こうしてみなさんと行っている勉強会でも『××Toxicity』というのを以前にお話しています。その中で、例えば、この薬を1ヶ月飲めば治りますと言われて、Aの薬は100万円、Bの薬は1万円だとしたらBの薬の方が良いですよね(笑)。こんな感じの話をしていたと思いますが、佐塚さん思い出せますか?
あぁ、ありましたね……! 薬価の話ですよね……。何だったかな……。
あっ、Financial Toxicity(経済毒性)の話でしたっけ
そうです、そうです。薬が生み出す価値や費用対効果のお話です。
ここで昨年の勉強会、『Financial Toxicity(経済毒性)の不都合な真実』(※)の中でもお話してきたことを少し思い出していただきたいのですが、なぜこの話を出したのかというと、最近の薬は高額なものばかりになっているという傾向があるからです。
昔はそこまで高い薬はなかったので、気にすることが無かったんです。でも、最近は抗がん剤で使われる分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤、リウマチなどの自己免疫疾患で使われるバイオ製剤のお薬、みんな高いんです。年間で使ったら数百万円、いや、1千万円単位になってしまうような。
でも、みなさんご存知のように日本は高額療養費制度があります。ですから患者さんが自己負担をしなければならない金額はキャップ(上限)があるのでそこまで深刻ではないのですが、アメリカのように皆保険制度を採用していない国だと、治療費に手が届かない人もいます。そこで、Financial Toxicityという話が出てきました
※以下の記事で詳しく解説しています。

【勉強会:前編】Financial Toxicity(経済毒性)の不都合な真実
2024.09.03
今回は、私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長の鈴木氏による勉強会レポートの前編です。 テーマは、治療に関連する経済的な負担がもたらす「Financial Toxicity(経済毒性)」です。 […]
薬にも「コスパ」や「タイパ」が求められる時代?!
考えてみれば当たり前のことで、同じような効果・安全性の期待できる2つのお薬の値段が、100万円と1万円なら、1万円の薬の方がいわゆる“コスパ”は断然良いですよね。だから、コストパフォーマンスは良い薬かどうかの判断の指標になるのは、間違いないということです。
さらに考えを深めると、コスパを考えるならタイパ(タイムパフォーマンス)だって考えなくてはならないよね、と(笑)。コストパフォーマンスは費用対効果なので、タイムパフォーマンスは時間対効果です。このタイムパフォーマンスがTime Toxicityの話と結びつくと思ってください
薬をタイパで考えるというのは斬新ですね
では、ここからが本題のTime Toxicityについての解説です。
例えば、何らかの病気になって治療を受ける時、何回も通院しなければならない治療もあるでしょうし、そうでもない治療もあります。それ以外にも、がんの治療でも点滴が必要で半日ずっとベッドで点滴を受けなければならない治療もあれば、経口摂取の抗がん剤で済む治療もある。
……こうして比べると治療に使う時間に結構違いがありますよね? なので、治療に伴って使う時間も評価に入れるべきなんじゃないのかということで、これがTime Toxicityの考え方です。
マルダンさん、どうですか? 納得できる考え方でしょうか? それとも何か疑問はありますか?
納得できました。私はTime Toxicityの考え方を聞いたことが無かったので
そうですね。僕も初めて聞いたのですが、確かに必要な考え方だなと思ったんですね。
で、もうちょっとTime Toxicityに対して考えを少し広げてみると、外来の通院とかでも、日本だと病院に行ってからすごく待たされることがあるじゃないですか。
みなさんはどうですか? 外来に行って長時間待たされた経験はないですか?
ありますよ。予約をしてその時間に受付をしても、呼ばれるのは30分後だったり……。もちろん、患者さんの状況にもよると思うので納得はしているのですが、病院にいる時間も治療の一部ですから
そうそう。でも、今の大病院の事情からすれば30分後に診察ができればかなり良い方です
うーん。まぁ、そうですよね(笑)
Time Toxicityを痛感させられた患者の言葉

例えば、がん患者さんなら2時間、3時間待ちは当たり前ですから。
マルダンさんはどうです? 通院のご経験はありますか?
日本の病院で通院した経験はあまりないです。でも、中国では同じでした。日本より待たされます。行列ができて、待ち時間は少なくても1時間ぐらいです
そうですよね。ある意味1回の通院で1日が潰れてしまうような感じじゃないですか。
ということは、治療をすることでムダになってしまう時間は通院でも出てきます。もう少し考えてみると、副作用が出た場合。こういった場合も再び通院しなければならないこともありますよね。なので、治療をしているがゆえに費やさなければならない時間が、どんどん増えていきます。こういった部分も含めて評価に入れないとおかしいよね、と。
僕が仲良くしていた、がん患者会のリーダーの方の言葉なのですけれど、『私たちは、がん治療をするために生きているわけではありません。生きていくために、がん治療をしているのです』ということを良く言われていましたが、まさにTime Toxicityに通じる言葉ですよね
病と闘う患者さんならではの言葉ですね。言葉に重みを感じます
そうなんです。でも、これはその言葉の通りで、治療のために生きているような状態になってしまったら、それは本末転倒になってしまうということなんですよね
―― 前半は一旦ここまでとなります。
後半では、引き続きTime Toxicity(時間毒性)について、治療に掛かる時間的なコストを評価する難しさや薬の利便性なども含め参加メンバーと質疑応答をしながら議論を深めていきます。続編も楽しみにお待ちください。

【勉強会:後編】薬を評価するための新たな概念「Time Toxicity(時間毒性)」とは?
2024.12.02
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。後編も引き続き「Time Toxicity(時間毒性)」をテーマとして、薬を評価するために治療の […]
この記事の担当者

佐塚 亮/Satsuka Ryo
職種:sales
入社年:2020年
経歴:大手スポーツメーカにて店舗sales,エリアマネージメント業務を担当。のちWEB制作会社にてWEBサイトの提案からディレクションをこなし、コンサルタントとしてサイト立ち上げ後の売上向上まで支援。その後2020年にメンバーズへ入社。主にクライアントからのヒアリング及び検証データを基に要件定義を行い、サイトの構築運用を実施。定常的に支援サポートを行う。クライアントはもちろんエンドユーザーの立場・視点に立ち、問題抽出から改善案の立案までを手がける