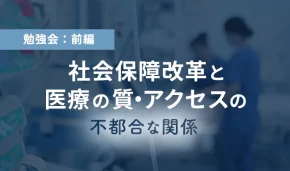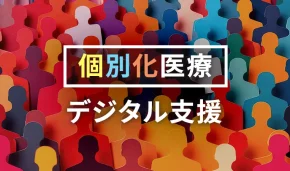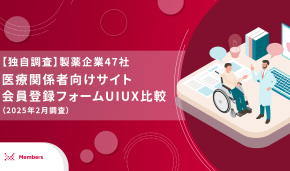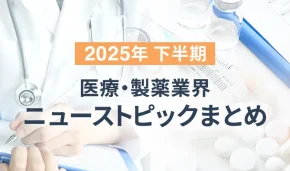2025年上半期の医療・製薬のニュースを独自視点でご紹介します。業界のDXはどのように発展し、医療現場ではどのような新テクノロジーが導入され始めているのでしょうか。電子カルテやAI活用といった話題を始め、制度整備の動きも含めて、最新の動向を振り返っていきます。今後の業界内のデジタルニーズをキャッチアップする際にもお役立てください。
DXは医療現場で本格始動!
2025年1月~6月の間で医療・製薬業界のデジタル活用に関するニュースを独自視点でピックアップしました。
DX関連では特に2024年に新設された「医療DX推進体制整備加算」による影響が拡大、これによって医療機関はデジタル化への対応を迫られています。マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の促進、電子処方箋および全国的な電子カルテ情報共有サービスの導入などがこれにあたりますが、国のDX戦略に沿った取り組みを行う医療機関に対して財政的なインセンティブが与えられるため、病院やクリニックの経営上、対応は無視できない要素です。
AI活用は医療現場で実践的なものになりつつあり、カルテ作成や事務作業といった負担の大きいワークフロー問題の解決へとシフトし始めているようです。一方、製薬業界でのAI活用は、研究開発とマーケティング活動の両方に革命をもたらし、マーケティングで得られたデータが研究を促進するという新たなフィードバックループを生み出している面もあるようです。そして、制度の整備が進む電子カルテの標準化の普及は、今後の医療提供体制の構造自体に大きな影響を与える動きであり、さらにこれらのデータを研究開発に活かすことで製薬企業の大きなチャンスとなるかもしれません。
以下からカテゴリー別のニュースを見ながら医療・製薬業界の動きを振り返りつつチェックしていきましょう。
2025年上半期の注目のニューストピック!
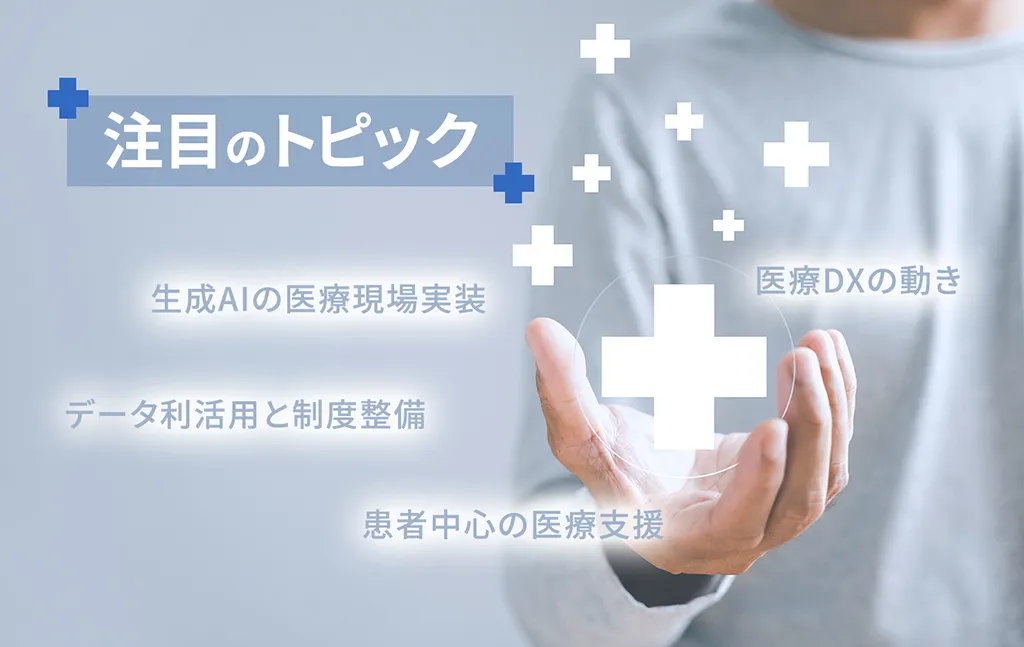
【生成AIの医療現場実装】
医療現場への生成AI導入や活用は進んでおり、業務効率と医療の質の向上が両立されつつあるようです。
企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社が慶應義塾大学病院と協業し、「退院サマリ作成支援AI」を臨床に導入しています。6月時点での発表では、試験導入を経て、5診療科の医師が活用を開始。医療現場での本格的な運用が始まっているとのこと。電子カルテから患者データを自動的に読み込み、10万文字を超える膨大な情報を短時間で要約できる機能や診療科ごとに最適化されたプロンプト設計が特徴となっており、医療業務の効率化と負担軽減に期待が集まっています。
同様に、藤田医科大学がクラウドインテグレーターの株式会社FIXERと共同で生成AIを用いた「退院時サマリー作成支援システム」を開発していました。2025年3月に行ったアンケート調査によると、このシステムによって医師の81%が「満足」、92%が「業務効率化につながった」としており、導入後3カ月の累計短縮時間は約1,000時間にも上るとのこと。
退院時サマリーのほかにも、兵庫医科大学では医療機関向け音声AIシステムの開発と提供を手掛ける 株式会社medimoが開発したシステム、「medimo(メディモ)」を導入。「medimo」は、音声認識と生成AIを活用した診療支援ツールであり、医療現場での会話を自動で文字起こしし、生成AIが要約文を作成することで電子カルテへの記録を効率化。特に医師による病状説明やインフォームドコンセントの記録支援に役立つものとして活用していました。
AI活用の現状から、従来の手作業が次々にシステム化されている様子がうかがえます。これらは医師の負担軽減と患者に向き合う時間の確保という課題をテクノロジーの導入で実現している好例です。
※参考:アルサーガパートナーズ株式会社【医療現場で本格導入】慶應義塾大学病院とアルサーガパートナーズ、 生成AIを活用した「退院サマリ作成支援AI」システムを共同開発
※参考:藤田医科大学:医師の92%が業務効率化につながったと回答 生成AIを活用した「退院時サマリー作成支援システム」が実用化
※参考:兵庫医科大学:病状説明をAIが自動要約し電子カルテに記録~大学病院で全国初の導入~
【データ利活用と制度整備】
データ活用と制度整備が一体的に進み、医療DXの基盤がより強固になり始めています。
政府の「医療DX令和ビジョン2030」は、“遅くとも2030年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す”という目標に向かって進み続けており、上期は政府主導の標準化されたクラウドベース電子カルテシステムの開発と、医療データインフラの法的枠組みの整備が着実に進展しています。現在多くの施設で使われているオンプレミス型・カスタマイズ型電子カルテから、クラウドネイティブ型へのシステム変更に負荷は掛かるものの、この導入方式は後々の保守や情報連携のしやすさ、コスト抑制などの利点もあります。このような電子処方箋や電子カルテの標準化は、行政・医療機関・企業の枠を超えたデータ利活用の未来にもつながります。
電子カルテ標準化に密接に連携する「電子カルテ情報共有サービス」は、個別の電子カルテをつなぎ、全国の医療機関や薬局で患者情報を共有できる仕組みで、厚労省が推進する「全国医療情報プラットフォーム」の中核機能のひとつです。4月から本格稼働が開始され、全国10地域でモデル事業が展開中ですが、導入率はまだ低く、特に中小病院や診療所への普及が課題とされています。
また、3月にアストラゼネカは「認定仮名加工医療情報利用事業者」として国内初認定を取得し、実臨床データの利活用に大きな前進がみられました。これまでは、個人情報保護の観点から、企業単独での取得・利用が制限されていたため、匿名加工医療情報やリアルワールドデータ(RWD)を外部の認定事業者から購入・委託して活用していましたが、この認定によって特異的な検査値や病名等のデータが含まれる仮名加工医療情報を利用できるようになりました。同一対象患者に関する詳細で継続的なデータの収集だけでなく、目的にあったRWDの構築、薬事承認のためのデータ利用が可能となるとのこと。こちらも医薬品開発に貢献する取り組みです。
※参考:厚生労働省:第7回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム資料について
※参考:厚生労働省:電子カルテ情報共有サービス
※参考:PHARMACY DX NEWS:医療DX推進体制整備加算の最後の経過措置~電子カルテ情報共有サービス~
※参考:アストラゼネカ株式会社:アストラゼネカ、次世代医療基盤法に基づく 日本初となる「認定仮名加工医療情報利用事業者」認定を取得
【患者中心の医療支援】
AIとデジタルを活用し、“見落とされがちな患者”にアプローチする取り組みが進んでいます。
医療は治療の部分に注目しがちですが、その前後の手続きや早期診断も医療を支える大切な仕組みです。
順天堂大学では、患者に最適な転院先を推薦するマッチングシステム「Patient Flow Management(PFM)AIマッチングシステム」の構築を開始していました。これは、電子カルテ・データと生成AIを活用し、患者さんに最適な転院先をより効率的に提供するというもの。患者さんに寄り添ったサービスであるとともに、医療機関としても退院調整に係る業務を20%以上効率化できると試算されており、患者と医療者の双方にメリットがあるサービスです。
また、 未診断患者の早期受診を促すサービスとして、ヘルステック・スタートアップ企業のUbie株式会社とサノフィ株式会社は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の早期受診を促すための啓発施策を開始していました。COPD は認知度の低さや初期症状が出にくい、または進行しても自覚しづらいという課題があるため、症状検索サービスを活用した患者さんへCOPD についての詳細なコンテンツを表示させることで疾患啓発による適切な受診行動の支援をするものです。
これは、デジタルサービスを通して疾患に気づける時代となった証であり、新たなサービスの形式が医療機関と患者をつなぐ重要なツールとなりつつあることを示しています。
※参考:順天堂医院:順天堂大学、患者一人ひとりに最適な医療機関への転院を支援する「PFM AIマッチングシステム」の構築および運用に向けた取り組みを開始
※ 参考:Ubie 株式会社:Ubie とサノフィ、COPD 啓発施策を開始
【医療DXの動き】
2025年の「骨太の方針」では、医療や介護分野のDXが重点項目として掲げられ、電子カルテやPHR(Personal Health Record:個人の健康・医療・介護などのデータ)の普及、医療職の待遇改善が明文化されています。こうした政策の根底には、医療現場の構造的課題に対するテクノロジーの活用という明確な方向性があります。さらに、その実現に向け、民間企業との連携が加速しています。
6月に、総合医療情報システム開発・販売などを手掛けるソフトマックス株式会社は、健康・医療データおよびそれらに関する情報を扱うシステムの企画、開発を行う株式会社HEMILLIONSおよびソフトバンク株式会社と医療分野における生成AI(人工知能)技術の社会実装に向けた共同検討について基本合意書を締結しました。この取り組みでは、クラウド型電子カルテと連携した医療文書作成支援AIの開発・PoC(概念実証)を通じて、医師の業務負担軽減と医療の質向上を両立させることを目指しています。特に、LLM(大規模言語モデル)を活用した医療文書の自動生成は、医師の時間外労働削減や働き方改革の実現に直結する技術として期待されています。
医療DXの推進は、制度と技術、行政と企業の連動で加速することを、これらの動きから感じ取ることができます。
※参考:週刊GemMed:骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う
※参考:PR TIMES:HEMILLIONSおよびソフトバンクと医療分野における生成AI技術の社会実装に向けて共同検討を開始
今後のニーズはどう変化する?
これらのニュースの潮流から見えるように、生成AIをはじめとしたデジタル技術は現場に浸透し、活用できている病院やクリニックなどは医療の質の向上に繋げています。すでに導入させているものの、現場で浸透しにくい状況が続いている医療施設や企業の今後の課題は、“点”で導入されてきたデジタル技術を、いかに“面”や“線”へと拡張させ、医療施設や企業全体で使われるツールとして実用できるかどうかに掛かっています。
3月に結果が発表されたCB news社主催の「第1回 病院DXアワード 2025」は、病院のDXに関する製品・サービス等を提供する企業から特に優れたものを表彰しています。大賞受賞企業はヘルステック・スタートアップ企業、kanata株式会社の「kanaVo」で、診察中の会話を約10秒でカルテ形式にするというサービスでした。その他の優秀賞受賞企業のサービスは、Dr.JOY株式会社の予約など電話対応の負担を軽減する「AI電話サービス」や、TOPPANエッジ株式会社の電子カルテと連携し、調剤状況をリアルタイムに確認する「RFIDを活用した病棟向け調剤工程管理システム」などでした。どれも病院DXを推進するサービスであり、選ばれた企業のサービスからも感じ取れるように、いま求められているのは、【いかに現場に浸透し、使いやすいデジタルツールであるか】という点です。
生成AIの医療現場への実装が進み、その中で生成AIによる文書作成支援やデータ連携も進んでいるため、今後は異なるプラットフォーム間の運用性や、PHRを中核とした情報統合基盤の整備が求められていくことが考えられます。これからの医療・製薬業界には、単なる“ツール導入”を越え、医療提供体制全体の構造改革に寄与するものであることが問われていくのではないでしょうか。
すでにDXが医療・製薬の現場が支え始めている!

カンパニー設立の2019年よりDXについてのご支援や発信を続けてきましたが、DXによる効果を医療・製薬の業務で実感できる段階まで到達したことが感じられました。
そして、マイナ保険証やオンライン診療など、私たちの医療を取り巻く環境も絶えず変化しています。今後はその仕組みの中でデータが取得・蓄積され、医療情報や製薬開発に役立てられていくという好循環に繋げていけるよう、生成AIの活用やDXに関するご支援を続けていきます。
メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。デジタルに関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。
この記事の担当者

内海 篤人/Uchiumi Atsuto
職種:プロデューサー
入社年:2023年
経歴:Web業界(企画・ディレクター)→ゲーム業界(プランナー・カスタマサポート)→ヘルステック企業(カスタマーサクセス・事業責任者)に従事