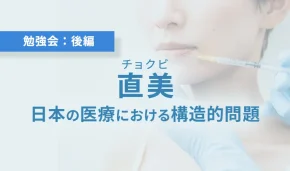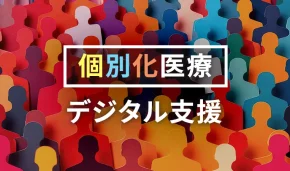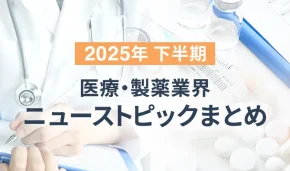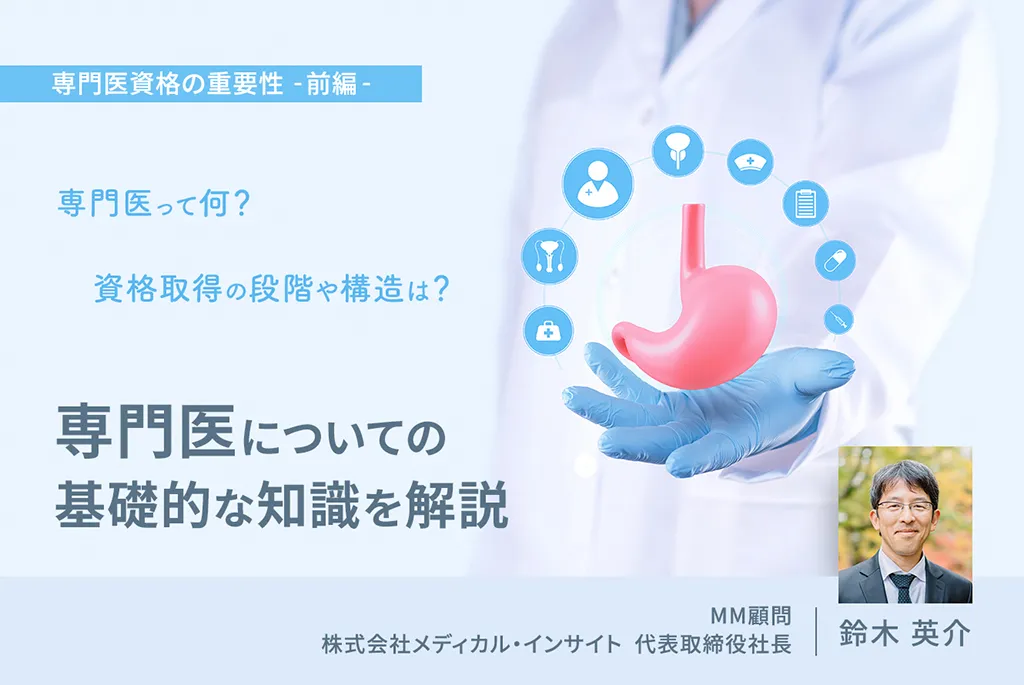
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。今回のテーマは「専門医資格の重要性」です。前半はどのように研修医が専門医の資格を取得していくのか、資格取得の段階や構造なども含めて説明していきます。ぜひ、ご覧ください。
勉強会の参加者

2018年中途入社
営業
佐塚さん

2017年中途入社
Webディレクター
嶋田さん

2008年新卒入社
Webディレクター
安原さん

2023年中途入社
プロデューサー
内海さん

2024年新卒入社
Webディレクター
及川さん

2012年中途入社
Webディレクター
大畑さん

2024年新卒入社
UIUXデザイナー
田川さん

2024年新卒入社
Webディレクター
森田さん

2023年新卒入社
Webディレクター
横山さん

2023年新卒入社
Webディレクター
中村さん
そもそも“専門医”とは、どんなもの?
それでは、よろしくお願いします。
出席者は、嶋田さん、安原さん、内海さん、及川さん、大畑さん、田川さん、森田さん、横山さん、中村さん、僕です
よろしくお願いします。
今日は『専門医資格の重要性』というテーマです。みなさん、専門医資格について知ってらっしゃる方はどれくらいいますか?
……あれ? いないですか(笑)
専門領域のお医者さんは、みなさん専門医かと思っていましたが……
じゃあ、何となく聞いたことがある、くらいの方はどうでしょう?
……ちょこちょこと手を挙げている方がいらっしゃいますね。
では、初めて聞いたという方は
……嶋田さん、及川さん、結構いらっしゃいますね。
まぁ、普通に生活をしているだけなら誰でも『専門医って何?』っていう感じだと思います。でも、この業界で仕事をしていくならば知っておいた方が良い内容なので、詳しく解説してきますね
専門医の資格を持たないお医者さんもいる?
みなさんも街を歩いていると皮膚科だったり眼科だったり、そういうクリニックを見かけますよね。では、ああいった○○眼科クリニック、というようなところにいるお医者さんは、専門医の資格を持っていると思いますか?
……では、初めて聞いたという及川さん、どうでしょう?
う~ん、どうでしょう……持っていないんじゃないでしょうか?
おぉ! 持っていない説、大胆に来ましたね
白内障とか、近眼とか、そういう症状に合わせた専門医があるのでは……?
良い視点ですね!
では、もう1人ぐらいに聞いてみたいですね。大畑さん、どうでしょう?
えっと……眼科医の中でも、専門医と、専門医じゃない眼科がいると思います。そういう“資格”があるからこそ、そう思いますね
大畑さん、大正解です。素晴らしい!
まず、眼科の先生には眼科医の専門資格があるんですね。眼科に対して、専門的な知識を持って診療にあたっている先生ということ。普通に考えたら、『眼科なんだから、眼科専門医の資格を持っていて当たり前だろう』と思いたいんですけど、大畑さんが話されたように、実はそうではなかったりするんです。眼科専門医の資格を持っていない方も、眼科を名乗っていたりします。
で、及川さんの言う、細かい単位での専門医という所で言えば正直なところ眼科ではないのですが、他の科ではあります。なので、それは後でお話させていただきますね。まずは、眼科医と名乗っていても専門医とそうでない人がいるというお話ですが、これは結構大事なところです。
じゃあ、これってどうして専門医の資格を持っていないのに、眼科だと名乗れると思いますか? ……田川さん、どうでしょう
医師免許を持っていたら問題ないのかなと……
鋭いですね!
今日の参加者の方は発言が鋭い(笑)。その通りです。
医師免許を持っていたら、何科を名乗ってもOKなんですよ。日本では自由標榜制を取っているので、これが世にも不思議な制度なんですが、診療科は何を名乗っても良いということになります。僕の知り合いでもいるんですけど、それまで精神科でトレーニングをしていたのに、ある日突然眼科のクリニックを建ててしまったという人もいて。だから、実際にそういうことができるんですね。
とはいえ、眼科とか皮膚科とか、専門性が必要そうな診療科の先生の中には1割もいないと思いますけど、専門医の資格がない方はいます。
あっ、嶋田さん。何でしょう?
すみません。ちょっと横道にそれますが、これって食品衛生責任者を置いてさえおけば、調理師免許を持っていなくてもどんな飲食店でも出せちゃうようなイメージかなと
そうですね。どちらかと言えば、中華料理しか修行していないのに、いきなりフレンチのお店を出しちゃう感じでしょうか(笑)。なので、医師免許を持ってさえいれば、それまでトレーニングをしていなかった、違う診療科を突然名乗ってもOKなんです。
逆に言えば、患者側がその医師が専門医の資格を持っているかをチェックするのは大事ということです。一昔前に眼科でレーシック手術が流行りましたが、眼科専門医資格を持っていないお医者さんが手を出して問題を起こして……なんていうこともありました。だから、やはり専門医資格というのはとても大事な資格なんです。ということがまずはお伝えしたい事です
専門医を認定する「学会」の役割とは?
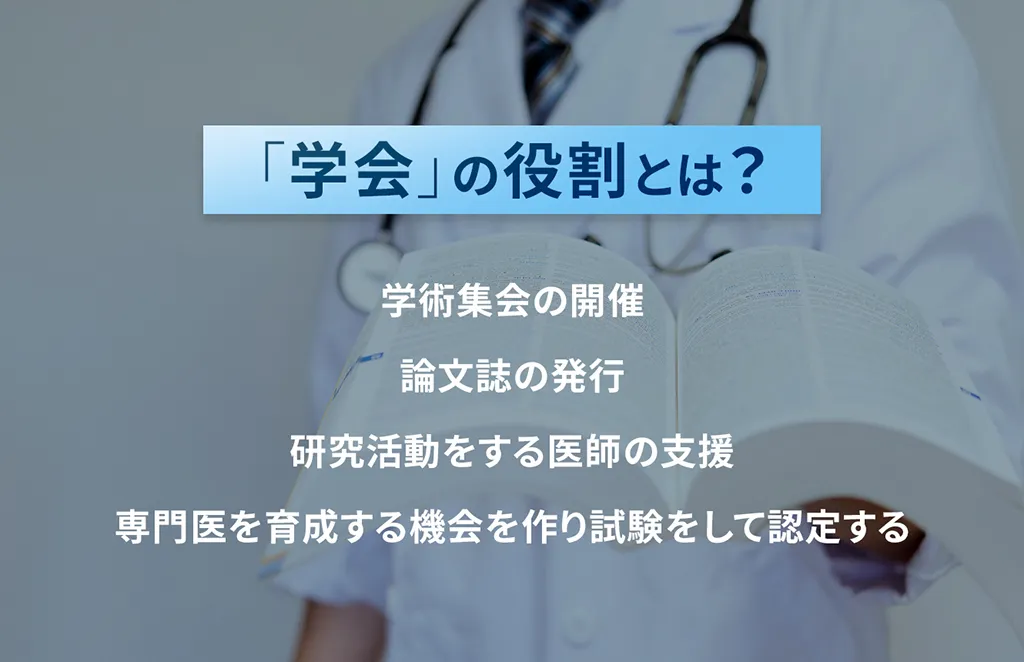
では、誰がどうやって『あなたは専門医です』と決めていると思いますか?勝手に名乗るわけにはいかないので、誰かが認定しなくちゃいけないですよね。
……森田さん、どうでしょう
そういう……協会みたいなところでしょうか?
おぉ、良いですね!
そう、これは“学会”ですね。いわゆる医療系の学会がやることです。
で、医療系の学会の役割というのは大きく4つあって。
1つは、学術集会の開催というものですね。色んな先生たちが研究結果を発表したり、講義をしたり、というものを年に1回ぐらいやります。
2つ目が、論文誌の発行。先生たちの研究結果を論文として発表する学術雑誌の発行です。
3つ目は、色々な研究活動をする先生たちの支援。グラントですね。資金をどこからか調達して研究を支援したり、場合によっては海外に派遣する資金や機会を提供したり。
最後の4つ目が、専門医の育成に関わる部分。専門医を育成する機会を作ることと、実際に専門医の試験をして認定する。そういった重要な役割を持っています。例えば、皮膚科専門医なら日本皮膚科学会が専門医を認定していますし、眼科なら日本眼科学会が認定しています。
では次に、先ほど、皮膚科と眼科を出しましたけど、専門医にはどんな専門医があるか想像してもらいたいと思います。他に何がありそうな気がしますか?
……じゃあ、安原さん
リウマチ科とか……
おぉ~、なかなか専門的なところから入りましたね!
じゃあ、他の方……横山さん、どうです?
婦人科、放射線科とか……
みなさん、ちょっと尖ったところから来ますね(笑)
精神科とかですかね
うん、精神科もありますね。他はどうですか?
みんなすごい角度から入ってきていますが(笑)、もっと街中で見るようなものだったら、泌尿器科とか耳鼻科とかがありますよね
そうそう、そうです。僕ももっと耳慣れた科から来ると思ったのでびっくりしたんですけど(笑)、みなさん素晴らしい回答です。ありがとうございました。
いま挙げていただいたもので、リウマチ科はこの後、説明するお話になりますが、他の科は専門医の資格があります。で、専門医の資格というのは実は二階建てになっていると良く言われるんですね
内科・外科の専門医資格の構造はちょっと複雑
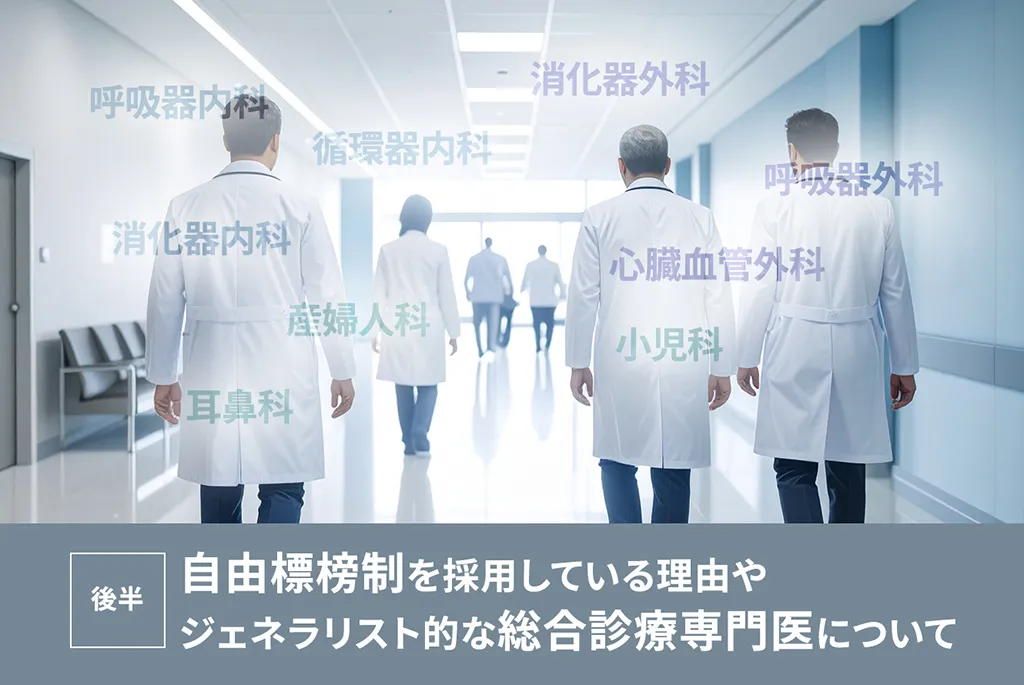
例えば、内科ってありますよね。で、内科というのは幅広くて、その中でもさらに細かく分かれているんです。ここで先ほど及川さんが言っていた、科の中でも細かく別れるのでは? というお話に繋がります。
眼科はそれ以上細かく分かれないのですが、内科は細かく分かれるんですね。あともう1つ、細かく分かれるのが外科。内科と外科は、みなさん良く耳にする科だと思いますが、この2つの科はあまりにも広すぎるので、内科と外科の専門医資格というのはそれぞれあるんですが、ある意味、取って当たり前の専門医資格なんですね。なので、そこから先がちょっと細かく分かれるんです。
では、内科が細かく分かれるなら、どんな科がありそうでしょう?
……中村さん、どうですか?
呼吸器内科ぐらいしか思いつきませんが……
そうですね。素晴らしい!
呼吸器内科は間違いなくありますね。ここでヒントを言うならば……部位です。どの器官なのかで変わる。呼吸器内科は、気管支とか、肺とか、そこで発生した病気を内科の中で対応する先生たち、ということですね。
田川さん、他には何かありますか?
内臓なら……心臓とか?
心臓、良いですね。でも、心臓内科とは言わないんですね。これは循環器内科。あとは、みなさんも良く調子が悪くなりそうなお腹系とか。
あっ、森田さんがコメントしてくれていますね。そう、消化器内科です。こういった形で内科の中でも専門分野がさらに分かれていて、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科などがあります。他にも、血液内科とか、脳神経内科とかもあります。
で、最初に安原さんから出してもらっていたリウマチ科。これは、内科系の専門医なんですね。膠原病リウマチ内科という、内科系の専門医資格があったりします。そんな形で内科は二階建てになっています。これは外科も同じです。一階に外科があって、二階に消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科というような形です。
で、外科と内科の話をしましたが、他にも診療科というのは色々ありますよね。耳鼻科、泌尿器科、精神科、産婦人科、整形外科、放射線科、小児科、麻酔科なんていうのもあります。実はそういう一階建ての診療科の部分を“基本領域”という風に呼んでいますが、この基本領域の診療科だけでも19ぐらいあります。そこへ二階建て部分を含めると、29ぐらいあるといわれていますね。
で、日本専門医機構という専門医制度を統括する団体のようなものがありまして、彼らが専門医制度は二階建てであるということを言い出して、現状はこのような形になっています。ここまでで何か質問はありますか?
そのお医者さんが専門医資格を持っているかどうか、それを判断するのはどうするのかな、と。昨日まで別の科で診療をしていたら……と思うと怖いなと思いまして(笑)
良い質問ですね!
安心してください、判断する方法はあります(笑)。これはWebサイトを持っているクリニックであれば、院長先生のプロフィールなどを載せているところが多いので、そこで○○の専門医資格がある、と確認すれば良いんですね。
ただ、Webサイトを持っていないクリニックというのもあって。そういう場合は先ほどお伝えしたように、専門医資格というのは学会が認定するものなんです。眼科だったら、日本眼科学会のサイトを見ると専門医のリストがあります。日本全国で専門医資格を持っている先生がどの医療機関に所属しているというのが出ています。
でも、いちいち調べるのは面倒臭いですよね
そうですね。今、聞いていて面倒だなと思っちゃいました(笑)。こっちから調べなくても、クリニックに行ったら看板とか、ネームプレートとかに出してもらいたいです
看板に出しているケースもありますけどね
そこれって、載せなくちゃいけないという義務はないんでしょうか?
それが、ないんですよね。そこがおかしなところで。
とはいえ、専門医資格を持っているお医者さんなら、普通は書きますけれどね。大事だと思っているからこそ取得するわけなので。
でも、例えば、皮膚科とかだと皮膚科の専門医資格は持っていないけど、形成外科の専門医資格なら持っているとか、近い科の専門医資格を持っている先生が皮膚科を名乗っちゃうという場合はありますね
―― 前半は、そもそも専門医とは? という、基礎的な知識となる部分について解説しました。後半は、自由標榜制を採用している理由やジェネラリスト的な総合診療専門医について解説していきます。続きも楽しみにお待ちください。
後編はこちら
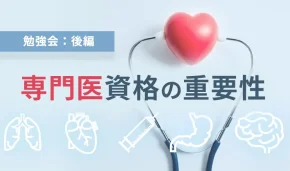
【勉強会:後編】知っていますか?“専門医資格”の重要性
2025.09.16
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。テーマは前半に引き続き「専門医資格の重要性」です。後半は、自由標榜制を採用している理由やジェネラ […]
この記事の担当者

佐塚 亮/Satsuka Ryo
職種:sales
入社年:2020年
経歴:大手スポーツメーカにて店舗sales,エリアマネージメント業務を担当。のちWEB制作会社にてWEBサイトの提案からディレクションをこなし、コンサルタントとしてサイト立ち上げ後の売上向上まで支援。その後2020年にメンバーズへ入社。主にクライアントからのヒアリング及び検証データを基に要件定義を行い、サイトの構築運用を実施。定常的に支援サポートを行う。クライアントはもちろんエンドユーザーの立場・視点に立ち、問題抽出から改善案の立案までを手がける