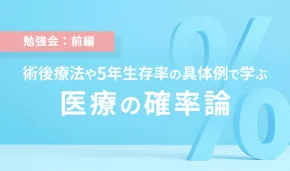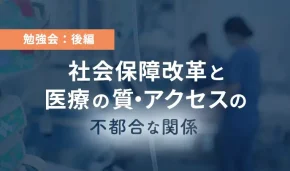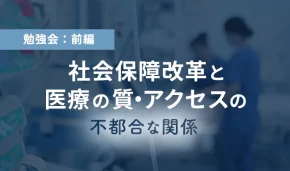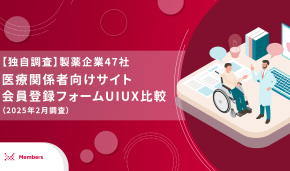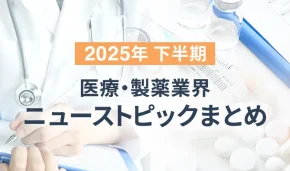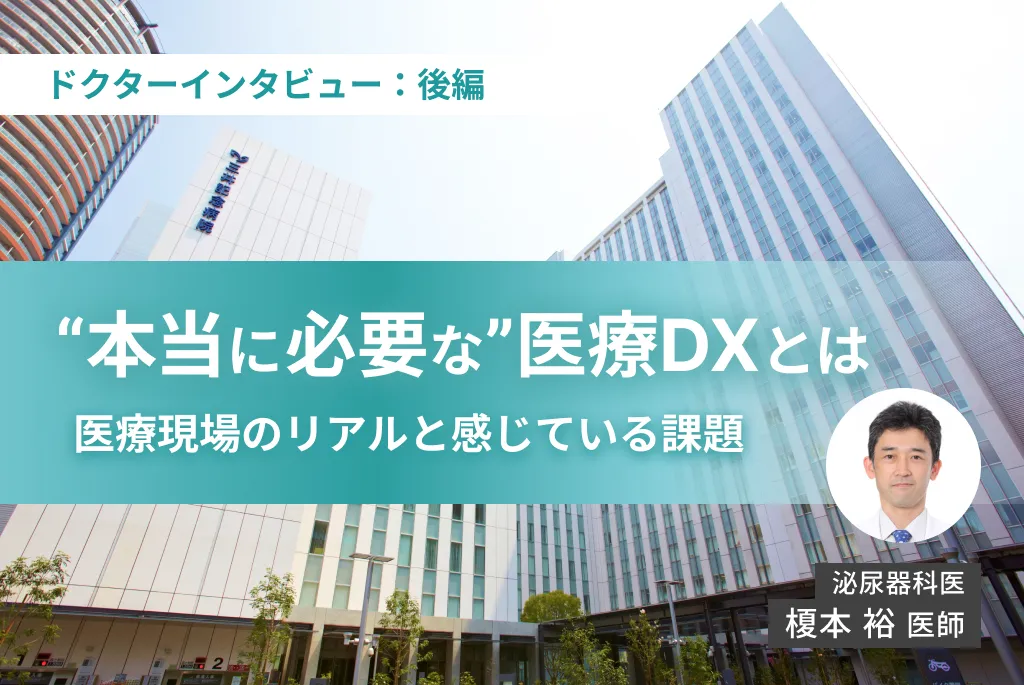
“リアルな医療現場の声を伝える”ドクターインタビューの続編です。お答えいただいたのは、前編に引き続き、社会福祉法人 三井記念病院 泌尿器科・地域医療部部長、がん診療センター副部長 榎本 裕 医師です。後編は、今後、AIなどを含めたデジタルテクノロジーは医療のどの領域で必要とされているのか、デジタル技術への期待やコミュニケーションについてのお話です。デジタルに関する戦略立案のヒントを含んだ内容となっています。ぜひご覧ください。
※前半の記事はコチラ
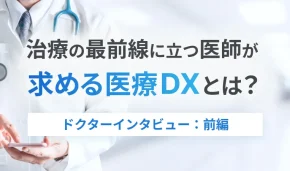
【ドクターインタビュー:前編】治療の最前線に立つ医師が求める医療DXとは?
2025.11.05
今回は、“リアルな医療現場の声を伝える”ドクターインタビューです。お答えいただいたのは、社会福祉法人 三井記念病院 泌尿器科・地域医療部部長、がん診療センター副部長 榎本 裕 医師です。医療の最前線で治療を行いながら日々 […]
推し進められる医療DXと医療現場の現実の差とは?
―― 後半もよろしくお願いします。
前半では、榎本先生が担当する泌尿器科の詳しいお話や情報との付き合い方について語っていただきました。次は、医療DXについてお聞きしていこうと思います。では、早速ですが、デジタルについて何か感じていることはありますでしょうか? 医療現場として、実はそれほど変化はなかったりしますか?
現状では、それほど変わっている気はしないですね。
やはりDXといっても、医療情報というのは病院の中で守っているものであって、あくまでイントラネットの中の世界で、言ってしまえば全部が要配慮個人情報(特に保護が必要な個人情報)です。これまで個人情報はいかに出さないか、という風にやってきたわけですね。ただ、それが政府の意向でいかに外と繋ぐかという方針に変わりました。
ですが、こうして病院の中にいるとあまり現実化はしていないと感じています。例えば、処方情報が見えるようになったという変化はありましたが、実際に医療をしている側からすると、処方情報があっても、それは患者が飲んでいるものとイコールである、という認識ではないんですよね。今、その薬を飲んでいないというのであれば、過去に出された処方情報になるわけで。そういった意味では、情報としては不十分なんですね。だから、現時点ではまだ課題が多いと感じています
―― そうなのですね。どちらかと言えば、厚労省や僕らのようなデジタル系の企業などが一方的に導入を推し進めている感じなのかもしれませんね。
そうは言っても、いかに情報を繋ぐか、というのは非常に大事なことだとは思っています。今、病院が持っている情報が基本的には全部デジタルなのに、その情報を病院間で受け渡すとなると、一旦プリントアウトして、アナログにする。で、それをまたデジタルに戻さなくちゃいけない。僕もずっとおかしなことだと思っています
―― 現状、法規制に合わせるとそのやり方になってしまっているんですよね。
なんだったら、いまだにファクスも使っていますからね。なんと前時代的なのだろうと思います。それがデジタルでやり取りできるようになったらもちろん良いとは思いますし、ただそれを病院間でピアツーピアではなく、いきなりクラウドにあげて……ということをしようと思うと、まだ道のりは遠いんだろうなと感じます。開業医の先生なんかは到底対応できない所もあるでしょうし、正直どうなってしまうのかなと
―― では、対スタッフの方とのやり取り、院内コミュニケーションという面で、デジタルによる変化は感じていますか?
今はそれほど感じていないです。
変化させようと思ったらスタッフ全員に業務用のiPhoneなどを持たせる必要があります。なので、基本的には電話での連絡が中心となっています。もちろん、カルテ上のメッセージボックスのようなものはありますし、電子カルテの端末で見られるグループウェアもありますが、確認が徹底されているとは言えず、情報の伝達に課題が残ります。こうした状況を改善するならば、個人に業務用のデバイスを持たせないと……ということになりますが、予算的な問題もありますし、検討段階といったところです
―― ドクターも含め、スタッフの方々の数を考えますと、そう簡単に導入できるものではないですよね。とはいえ、実際にiphoneがあれば、さまざまな面で便利なのではないでしょうか。
iPhoneを持っていれば、それが動いた時間を記録できますし、勤怠管理に使えますよね。個人毎の情報のやり取りもそうですが、病棟のフロア毎とか、診療科毎でグループを作れば、きめ細かい情報伝達ツールになると思っています
―― 一般企業と同様にコミュニケーションの効率化は大きなテーマなのですね。リアルな実情がうかがえました。
アプリを使った健康管理や診療につなげる難しさ

―― では、デジタル時代になったことで、対患者さんとのやり取りで変化を感じることはありますか?
そうですね……。
患者さんもデジタルである程度データを持ってくる時代にはなりましたけど、患者さんがスマホなどにメモしていたものを見せてくれる程度で、それほど変わってない気がします
―― しかも、そのデータの精度、という意味で言えば微妙なところも……。
そこですね。
慢性疾患であれば、日々の症状を患者さん自身が入力して医師へ共有するというようなアプリもありますけど、精度については課題があると感じています
―― そういったアプリで健康管理に繋げましょう、というのも今後の時代の潮流としては推し進める形になると思いますが、先生のように医師の視点で見ると精度の問題などもあるのですね。
症状をベースにする疾患なら、それでも良いんです。
でも、多くの患者さんが持ってきてくださる情報が、必ずしも客観的なデータと合うわけではないんですね。ただ、『○日は痛みが強い』『この日はむくんでいる』『むくんでいない』というような、患者さんが感じた記録が次の診療の元になっているようなものには合っていると思います
―― 使いどころによっては合う、ということですね。
その通りです。泌尿器科でいうなら、頻尿の患者が1日に何回排尿があったかを記録している場合、その情報が正確でなければ診断に活用できません。患者さんの記憶のみに従った情報は過少か過剰か、どちらかに偏っているという論文だってありますから、我々医師としては、記憶に頼った情報を鵜呑みにするのではなく、慎重に扱う必要があると考えています
―― ユーザーのデジタルリテラシーも人によってさまざまなので、難しいですね。また、裏側の仕組みも、不正や誤りを防ぐために細かく管理されているようですね。
なので、治験などでiPadを患者さんへ貸して日々データを入れてもらう時などは、結構シビアに入力してもらいます。というのは、それ位やらないと本当の意味で情報収集にならないからです
医師が今、必要としているのは事務的なサポート!
―― では、こうなったら良いだろうなと思うような理想についてはいかがでしょうか? セキュリティ面などは一旦無視していただいて、極論、ボタン一つで全病院の情報がつなげられるようなのでも構いません。
そういったものがあれば良いと思いますよね。
多くの先生がそのように感じているとは思います。よそから情報を貰うっていうのは非常に手間がかかりますし、まだまだハードルが高いです。逆もしかりで、他の病院から、患者さんが入院されたので治療の情報をください、という問い合わせがたくさん来るんです。一つ一つそれらを用意するのは、非常に大変です。その作業が何とかならないのかというのはずっと思っています。だったら、患者さん自身が情報を持てばいいだろうという考え方もあるとは思います。
でも、カルテの情報というのは分散していて入院~退院までの情報を集めたらファイル1冊ぐらい、非常に情報量が多くなってしまいます。そこからどうやって患者さんにそのエッセンスを伝えるのか……と考えたら難しいですよね。だからこそ、厚労省が共有すべき情報として指定している、退院時サマリーのような形式に落ち着いてしまうのですが
―― この辺りは、先生方みなさん同じ事を思っていらっしゃいますよね。ちなみに、こういった文書のフォーマットのボリューム感というのはどうなんでしょうか。「もっと書くべきだ!」と思ったりするものですか?
それは、どれぐらい書けば理解できるのかによると思います。
あとは患者さんがどれだけ濃密な治療を受けて来たのかにもよりますよね。イチから書き起こす人はほぼいないので、患者さん毎に何らかのサマリー的なものがありますので、それをいかにうまく活用するか。
でも、それは泌尿器科医が診れば分かるサマリーですから、対泌尿器科医へはほぼコピペで良いけれど、これを他の科の先生が見たら理解しづらいものになってしまいます。なので、そこはある程度はちゃんと読めるような形に翻訳して送らないといけないので、その負担はあります
―― 先生は、他の科の先生や専門医に文書を送る機会は多いのでしょうか?
頻繁にあります。そこで、相手が誰なのかによって、どうエディットするかは変わります。サマリーは基本、自分のために書いているものなので、他の科の先生などに送るのは手間がかかります
医師を支えるのは優秀なクラークか? それともAIか?

―― ということは、この辺りの作成代行をするクラーク(※)の必要性については、どのようにお考えでしょうか。
メディカルクラークの存在は非常に重要だと考えています。
十分な技量を持った方がいれば事務作業の一部を代行していただくことが可能ですが、専門性が求められるため、ポンと入れて直ぐにできるような仕事では絶対ないんですよね。でも、病院によってはクラークを置いていて、文書やカルテの下書きを行っているケースもあります
※メディカルクラーク:医療事務全般を担当し、医療関係者を支える職種
―― 近年では、こうした業務をAIで代替する動きも見られますが……。
AIは、文書作成支援の分野において最も導入しやすい技術の一つだと考えています。それこそ、紹介状なんて今は殆ど手書きではないので、パッとスキャンして文字起こしをして、それをAIがまとめてくれるんじゃないかと
―― ちなみに、先生はひと月にどの位、紹介状を書かれるのでしょう?
紹介状というか、一番多いのは、紹介してもらった病院への報告書ですね
―― 確か、報告というのは法的な義務ではなかったと思っていますが……。
開業医のお医者さんからすれば、患者さんを紹介したあと、どうなったか全く分からない病院より、『治療の結果はこのようになりました』と報告があった病院へ患者さんを送りますよね。それは患者さん自身の次の診療にとっても必要な情報ですし。僕は今、医療連携も担当していますので、外の先生にも会うことがあって、その時に『あの患者さん、どうなりました?』と聞かれて分からないと困りますから。
だからこそ、返事は書いておく。そうすることで、きちんと返事をくれる病院には次に患者さんが来た時も送ろう、ということになりますし。選ばれる病院になるためには、それなりの努力はしなければならないですし、重要なことだと考えています
医療技術の進化だけではなく、医療格差の是正も必須!
―― では、最後にDXに関して企業や行政に対して「こうしてほしい」と感じていることがあればお聞かせください。ツールの開発だけでなく、制度設計や旗振り役としての役割など、幅広い視点で構いません。
していただきたいことはたくさんあります。
例えば、日ごろの診療の中で自動化できることは色々ありますし、紹介状の文字起こし、退院サマリーや報告書を自動で作るのは、AI技術の活用によって効率化が期待される分野です。治療に関しては画像診断がかなり進んでいますよね。ただし、現実的な課題として、病院にお金が掛かるばかりで利益にならない。そこがネックだと思っています。
DXで国は電子カルテを標準化してちゃんと繋がるように改変して下さい、といって、それに病院が対応してもほぼお金にはならない。一応加算は付いているようですが。結局、国が旗は振っているけれど、病院側にとっては収益に直結しない取り組みだというのが正直なところです。確かに、電子カルテを繋げば人的な部分で間接的な手間は省けるので、そこで回収できるでしょう、と言われればそうなんですけれどね
―― あくまで管理コストの圧縮で、直接的な収益にはつながりにくいということですね。
はい。管理コストを圧縮することで、それを人件費に充てられると言えばそうですけど、初期投資が必要である以上、制度的な支援が不可欠です。あとは、そういったアプリケーションを作る企業さんには、便利な機能も良いのですが、それによって日本の医療全体の“均てん化(※)”に資するような視点を持っていただきたいと思っています。
例えば、手術を動画にするなら、他の病院の手法まで解析してもらえたら嬉しいですよね。この手術なら、これ位の出血で、このステップならこの位の時間で終わります、というような。それを見て、上手い医師ならここまでできそうだとか、標準化すればここは誰でも短い時間でできるというようなフィードバックができる仕組みがあれば、技術の向上と均質化に大きく貢献するはずです。そうした視点を含めた医療DXの推進に今後も期待しています
※均てん化:全国どこでもがんの標準的な専門医療を受けられるよう、医療技術等の格差の是正を図ること
―― 確かに、医療技術などの格差の是正という視点も重要ですね。ツールの開発などにおいては、そういった視点がより求められてくるのでしょうね。医師の視点からのお話を詳しくお聞かせいただき、大変参考になりました。ありがとうございました!
今回は、三井記念病院のみなさまにご協力いただき、第2回目のドクターインタビューを実施しました。 現在、AIなどが導入されつつある医療の最先端の現場で医師が何を必要としているのか、私たちがデジタルを通してやるべきことの方向性を確かめつつ、今後の業務に活かしていきたいと思います。また、今後もこのようなインタビューも実施していきますので、ぜひ期待してお待ちください。
※前回のドクターインタビューはコチラ!
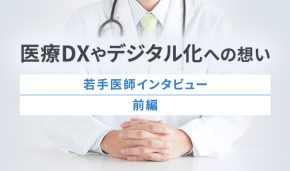
【若手医師インタビュー:前編】医療現場のデジタル化と未来の医療への想いを語る
2024.11.20
みなさん、こんにちは。広報担当です。今回のインタビューでは、実際に医療に携わる医療者がこれからの医療DXやデジタル化についてどのような想いを持っているか、現場でどの程度デジタルが普及しているかなどを東北の病院で緊急医療に […]
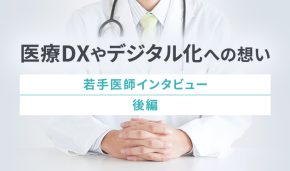
【若手医師インタビュー:後編】医師が求める情報とは何か?デジタル活用の現状を語る
2024.11.20
みなさん、こんにちは。広報担当です。今回の記事は、若手医師インタビューシリーズの後編となります。前編では、医療DXと言われているいま、実際の医療現場のデジタル活用がどうなっているのか、MRの動きは変ったのか? などについ […]
この記事の担当者

内海 篤人/Uchiumi Atsuto
職種:プロデューサー
入社年:2023年
経歴:Web業界(企画・ディレクター)→ゲーム業界(プランナー・カスタマサポート)→ヘルステック企業(カスタマーサクセス・事業責任者)に従事