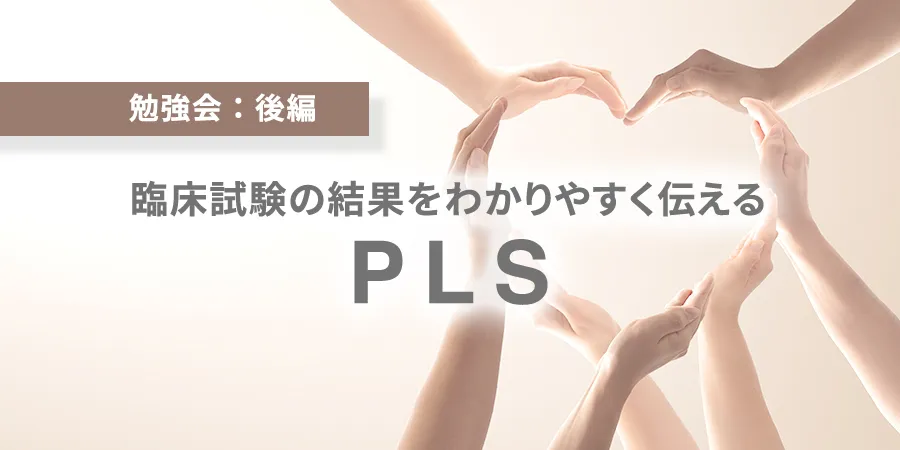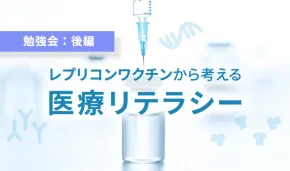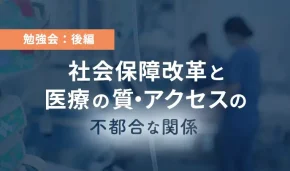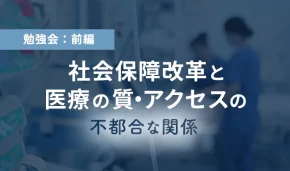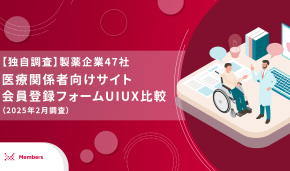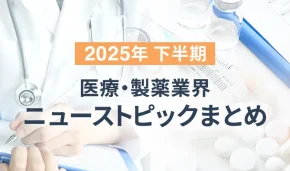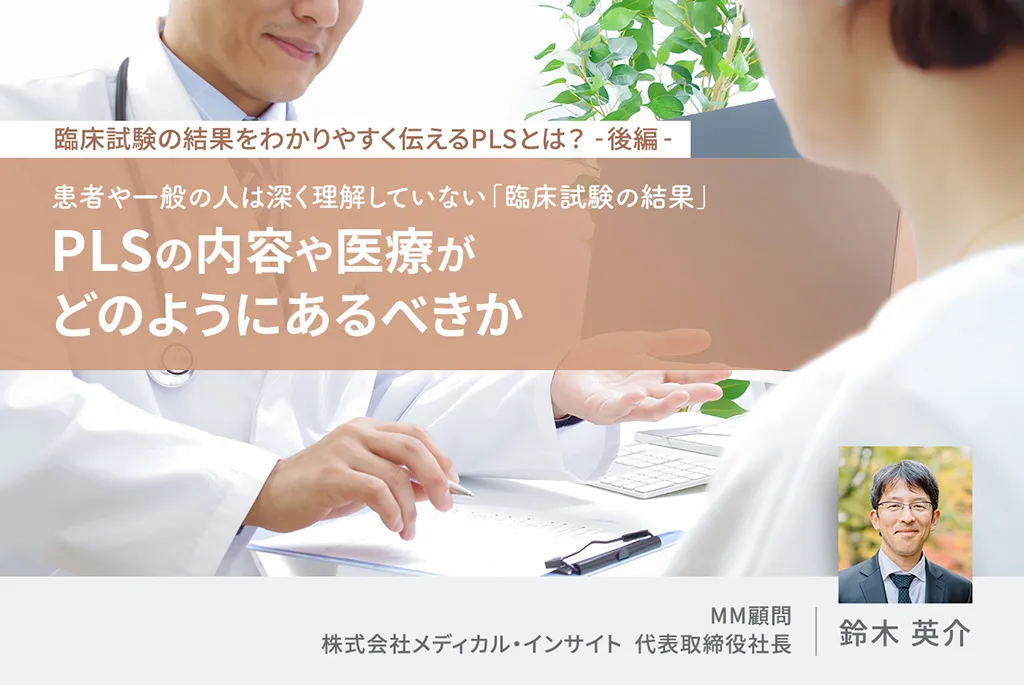
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。テーマは、まだ一般に広まっていない「プレーン・ランゲージ・サマリー(PLS)」について解説します。
後半は、PLSの内容や医療がどのようにあるべきかについて触れています。
前編はこちら
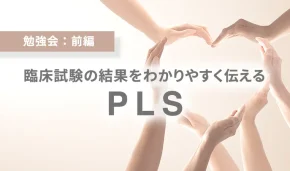
【勉強会:前編】臨床試験の結果をわかりやすく伝える「プレーン・ランゲージ・サマリー(PLS)」とは?
2025.04.14
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。テーマは、まだ新しい単語「プレーン・ランゲージ・サマリー(PLS)」について解説します。前半では […]
勉強会の参加者

2018年中途入社
営業
佐塚さん

2023年中途入社
プロデューサー
内海さん
臨床試験の結果を患者や一般の人は深く理解していない
では鈴木さん、後半もよろしくお願いします
よろしくお願いします。
では、改めてPLS(プレーン・ランゲージ・サマリー)の詳しいお話をしていきます。
前半の最後に触れたように、PLSは治験とかの結果を分かりやすく伝えるっていうことなんですが、
最初にお聞きしたいのですが、お2人は何らかの治験の結果とか論文とかって……見たことはありますか?
僕は正直、ないですね(笑)
ないですよね。というか、普通はないと思うんですよね(笑)
製薬メーカーさんが新しい薬を発売した時とか、その臨床試験データみたいなのがサイトで公開されたりはしていますが
そうですよね。
一般的なニュースに出てくるのは、基本的には薬が承認されましたっていう時に出てくるっていう感じです。
ご承知のように薬が承認されるためには、いわゆる3つのフェーズで治験が行われて、最終のフェーズ3の段階の治験の結果がポジティブ=ちゃんと上手く行きましたとなって、初めてそこで承認申請を製薬会社がして、その結果を国が審査して最終的には承認に至る。
なので、なんで承認されたのかっていう根拠となる話が、治験結果の中には当然入っています。
で、その結果に関しては医療者には論文の形などで提供するんですけど、患者さんとかご家族とかには『なぜ、この薬が良いのか』っていう根拠になるようなものが、しっかり伝わってない状態なのです。
特に日本の場合は、医療用医薬品の広告宣伝に対しての規制が強いというのがあります。だから、こういった情報提供の面で海外は先に進んでいるけれど、日本ではなかなか進まなかったというのもおそらくあるんじゃないのかなと思います。
でも、よくよく考えたら臨床試験の内容って医学論文として公表されているわけで、別に僕だって患者さんだって読もうと思えば読めるんですよね。なので、それを『製薬会社が言っちゃいけない』っていう風になっていること自体がどうなの?みたいな話もあります。
もう一つは、患者さんやご家族にとって、そこを理解しておくことが治療を選択するのにあたって実は結構大事な話になりうるよね、ということがあります。
例えば先生から『どっちの薬が良いですか?』みたいな話を振られた時に『この薬はこんな感じ、この薬こんな感じ』……ぐらいに、すごくざっくりとした説明は受けるけれども、もうちょっとしっかり知った上で選びたいという人がいても、おかしくはないと思うんです。
そんな中で出てきたPLSということで、じゃあ実際はどうなのかを、これは“ロルラチニブ”っていう薬に関してなんですが、ちょっと見てみましょう。(ファイザー製薬さんの記事を見ながら)
……なんか見た瞬間『わっ!』ってなってしまう感じですよね
専門用語だらけの臨床試験の結果を患者にどう見せる?

分かりやすい……ってどういうことなんだろうなって思っちゃいました(苦笑)
そうそうそう(笑)。
僕も正直、これを見てちょっと”あれ?”と思っちゃいました。
これが、そのCROWN試験の結果です。ちょっと要約部分を眺めてみてください
なんでしょう、省庁が作るような資料ですね
多分ですが、これはおそらく海外の資料をそのまま日本語訳をして全部載せました、みたいな感じだと思うんですね。
これがこのまま続くんですけど、この目的は何か、この論文は誰が読むべきか、依頼者は誰か、NSCLCとはetc……
う~ん。
確かに分かりやすくなってはいるところもあるのかなっていうような気もしますが……
原著論文を読むよりは分かりやすくなっていますけど、まあこんな感じで延々続きますと。
あ、『治験責任医師らはこの試験で何が分かった?』の部分が大事なところですけど、ここは分かりやすく書いていますね。
『がんが悪化していない人が全体の半数未満になるまでの期間』が一番メインのところなんですけど、『これらの人の半数以上はがんが悪化していないため、結果を見るのは時期尚早である。』……と。
でも、これってだから何?みたいな(笑)。こんな感じで書かれています。
で、まだまだまだ書いてあります。『5年後の時点でがんが悪化しなかった割合』とか、副作用に関しても書いてあって、ずっと続いていく。図を使って説明するのは分かりやすくて良いかなと思いますけどね。
で、最後にサマリーとして『この試験結果が何を意味するのか』があると。こんな感じです。
どうでしょう?プレーン・ランゲージ・サマリーを見ていただいた感じは(笑)
これを読み解くだけで労力を結構使うっていう……
僕もそうですね……。
ちなみに各疾患の薬剤の臨床試験のPLSってコンテンツ化することとかっていうのは禁じられているんですか?
いや、今までは製薬会社として遠慮してきたっていうことかなと。
広告になっちゃうんじゃないかなみたいな
むしろこれだけ見にくくてありがたいなあっていうのがあって……。
いや、これをどうするかは、我々の仕事かなっていう観点がありまして(笑)
そういうことはあり得ますよね。
これ、もう一段ちゃんと分かりやすくしなかったら、ちょっときついよね、みたいなのはありますから。やっぱり製薬会社って、正確に漏れなく伝えなければいけないという話にどうしてもなっちゃうので。
ちなみに原著論文もあるので、それをお見せします。(原著論文を画面共有しながら)これが元々の論文ですね。
『Journal of Clinical Oncology』というのがあるんですけれど、ここにあるアブストラクト(Abstract)っていうのは、いわゆる治験概要ですね。アブストラクトをまとめてあげれば良いんじゃないかっていう話なんですけどね。ちゃんと原著にはコンテキストやまとめがあるんです。
なので、そこをもうちょっと見やすくしてあげればいいんじゃないみたいな。(延々スクロールしながら)…と、こんな感じです。よく医師向けに出すような、こういうグラフは(サイト内のグラフを見ながら)出してないですね。こんな感じでセーフティ(安全性)とか全部掲載されています。
まあ、下に行けば行くほど、なんかもう大変だ……みたいな感じなんですけど(笑)。
だから、これを分かりやすく日本語にするっていうのは大事なことかなと思いますが、それを分かりやすくしたものがさっきのファイザーさんの内容っていうことですね
専門知識が十分に無いと何を言われているのか分からなくなりますね……
実は僕もこの話に関してメルマガに書いているので、どんな風に書いたかっていうのを、ご参考までにこちらも共有したいと思います。(鈴木氏のnote記事を画面共有しながら)。
これは去年の10月31日に出したメルマガで『肺がんで続く、分子標的薬の劇的な進化』という話で書いていまして。
で、前半はちょっと違うEGFRの変異に対する薬の話を書いているんですが、後半から書いた部分ですね。
肺がんの遺伝子変異でEGFRっていう一番多い遺伝子変異があるんですが、もう1つALKっていうのがあるんです。ALKは3~5%程度で、そんなにいっぱいあるわけじゃないんですけど。その第一世代っていうクリゾチニブは、さっきの治験の比較対象として出てきたと思うんですけど。
で、その後第二世代としてアレクチニブとセリニチブが出てきて。で、アレクチニブはクリゾチニブとガチンコ勝負をして圧勝しました。そうして天下を取ったんですね。で、そこに出てきたのがロルラチニブという第三世代です。
で、ここにさっき出てきた治験結果をそのままリンクを貼っているんですけど、アレクチニブと同じようにクリゾチニブとガチンコ勝負をして、先ほども出てきた、無憎悪生存期間(PFS)が『何も言えません』っていうのがあったと思うんですが、PFSがクリゾチニブが10.2ヶ月に対してロルラチニブが“Not Reached”。
ということは、ロルラチニブは5年経ってもまだ半数以上が無憎悪、つまり、良い状態のままです。ということで、ロルラチニブのPFSは60ヶ月(5年)以上になることが確定です
……みたいな話で、実はものすごく差があるんですよ。60カ月以上vs10.2ヵ月って、圧勝どころか、こんなに差が付くケースはまず見ないんですよね。
あとは安全性の話などを書いたんですけど、これぐらいにまとめると意味合いも分かるようになると思いますが、残念ながら製薬会社はここまで書けません。
なぜかというと自社の薬の事しか書けないから。このメルマガのようにアレクチニブの話とかは書けないんですよ。
なので、やっぱり治験結果をもっと分かりやすく伝えた方が良いけれど、PLSも今の状態だとまだちょっと中途半端ですよねっていう話が一つと、そうは言っても文脈をちゃんと伝えるっていうことが患者さんの理解のためには必要ですということ。
これは多分製薬会社ではできないというか、やっちゃいけないことになっているんで、だから僕みたいな第三者が、じゃあどう解釈したら良いのか?という話を書くことの意味はあるのかなと思っています。
患者さんにとってはここまで書かないと、そのお薬の持つ意味とかなかなか分からないかなと思うので、その辺のかゆい所まで手を届かせるにはどうしたら良いかについては、まだまだ工夫のしようがあるかなと思います。
今日のテーマのPLSの話については以上ですが、どうですか?お2人の感想とか
「患者中心主義」で医療の在り方をより良く変える
これは欧州の方では基本的に義務化されているものなのでしょうか
はい、そうですね。おっしゃる通りですね
鈴木さんがご存じだったらで良いんですけど、このPLSを作ることに対して欧州の製薬メーカーさんって結構ウェルカムですか?
それともだるいな……みたいな(笑)
いや、ウェルカムだと思います。
というか、患者さんにも分かっておいてもらいたいというのは、当然あると思うので
日本のメーカーだとどう思ってますでしょうか?
まあ、やっぱりちょっとおよび腰と言えば、および腰でしょうね。
でもさっき佐塚さんも前半の頭の方でおっしゃってくださいましたけど、ペイシェント・セントリシティ(患者中心主義)っていう考え方はだんだん浸透しつつあるので、こういうのもやってかなきゃいけないよねって話は、共通認識として出てきていると思います。
あと、そういう意味で言うと、治験の時に、製薬会社というよりはその治験を実施する病院側の方なんですけれども、患者さんに対してその治験の中身を説明して同意を取得するっていうプロセスが必要になるんですが、その説明文書であったり、同意を取得するときの文書ですね。それがやたらと長くて専門用語がブワッと出てきて(笑)。
手術の同意書とかもそうですけど、要はなんなの?みたいになって、サインすれば良いんでしょう?みたいな感じになっているものって結構あると思うんですけどね
過去に、親父の入院時の資料で見たことあります。
サインはしましたけど、なんか英語のドキュメントで何十ページもあって見る気もしないし……
結局はサインするしかないんでしょ?っていう(笑)。
ただ、治験の場合は特に患者さんが本当の意味で理解した上で参加してくれる必要があると思うんですよね。なので、そこをもっと分かりやすい文章に変えてくれ、みたいな話が結構あります。
患者さんが治験の審査委員という形で入っていくケースがだいぶ最近増えてきたので、その中で患者さんにもっと分かりやすい言葉で書いてくださいっていう要望は出てきていて。今ちょっとずつですけれども、患者さんが分かる言葉で書く、みたいなところは少し変わりつつあるかなと思いますね。
それでもやっぱり専門用語が多すぎるのは確かなので、そこを何とかしたいですが。今だったら、AIに書かせたら一発で書けるんじゃないかなとも思うんですけどね(笑)
それは思っていました(笑)。
ただ僕個人は、というところですけれど、確かにその製薬メーカーや病院側にも『すごく分かりにくいよね』という話は簡単に投げかけることはできますけど、患者さん側もやっぱり知る努力というか、知ることができるツールがいっぱいあるので、そういったリテラシーを上げる必要性もあるのかなと。
『もっと知ろう!』みたいな、相互の歩み寄りがない限りはなかなか難しいと思いますけどね
そうですね。
でも先生たちが良く言うのは、最近の患者さんはすごく勉強してくるようになってきているということ。
当然ウェブ上で色んなものを調べられるようになってきましたから。ただ、その中でちゃんとした理解が進むようなコンテンツがもっと流れてくるようにしておくべきなんだろうなとは思います。
僕がメルマガをやっているのはそういう思想で、学術論文とか出てくるような中でも、『これは患者さん知っておいた方が良いよね』とか『こういう話は面白いよね』っていうのを取り上げて、なるべく分かりやすい言葉で書いていくことをしています
ありがとうございます。
知ろうという気持ちがある方は、良い情報をちゃんとピックアップしている場面もありますね
お2人は、業界の人で市川衛さんというジャーナリストのお名前は聞いたことありますか?元々はNHKの方で、今の所属はREADYFOR株式会社っていう方なんですけどね。
彼は東大の医学部出身だけどNHKに就職して、一般の人に医療をわかりやすく伝えるっていうことをミッションにしていて、ご自身のことを“医療の翻訳家”と名乗りながらブランディングをしていて。結構、色んなウェブサイトとか……Yahoo!のコメントとかでも出てきます。色んな記事を書かれているので、みなさんも目にされたことがあるかもしれないです。僕も彼の考え方にすごく近くて。
だから、本当の意味での翻訳=患者さんに分かる言葉で伝えるっていうことはまだまだ続けていきたいなと思っています。
では話を戻して、お2人はなんかこう、医療を受けたりしたとき、ご自身やご家族で『なんか分からないな』とか『もうちょっとこうしてもらえたら良いんだけどな』みたいに思う場面はありますか?
医療現場と患者間の「ギャップ」をどう埋めるべき?

僕はずっと前から言っていますが、本題から少しずれてしまうんですけど、いざ入院したりとか、診察を受けるっていう時に時間であったりルーティン制度みたいなところは本当に余計なストレスしか掛からないので、そこをどう変えていくのかって思うことはありますね。
待ち時間とか転院する手続きの根回しとか諸々含めて、になると思うんですけど、それに関してはずっと思っています
そうですね。手続き書類がやたらと多いというのはありますよね
今まさに母親が転院をするんですが、そもそも救急搬送された時も病院が見つからなくて。
朝4時半に叩き起こされて、その後2時間待たされたという……。よく話で聞いたりしますが、実体験すると思ってなかったので
そうそう。
僕ももちろん病院にも色んな事情があるのは分かっているんですけど、うちの娘がこの間、病院に行ったときに待ち時間が1時間30分ぐらいだったんです。2名いるドクターの1名がちょっと遅刻したのか、1名体制になっちゃったんですね。で、3~ 4分ぐらいで診察が終わったわけですよ(笑)。
診察が終わった時に娘が『これだけだったのに、こんなに待つの?』って。その質問に上手く答えられなかったです
そうですね……。
まあそこはすごく難しいところで、需要と供給という意味で言うと、供給側が本当にパンクしちゃっているっていうのが実際起きているんですよね。
でも、難しいですよね。その需要と供給のバランスをちゃんと合うような形で、その医療リソースをうまい具合に割けるようにするかっていうのは。
それこそ、以前の勉強会で“直美(チョクビ)”の話とかもありましたけれども、これも結局、直美の先生が増えているイコール、非常に需要の高い診療科の医師の供給がどんどん減るって話になってくるんで、やっぱりそこをどうするのかってことは待ったなしできちんと考えていかないといけませんね。
だけど、これは制度設計とか少し違う話になってしまうので、僕らがなんとかできる話じゃないんですけれども、おっしゃる通りだとは思います

【勉強会:前編】増加する「直美」から日本の医療における構造的問題を考える
2025.03.19
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。テーマは、「日本の医療における構造的問題」について、増加する「直美」の医師の話題に絡めてお届けし […]
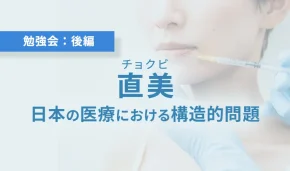
【勉強会:後編】増加する「直美」の医師から日本の医療における構造的問題を考える
2025.03.19
私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。後半も引き続き「日本の医療における構造的問題」について、「直美」の医師の増加にスポットを当てつつ […]
僕は医療機関だけの問題じゃなくて、一般企業に勤める人も1週間の内に1日休みを増やせばいいのにと思います。医療機関が混んでいても土曜日にしか行けないっていう人も、お休みが増えたら分散するのになぁと。
この間、週休3日制にして水曜日休みにしたら、基本的には『前日休み』と『翌日が休み』が毎日続くよねっていう記事を見て確かになぁと思いました。
月曜日は、昨日休みだから頑張ろう、火曜日は明日休みだから頑張ろう……みたいな(笑)。週休3日になったら病院に行く時間も確保できますよね。まぁでも、休みのフォローはどうするんだって話になるんですけど(笑)。
すみません、ちょっと話が飛びました
いえいえ(笑)。じゃあ、今日はこんなところですかね。
でもPLS的な考え方はこれから広がっていくと思いますし、みなさんにとってもチャンスのある話になりうるかなと思います。それこそ『こういう形で見せたらいいですよね!』みたいな提案って、資材だけじゃなくて動画にするとか全然ありかなと思います。色々と面白く考えていければ良いんじゃないかなと思いました。
では、今日は以上となります
佐塚さん、内海さん「ありがとうございました!」
―― 今回は、プレーンランゲージサマリー(PLS)についての勉強会レポートをお届けしました。
医療が患者中心になっていく中で、PLSは重要視されていくことが考えられます。PLSの広がりとともに、現在の日本の医療の状況や背景を理解することが大切です。
今後もホットな話題をお届けしますので、ぜひご期待ください。
この記事の担当者

佐塚 亮/Satsuka Ryo
職種:sales
入社年:2020年
経歴:大手スポーツメーカにて店舗sales,エリアマネージメント業務を担当。のちWEB制作会社にてWEBサイトの提案からディレクションをこなし、コンサルタントとしてサイト立ち上げ後の売上向上まで支援。その後2020年にメンバーズへ入社。主にクライアントからのヒアリング及び検証データを基に要件定義を行い、サイトの構築運用を実施。定常的に支援サポートを行う。クライアントはもちろんエンドユーザーの立場・視点に立ち、問題抽出から改善案の立案までを手がける